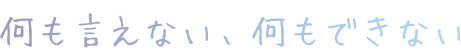  定期テスト最終日も無事終わった。途端にざわめき出す教室。まだ来週からテスト返却と言う恐ろしいイベントが待っていると言うのに、帰宅部組はこれから遊びに行く算段をしているらしい。俺たち野球部は当然、テストさえ終われば練習は即再開だ。たった数日なのに、随分長い間離れていたような気がする。 俺にとってもにとっても、いよいよ、という時期がやって来る。今年のインターハイは神奈川であるらしく、「予算的にラッキーだった」とは言っている。バドミントン部の年予算は大分少ないらしい。 「お、どっか行くのか?」 テストが終わると早々に、しかし鞄も持たずに席を立つ。思わず声をかけると、「呼び出された」と簡潔に一言。呼び出されたって誰にだ。そういや前に女子のグループに呼び出されたと噂で聞いた。もしやその続きなのか。だとしたら、今度こそやばくないのか。 大丈夫か、と聞くが「何が?」といつもの声のトーンで返って来る。平然と、しかしそのたった一言には「御幸くんには関係ないよ」という意味が込められているようで、それ以上は追求できなかった。 けれど、やはり心配だ。部活が始まるまではまだ時間がある。どうしても気になって、重い足取りで教室を出て行くを尾行することにした。見つかったらその時はその時だ。大会前にに何かあってからでは遅い。 そうして辿り着いたのは人気のない中庭だった。そこにいたのは、想像していた女子グループではなく、一人の男子生徒。いやまさか、と思いながらも死角に入って聞き耳を立てる。男子生徒の方は「突然呼び出してごめん」というありがちな台詞を吐いた。 「それで、用件は」 いや、絶対分かってるだろ。緊張でガチガチになっている相手を前に、相変わらずの返事をする。おかしくて思わず噴き出しそうになった。 「俺と付き合って欲しい」 「ごめん、無理」 相手からの告白に一秒もかからず即答した。本当にはどこまでもである。断り方も容赦ない。まあ、多分そう言う所も含めて俺はが好きなんだろうけど。飽くまで俺はに気持ちを伝えるつもりはないし、あの男子生徒のことは完全に他人事だ。何かややこしいことでもあったなら出て行くべきかと思ったが、これくらいの用件で俺が出て行かなければならないことにはならないだろう。 そう思い踵を返そうとしたその時、突然男子生徒の声が大きくなる。 「な…なんでだよ!バドミントン部なんてうちは全国区じゃないし片手間でいいだろ?野球部じゃあるまいし!」 どうやら、相手もしつこいらしい。恐らくは交際を断る理由に部活を挙げたのだろう。らしい、嘘も誤魔化しもない真っ直ぐな理由だ。だが相手も一向に引く様子はない。それより、正直言ってあの男子生徒、のどこがいいのだろうか。友達も倉持くらいしかいない、クラスでも浮いているし、正直、顔も並みだ。ずば抜けて美人でもなければスタイルがものすごく良い訳でもない。 じゃあ俺はと聞かれれば、そんなもの直感としか言いようがないが。話す内にバドミントンに対する思いだとか、俺にだけ見せた涙だとか、たった一度だけ頬を染めて笑って見せた所だとか、好きな所はいくらでも出て来る。 けれど、あの生徒はと接点なんてないだろう。それなのに、一体なぜ。適当に彼女ってポジションの人間が欲しいだけなのか。それともタチの悪い罰ゲームか。 「私は今のバドミントン部で来年も全国へ行く。それは変わらない」 「普通の高校生活捨てるのかよ!?」 「私は…」 は嘘をつかない。こんな奴相手に何も本音を晒すことなんてないのに。恐らく、上手な躱し方を知らないだけなのだろうが。 「私はバドミントンを始めた時からバドミントンしか見てない。これから先もそう」 「な…っ」 これじゃ埒が明かないな。放って帰らなくて良かった、尾行しておいて良かった。もうここまで来たら俺が出て行って止めるしかないだろう。これ以上相手が何を言った所での口からはバドミントンしか出て来ない。馬鹿の一つ覚えみたいに。 「おーい、その辺でやめとけって」 突然出て来た俺を見て、男子生徒はもちろん、も目を見開いて驚く。そんな驚いた顔を見るなんて初めてだ。これはラッキーかも知れない。しかしこの男子生徒、うちのクラスの生徒じゃない。だったら尚更何がきっかけでに目を付けたのだか。謎の多い呼び出しだ。 俺は溜め息をつきながらを親指で指しながら言う。 「こいつ見た目はどうか知らねぇけど、口も態度も悪いぜ?他当たれって」 「お前なんだよ!さんの彼氏でもない癖に!」 まあそりゃそうだよな―――面倒臭いと思いながら溜め息をつく。ここまでがNOを連発しているんだからとっとと諦めればいいのに。見込みはなんて俺も含めて最初から誰にもないんだ。の目にはバドミントンしか映っていないから。 とりあえず、の部活に対する思いを踏みにじるような発言があったことには腹が立ったため、挑発するようにの腕を引いて言ってやった。 「ま、今はな」 * ある程度の所まで来たら、の手を離した。これでまだにちょっかい掛けて来るようだったらもう少し対策をした方が良さそうだけれど、そこまでの根性はなさそうだ。これでもすっきり部活に打ち込めるだろう。 すると、後ろから声がかかって来た。少し、動揺しているような。 「ちょっと…さっきのどういうつもり」 「なかなか演技上手かっただろ?」 「…………」 何か言いたげな顔をしているが、何も言って来ない。俺を訝しむというよりは、俺に何か言いたいのに躊躇っているような、そんな雰囲気だ。 教室に戻って来て時計を見るが、まだ時間には余裕がある。テスト期間終了日の今日は、もう既に教室は空っぽになっていた。どこからか生徒の声は聞こえるものの、うちのクラスにはもう俺たち以外の生徒は誰もいない。そんな中で、は鞄を準備しながらぽつりと吐き出した。 「そんなにおかしいかな」 「何が」 「この学校のバド部で全国を狙うって。高校三年間も、その先もバドミントンで生きるって」 意外だった。あんな奴の言葉を気にしていたのか。いや、思えばはバドミントン部のことであれこれ言われていた。のいない所で胸糞悪い話をしているのを聞いたこともある。きっと自身も色んな噂を耳にはしているのだろう。だから、には人が寄りつかない。俺や倉持以外は。自分が周りに良い印象を持たれていないことを知っているから、歩み寄ることもしない。クラスに馴染むことを諦めているのだ。それは俺も人のことを言えたものではないけれども。 そういうことがじわりじわりとの心を侵食していたのだとしたら。の気持ちや覚悟の中の弱い部分を少しずつ傷付けていたとしたら。ちゃんと弱い部分も持っているが、いつか折れてしまったって不思議ではない。 「おかしくなんかねぇだろ」 「……ん」 「好きなんだろ、バドミントン」 「うん、好き」 「それをやりたくて青道に来たんだろ」 「…うん」 じゃあいいんじゃねえの、廻り何か。最後にそう言って、少し躊躇ったがの頭のてっぺんをくしゃりと撫でてやる。思った以上に柔らかいその髪は、するりと指の隙間をすり抜けた。わざと少し乱暴に撫でてやったのに、すぐにの手櫛で元通りになる。 こんな時、どう励ますのが正解なのか、やっぱり分からない。マウンドにいるピッチャーをその気にさせることだけはできるのに、どうして普段同じようにできないのか。今だって、は一人で悩んでいる。背中を押してくれる誰かはいない。倉持は友人だが深い事情を知っている訳ではない。だったら、中学時代のことも話してくれた俺が、気の利く言葉の一つや二つ、掛けてやるべきなのに。 だがいつまでもだらだらと居残っている訳にはいかない。俺ももこれからまた部活なのだ。一緒に教室を出ようとすると、「御幸くん」と再び引きとめられる。しかも、俺の鞄を引っ張って。少し俯き気味に、何かを言おうと数回口を開いたり目線を左右に彷徨わせる。 「まだ何かあるのかー」 言いやすいようにわざと軽く言ってやると、更に鞄をぎゅっと引っ張る。それだけでの緊張が伝わって来る気がした。そしてぼそぼそと、耳を澄まさなければ聞こえないような声では言った。 「さっきはありがとう。嘘でも嬉しかった。…それじゃ」 そう言い残して、足早に教室を一人出て行く。俺を置いて。そんなの背を、俺は見送るしかできない。追い掛けて、あの細い手首を掴んで、「好きだ」なんて言うことはできない。だから、思い出す。さっき触れたばかりのの髪の感触を思い出し、右手を見つめた。 「嘘か…」 半分本気だった、と言わなければそれこそ嘘になる。本当は、の“特別な一人”になりたいのに。 (2014/06/25) ←  → →
|