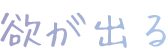  真っ赤に目を腫らしたを家まで送って行った次の日、いつもと変わらない顔では学校にやって来た。帰宅後すぐに冷やすか何かしたのだろう、昨日あんなにも俺に見せた隙も弱さもない。「今日は遅いな」と声をかけると「いつもと同じくらい」と淡泊な返事が返って来る。けれど、これまでほど声に棘もなく、完全に元気が戻った訳ではないようだった。いつものように静かに席に着き、ぴんと伸ばした背筋で授業を受ける。授業を退屈そうに受けることも、転寝するようなこともない。けれどその背中は以前とはどう考えても違って見えた。 「が泣いてるとこって見たことあるか?」 が部活の先輩に呼ばれている間に、目当てでやって来た倉持に聞いてみた。「はっ!昨日帰りが遅かったのはもしかして御幸テメェ…!」なんて、期待を裏切らない誤解と無実の罪を着せられそうになったのでとりあえずちゃんと否定をしておく。からべたべた触って来たことは一回だけあったが、俺からに触るなんてことは昨日が初めてだ。しかも泣いているの手を握ってやるだけで精一杯だった。 詮索されることは嫌いだと言っていたし、個人的な問題なので詳しくは倉持には話せない。話せるならとっくに話しているだろう。けれど昨日の感じからするに、誰にも言ったことがない様子だった。中学時代に起きたことは。 じゃあ俺は、これからどうに接すれば良いのか。倉持とはお互い友人だと認め合っているが、俺の立ち位置は一体どこにある。 「が泣いたのかを泣かせたのかとりあえず聞かせろ」 「が話の途中で泣き始めた」 「ふーん…」 そう言って、現在空席となっているの席に座り、俺の方を向く。すると、今度は倉持が訊ねて来た。 「なあ、の携帯の待ち受け画像見たか?」 「まずが学校で携帯を触っている所を見たことがねーんだけど」 「ヒャハハッ、そりゃそうだろうな!」 なんだ、その嬉しそうな顔は。まるで仕返しとでも言いたげに笑う倉持に顔が引き攣る。勘の良い倉持のことだ、何か察してはいるのだろう。だがその待ち受け画像が何なのか教えてはくれないようだ。そりゃあそうだろう、こっちだって詳しく事情を話していないのだから。けれど、倉持が知っていて俺は知らないことがあると言うのは無性に腹立たしい。俺は別に、の友人と認められたわけでもなく、知らないことの方が多くて当然のはずなのに。 と関われば関わるほど女々しい部分が顔を覗かせる。それもあってなんだかイライラしてしまう。 「ちなみに俺はの泣いてる所なんて見たことねぇよ。てか想像もつかねえ」 「今日の見てみろよ、様子が明らかに変だ」 「まあこの間から変だったけどな。今日は割と普通だろ」 「もう会ったのかよ」 「朝」 それで教室に入って来たのが遅かったのか。本人はいつも通りとは言っていたが、どう考えてもいつもより遅めだったのだ。昨日あんなことがあったとはいえ、寝過ごすなんて、それこそに関しては想像できない。どうやら倉持と話し込んでいたらしい。 倉持は知っているのだろうか、のラケットが折られたことを。もしあの件を知っていたらの次に怒りそうなのは倉持だ。だから知っていたら何かしらしそうなものではあるが、倉持もいつも通りである。ということは、やはりは倉持に話していないと考えた方が良さそうだ。変に倉持相手に探りを入れて言及されても、俺だって今は上手く躱す自信があまりない。 そしてものの十分ほどでは教室に戻って来た。開口一番、「そこ私の席」といつもの調子で倉持に話しかける。いつもの調子、に見える。一見そうだが、やはりよく見ると違う。覇気がないのは元々だが、何か違和感を拭い去れない。 「部活の用事か?」 「うん、壮行会に女子バド部も出るって」 「そりゃそうだろ、挨拶はがすんのか?」 「さあ…キャプテンじゃないの、そういうのって」 「でもインターハイ出るのはだろ」 「まあ、そうだけど」 目の前で繰り広げられる会話はごくごく普通のものだ。日常的なものだ。不自然なやり取りは一つもない。けれど何か、何かがいつもと違う。 (…あ) 俺と一つも目が合わない。 「ということはもうすぐ定期試験ということか」 「倉持赤点だけは取っちゃ駄目だよ」 「恐ろしくて取れねえよ」 「取りかねないから言ってるのに」 俺の方を一切見ようとしないし、会話に入れなさそうな雰囲気をがわざと作っている感じがする。これは本格的に避けられているのではないのか。それとも単に昨日の今日で一時的に気まずいだけか。俺としては当然、後者であって欲しい。しかも今すぐ元に戻って欲しい、昨日までと同じように。 まあそれも無理な話か、と小さく息をついた。誰だって思い出したくもない過去話をしてすぐに元通りになれと言われても無理話だ。こちらが強要した訳ではないにしても。少なくとも、はそういう人間だ。思いの外、弱い。思いの外、強い。矛盾した二面を持つは、不安定な天秤のようにぐらぐらと不安定に揺れている気がした。もうすぐ、大会だというのに。 「じゃあ俺クラス戻るから」 「うん」 「お前、御幸と喧嘩したなら早く仲直りしろよー」 「してないし」 「してねーよ」 偶然、声が被る。するとは一瞬俺の方を見たが、またすぐに倉持の方へ目線を戻してしまった。倉持派と言えば、「じゃ、大丈夫だろ」なんていう無責任な一言を残して自分の教室に戻って行く。そんな倉持に手を振る。 無責任な、とは思ったが、思い出せば昨日の俺も同じ言葉をにかけた。今年は大丈夫だろ、と何の保証も確信もないのに。ただ、その言葉しか出て来なかった。なんとなく、大丈夫なような気がしたから。バドミントンは嫌いになっていないし、ラケットも選んだ。先輩たちにも可愛がってもらっているようだし、インターハイへの出場の切符も掴んでいる。 けれど、俺との関係を「大丈夫だろ」と言われても、それとこれとは根本的に問題が違う。俺はいつも通りでいたいのに、がこんなではどうしようもない。 「」 「…なに」 「壮行会の挨拶一応考えとけよ」 「私に出番はないでしょ」 「無茶振りされる可能性もあるだろ」 「…ないことを願う」 「おいおい…」 どうせその内、校舎の壁面には“祝・女子バドミントン部シングルスインターハイ出場”なんて垂れ幕が飾られるに決まっている。青道高校始まって以来の快挙だというのに、マイペースと言うか何と言うか、自分のことなのに他人事のように言う。 いや、それでも心の内では一点に必死にしがみつき、勝つためならどこまでも努力をすることを知っている。だからこそ、この普段の無気力具合との差は今でも嘘なんじゃないかと思うほどだ。 「うちの本命はいつだって野球部なんだから、バド部は余興程度で良いのよ」 「その他大勢の生徒にはそうでも、俺や倉持にとったらバド部だって本命だろ」 「…あんまり、そういうことさらっと言わないでよ」 俯き加減に、ぼそりと呟く。黒い髪がさらりと落ちて、の顔の半分を隠してしまった。 まずい、プレッシャーをかけ過ぎたか。中学時代も常に重圧と闘いながら一人で勝ち抜いて来たには余計な一言だったかもしれない。咄嗟に謝ろうと口を開いたら、 「調子乗るし、期待するから、私。あんまり、言わないで」 ほんの少し、頬を染めながら消えそうな声でぽつりぽつりと言う。それを見て頬杖をついていた頭が、がくりと落ちた。が照れている。いや、プレッシャーになっていないならそれでいいのだが、さっきの言葉のどこに照れる要素があったというのだ。のことは好きだと自覚しているが、時々分からない。分からないからこそ面白い部分もあるが、これは本当に意外だった。またの口から毒が飛び出すことも覚悟したのに、拍子抜けだ。 どんどん、知らなかったの表情が見えて来る。見たことのなかったの一面を知って行く。その度にもっと知りたい、もっと見たいと膨らんで行く欲。まだ振り向いて欲しいとまでは言わない。けれど、ほんの少しで良いから意識して欲しいという気持ちは、ないとは言えない。今こうして目を合わせてくれないのは、僅かでも何かしら意識してくれていると思って良いのだろうか。 それきり無理矢理会話を打ち切ったの背中を見つめながら、かなり重症になって来たな、と思った。 (2014/06/20) ←  → →
|