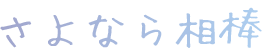  事件はある日の昼休みに起きた。その日はたまたま、本当に偶然は教室にラケットを持ち込んでいた。きっと昨日部活の後、部室のロッカーに返さず持ち帰ったのだろう。今朝またそれを持って登校し、そして偶然、昼休みに担任と面談があると言って席を外した。俺も野球部のミーティングに呼ばれていた。 その僅かな隙に、のラケットは狙われた。俺も外に出ていたから詳しくは知らない。予鈴の鳴る少し前、教室に戻るとは自分の席の前で立ち尽くしていた。そんなから距離を置き、取り囲むクラスメートたち。嫌な雰囲気だと思いながらそっと教室に入り、の傍まで寄る。そのことにすらは気付かない。よく見るとの顔は青褪めている。何かと思いの机を見れば。 (…んだよ、これ) 真っ二つに折られたのラケットがそこにはあった。ガットなら切れようがまた修理すればいい。だが素人でも分かる。折れたラケットは元には戻らないと。 「、」 「…痛かったね」 「……」 「昼休み、一緒に行けば良かったね」 二つに折れたラケットをそっと持ち上げ、抱き締める。それを遠巻きからクスクスと気色悪く笑う女子のグループがいた。この間、体育でにやられていた奴らだ。仕返しにしては度が過ぎる。顔面すれすれとはいえ、はあいつらの顔面に傷を付けるつもりもなかったし、挑発したのは寧ろ向こうだ。 だが腹の立つ俺とは裏腹に、には言い返す気力もない。ラケットケースに折れた相棒をしまうと、いつものように静かに席につき、次の授業の準備を始める。 「お…おい、」 俯くを泣いているのかと顔を覗き込むと、今まで見たことのない怒りをその目に宿していた。ライバルや対戦相手に向ける敵対心ではない、純粋な怒りだ。けれど肩を震わせ爆発させるのを抑えていた。まるで、痛いのは自分ではなくラケットだとでも言うように。犯人の目星はついているのだろう、だがは何も言わない。だから、俺も何も言うことができなかった。 そしてそのラケットの事件以来、目に見えての様子がおかしかった。何をしていてもぼうっとしている。普段から脱力感のある無気力な人間だが、そういうレベルじゃない。授業中も集中していないし、昼ごはんも食べているのかいないのかよく分からない。最近は楽しいと言っていた部活ですらぼうっとしているらしい。 あのラケットは恐らく、中学時代から相当一緒に戦ってきた相棒だったのだろう。そしてこれからもそのつもりだったのだろう。手入れを怠らなければ道具というのはどんどん手に馴染んで行く。部室にある控えのラケットでは駄目なのだ。 分かる気がした。俺だって野球をしている身だ。備品の大切さは分かっている。けれどにとって、あのラケットは心が折れそうだった中学時代の部活を共に戦ってきた唯一の相棒だったのだ。だがいつまでも落ち込んではいられないだろう。バドミントン部も野球部同様、大会は日に日に近付いて来ている。そんな腑抜けた面はじゃない。 「、明日部活か?」 「夕方までは…」 「部活終わるのは?」 「多分…六時」 「じゃ、七時に校門な」 「は…?」 「ちょっと買い物付き合えよ」 とか言って、本当はの買い物をさせる気なんだけど。ぼうっとしてるは、意味も分からずただ頷いていた。 * 「聞いてない」 「はっはっはっ、そりゃ言ってないからな」 無表情ながらもふて腐れオーラ全開の。それもそのはず。電車を乗り継いでを連れて来たのは、スポーツ用品店だったのだ。ここまで来たら流石に察したらしい、新しいラケットを選べということを。同じモデルでも違うモデルでもいい、とにかく早くには元通りになって欲しかった。そしてあの打ち返しようのないえげつないスマッシュや、まだ見たことのないコスいフェイントを楽しそうにするが見てみたいのだ。 「…手に馴染んだこれで、今年は戦い抜く気だった。グリップテープも昨日巻き直したばかり」 あれから肌身離さず折れたラケットを持ち歩いているはぽつりと言った。ぎゅっと抱きしめられたラケットケースの中には、無理矢理グリップテープでくっつけた不細工なの相棒が入っている。もう使えないと分かっていても、手離せないらしい。 「だったら早く選べよ、一日でも早く新しいのが手に馴染むように」 「簡単に言うね。他人事だから」 「…俺だって自分のグローブやられたら怒るだろうさ」 俺から見たらどのラケットも違いがよく分からない。だがこれだけ数があればきっと一本くらいの手に馴染むものがあるはずだ。そうやって誰もが選んでいるのだろう。どれだけ大事にしたって、形のあるものはいつか壊れる日が来る。の場合は故意に壊されてしまったが。 「けど立ち止まって勝利を逃してそいつは喜ぶのかよ。お前が全国狙っていることくらい、近くにいる奴らは分かってんだ」 そうしてようやく、は恐る恐る並ぶラケットに手を伸ばし始めた。握っては棚に戻し、また別のを取っては棚に戻す。振ってみたり、しなりを確かめてみたり、ガットの固さを確認してみたり。何がどう違うのか素人の俺にはさっぱり分からないが、まあ俺達にとっての自分専用バットやグローブと同じものだろう。 やがて、段々とラケットを見る目が輝き始める。新しいラケットを持ち、コートの上に立つ自分を想像しているのだろうか。それともあのえげつないスマッシュか、プッシュか、相手に考える隙を与えない素早いサーブか。 「…いい感じ」 「お、それ?」 「小学生の時からこのメーカー。みんなの憧れだった」 「ふーん。軽ぃの?」 「丁度いい」 持ってみる、と簡単に俺に手渡す。まあまだのものになってないからだろうが、こいつ、自分のラケットは意地でも貸さないタイプだろうな。 受け取ってみると、バットに比べたら当然だがラケットは軽かった。こんな軽いラケットでこいつはあんなスマッシュを打つのか。思わず避けてしまうような速くて重い音のするスマッシュを。 学校の備品は所詮備品で、に言わせれば安物だわ重いわガット緩いわグリップテープ剥がれているわで散々な状態らしい。使い物にならない、と溜め息をついていた。けれどその言葉の裏には「もっとちゃんと手入れしてやって欲しい」という気持ちが隠れている。自分のグリップテープで学校備品のラケットを直している所も俺は知っているのだ。 それを思うと、選手に選ばれたラケットは相当幸せだろうと思う。 「お金足りるかな…」 「足りなかったら多少貸すぜ」 「いい、最悪カード使う」 「お前カードなんか持ってんのかよ…」 「兄名義」 「まさか強奪…」 「人聞きの悪いこと言わないで。一人暮らしするって言ったら“貸して”くれたの」 新しいラケットを片手にレジへ向かうの背中は、いくらか機嫌よさ気に見えた。そして戻って来たの手には、真新しいラケットの入った袋。ここに来た時よりはどんよりとした空気はなくなっている。 「ラケットの寿命、知ってる?」 店を出ると、唐突にはそんなことを訊いて来た。当然そんなことを知らない俺は「いや」と答える。 「一年」 「え?」 「毎日部活で使っていれば、一年が良いとこ。買い替え時、てことだったのかもね」 「…………」 「昨年、中学最後の大会にこのラケットで挑んで、今年の夏にこれで出て…それで最後にしようと思ってた」 が言うには、大会が先か、ラケットがへばるのが先か、それくらいだったという。ラケットの寿命だと言われればそれまでだが、今回のような場合は不本意だっただろう。あれだけ怒りを面に出したも珍しい。今はもういつも通りの平静な空気が漂っているが、心のどこかには大きな傷を負ったに違いない。今も抱え込んでいるラケットのように。 駅のホームが近付く。ICカードでいつも通り改札を抜け、五分、十分毎にやって来る電車を待つ。すると、は電車を待つ人の列から下がった。不思議に思い隣にいるを見下ろすと、もこちらを見上げている。 「御幸くん、まだ時間大丈夫?」 「ああ、俺は大丈夫だけど」 「ちょっと話そっか」 そう言って、ホームに設置された椅子に目をやる。「電車が参ります、白線の内側までお下がり下さい」―――そんなアナウンスを聞きながら、俺とは人混みから離れる。教室の椅子と同じように、は駅の椅子にも静かに座る。電車の発車と共に、生温い風が通り抜けて行く。そしてホームにはまた、人がまばらになった。 ちらりと横目でを見る。相変わらず読めない表情で、向かいのホームを見る―――いや、何も映していないのかも知れない。どこにも焦点が合っていない。そんな中、ようやくぽつりと話し出した。 「私が初めて県大会に出場したのは、中学一年の時。優勝したのは、二年の時だった」 (2014/06/14) ←  → →
|