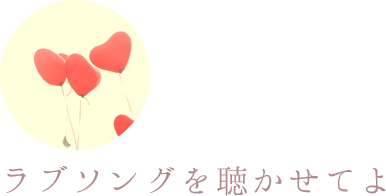 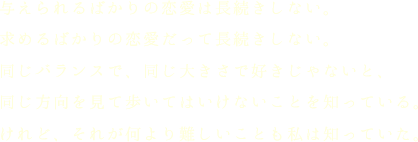 私は、食わず嫌いはしない方だ。読まず嫌いも聴かず嫌いもしない。だから、恋愛だってしたこともなくて「恋なんてしたくない」と言っている訳ではない。私だって高校生や学生の頃にはそれなりに恋愛をしていた。彼氏だっていなかった訳ではない。けれど、終わり方はいつも同じだった。最後の一線を先延ばしにしている内に浮気されて終了。「のペースでいいから」と最初はみんな同じことを言う。でも結局は待ってくれない。私のペースで歩かせてくれない相手にしか出会えなかった。けれど、今思えば私が相手に合わせる努力も必要だったのだろうか。そうすれば今頃、“恋をしない失恋歌い”なんて不名誉なキャッチフレーズをつけられなかったかも知れない。 「、今日の三曲目って新曲か?」 今日のステージが終わり、ハコの店長からチャージバックを受け取っていると、不意にそんなことを言われた。活動を始めたばかりの頃からお世話になっている店長には、新曲を見抜かれたらしい。どうも、最近は随分もやもやしており、その度に新しい曲を作っていた。それが私の最大のストレス発散方法なのだが、新しい曲でまだあまり歌い込めていないと、詰めが甘いのがバレてしまう。 「……微妙ですか」 「いや、かなりよかったんだがどうしたいきなり」 「え?」 「今までフィクションだった歌詞が急にノンフィクションになったぞ。生々しいってか、リアリティが出たって言うか」 「そ……そんなつもりはないんですけど!」 手帳に来月の出演日を書き込みながら、反射的に叫ぶ。 烏丸くんとあれこれあってからだなんて、そんなこと絶対に言えない。ちゃんにだって言えてないのだ。いや、疚しいことなんて何もない。何もないのに、あんな風に思わせぶりなことをされたら、いくらずっと年も下の男の子とは言え意識せずにはいられない。なぜか本部でエンカウントする回数が増え、その度に緊張している自分がいる。確かな言葉は一つも言われていないのに、遠回しな言い方から何も察することができないほど鈍感ではない。まともな恋愛をしたことがなくたって、向けられる淡い好意に気付かないような子どもでもない。烏丸くんが他の女の子へ向ける目と、私を見る時の目が違うことくらい分かる。私は、そういうことに敏感でないといけない仕事だから、余計だ。 どう接すればいいのか分からない。自販機での一件があって以来、目を見て話すことすらできないのだ。まるで刷り込みだ。仕事中にあの自販機の前を通るだけで、烏丸くんを思い出してしまう。けれど、もう「それならお試しで」なんて軽い気持ちで誰かと付き合うなんてできない。その先にあるのは、結局別れなのだ。どれだけ好きだと言われても、私が仕事と音楽をしていると二人での時間が作れず、その“お試し期間”が終わる前に終わりを告げられてしまう。もっと器用だったら上手くできるのだろうけれど、私はそんな器用な人間ではない。私は、私が傷付くのが嫌なだけだ。 お客さんも全員帰ったお店を出て、足はいつも通り駅へ向かう。 「さん?」 「え……?」 その途中、後ろから名前を呼ばれて思わず立ち止まる。私を“さん”なんて呼ぶ人は限られている。振り返らなくても十分、その声には心当たりがあった。どくんどくんと首が脈打つのを感じながら、ゆっくりその声の方を振り返った。 「今帰りですか」 「そうだけど……烏丸くんはバイト?」 「俺は玉狛の帰りです」 「そう……」 それじゃ、とここで別れるのも不自然な感じがして、流れで烏丸くんは私の隣に立つ。それだけでもう、私は冷や汗が止まらない気がした。勤務外で会って下さい、という言葉を拒んだ私を、それでも諦めていないらしい烏丸くんに、どんな顔を見せればいいのか本当はいつも分からない。だから俯くしかなくて、今はその表情を汲み取ることも、どんな目で私を見ているかも分からない。けれど、ずっと変わらない視線を送られているのだろうということは、なんとなく分かっていた。 「そうだ、さん」 「なに」 つい、冷たい声が出る。本当は冷たくしたい訳じゃなくて、上手く声が出なくて低い声を出してしまうだけだ。上ずってしまえば、緊張しているのが伝わってしまう。もしかしたら、烏丸くんは察しのいい子だから見透かしているのかも知れないけれど。 「これ、見付けたんですけど」 「なに……えっ!?」 私に向けられた携帯の画面には、私のライブ映像が流れていた。思わずその携帯を取り上げ、しっかりその動画を確認する。そりゃ、私は撮影禁止にしていないし、動画を撮影してくれるお客さんもいる。動画サイトにアップロードされていることも知っていた。私はエゴサーチなんてしていないから、いつのどの曲がアップロードされているのかまでは知らなかったが、それを見てみると割と最近のものである。私の知らない所で、一応同じ職場の人間に見られていたと思うと急に恥ずかしくなる。鳴っている動画を止めて烏丸くんに噛みついた。 「何検索してるの!?」 「さんが教えてくれたんで」 「あ……そう……」 急に気持ちが冷えて行く。ちゃんと、連絡を取っているらしい。あれ、でもどこでだろう。いつ二人は連絡先を交換したのだろう。頻繁に連絡し合っているのだろうか。いや、でもちゃんには彼氏がいると言っていた。だから、何も後ろめたいことはしていないだろう。 (あれ………) もやっと、した。灰色の雲が、ゆらゆらと揺れるような感じだ。今、すごく自分勝手なことを考えた。私に思わせぶりなことをしておいて、私にはあれ以来連絡一つ寄越さない癖に、他の女の子とは連絡を取っているんだ、と。付き合っている訳じゃないし、好きだと言われた訳でもない。勤務外で会って欲しいという言葉だって、もっとよく考えれば、例えば学校のことで悩みがあるとか、本部内では言いにくいことがあるとか、そういうことだったかも知れない。私は何を早とちりしていたのだろう。 携帯を烏丸くんに返す。ほんの少しだけ、指先を掠める。それだけでぴくりと人差し指が反応する。すると、様子がおかしいとでも思ったのか、「さん?」と言いながら顔を覗き込んで来る。久し振りにぴたりと焦点の合った双眸に、私の心拍数はたちまち上昇する。 「さんは酷いですね」 「え……?」 「俺から寄って行ったら逃げるのに、俺がちょっと離れるとそんな顔をする」 「ど、どんな顔よ……」 「泣きそうです」 指摘された通りだった。私が自ら拒んでおいて、こうしてちゃんと連絡を取っていたことを知るとショックを受ける。そんな風に思う筋合いは私にはないのに。それだったら、素直に烏丸くんの好意を受け取れば良いのだ。でも最後の良心と言えば良いのか、いや、臆病な心がそこに制止をかける。 「そんな顔するくらいなら、さんから俺のとこに来て下さい」 「な、何言ってんの」 「俺、これでも焦ってるんすけど」 「どこが……!」 「さんは大人だから、その内すぐ誰かのものになるんじゃないかって」 「そんなこと……烏丸くんに関係あるの?」 ああほら、また意地悪なことを言う。そんなことない、と言えば良いだけなのに、余計な一言で烏丸くんを遠ざけようとする。 この間、友人に相談をした。かなり年下の子に思わせぶりなことばかりされると。だからそれが気になって仕方なくて、どうしようもないと。返って来た答えは、「一度応えてみたら」だった。傷付いたらその時はその時で、きっと恋をしようと思えばまたいつでもできると。そんな風に思えないからここまで来たのにと言っても、「じゃあ今変わらなかったらいつチャンスが来るの?」とじろりと睨まれただけ。恋をしようと思えば、きっとできる。けれど、自分を本当に思ってくれる相手がそう都合良く何度も現れるとは限らない。多分、そういうことを言いたかったのだろうと思う。 そっと、烏丸くんの両手が私の両手に触れる。そして包むように少し力を込めて掴むと、同時に「こっち向いて下さい」という声が降って来る。 「俺がさんを好きだって言ったら、関係あることになりますか?」 「そ、れは……」 「俺、さんより年は下ですけど、さんが思ってるほど子どもじゃないですよ」 「…………」 「動画見ながら、この声が俺だけのものになればいいと思ったし、誰にも知られたくないと思ったし、他にも色々さんのこと考えました」 「い、色々ってなに……」 「言っていいんですか?」 「言わなくていい!」 泣きそうになりながら叫ぶ。一気に色んなことを言われて、頭が追いつかない。ここまで言われて、無下にできるような所には、私はもういなかったのだ。 「好きです、さん」 「……た、ぶん、わたし、も…」 「…今はそれでいいです」 そう言って小さく笑い、私の頭を撫でた彼の手は、確かに男の人の手のようだった。 ≪≪  ≫≫
≫≫(2016/04/11) |