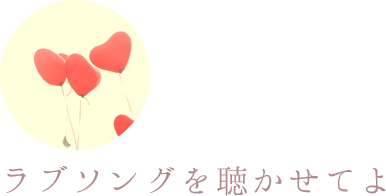 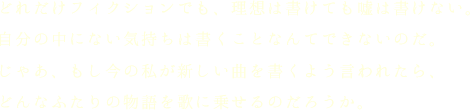 失敗したな、と思った。多分烏丸くんだって私をからかっただけに違いないのに、「やめといた方が良いよ」なんて、本気になって返してしまった。もっと軽く、大人の対応ならいくらでもできたはずだ。大人のはずが、大人じゃなかったのだろうか。 いつものように医療研究室にいられればよかったのだが、生憎今日は救護室の待機当番の日だった。滅多に怪我人なんて出ないここでの仕事は日がな座っているだけだ。そのため研究室からパソコンを持ち込んで別の仕事をしているのだが、こうも一人だと色々と考えてしまって仕方がない。いや、いつも通りの勤務だと逆に手につかなかったかも知れないが。 どういうことか、あれ以来ずっと烏丸くんのことを考えてしまっている。あんな高校生に、私のような二十歳すぎの女が、有り得ない。でも、ともすれば昨日触られた指の感触を思い出して、かあっと顔が熱くなる。 「いやいやいや……」 目の前の書類を捌きながら頭を振る。暫く異性にあんな風に触られることがなかったから緊張しただけだ。お客さんや店長と握手することはあっても、あんな、まるで恋しい相手に触れるかのように。 「いやいやいや!だから!」 思いっ切り机を叩いて立ち上がった。だめだ、仕事にならない。やっぱり今日は救護室待機で良かったのかも知れない。白衣のポケットから救護室の鍵を取り出し、早足で救護室を出る。 落ち着くために一度外に出よう。そうだ、自販機で私の好きなレモンティーでも買おう。まだホットも入っている時期だ。あれを飲めば大抵は落ち着ける。私に今一番必要なのは、そう、落ち着きだ。 救護室の鍵を閉める。ポケットの中に小銭と携帯だけ入っていることを確認する。ここから一番近い自販機を求めてとにかく歩く。歩いていても頭の中で昨日のことがリフレインする。振り切ることができない。言われたこと、されたこと、見せられた表情が頭の一番奥に貼りついて剥がれてくれない。 やがて自販機まで辿り着くと、少し震える手できっちり小銭を入れて、叩くようにレモンティーのボタンを押した。ガコン、という音と共に落ちて来た小さいペットボトルのレモンティー。自販機のすぐ横に座り込んで、その蓋を開けた。一口飲んで、深呼吸する。 (やだなあ……) 正直、もう恋愛なんてこりごりだと思っている。たとえそのせいでつまらない女だと言われようと構わなかった。漫画やドラマで恋愛をした気分にはなっていたし、人の話を聞いているだけでお腹いっぱいだ。私には今、恋愛をする必要性を感じなかった。それなのに、烏丸くんを惑わすようなことを言うから。 「さん?」 「へっ!?」 なぜ、こういう時に限って会いたくない人に会ってしまうのだろうか。顔を上げれば、今まさに私の頭を悩ませている人物が立っていた。自販機に隠れるように座りこんでいるのを見て不審に思ったのだろう、首を傾げて見せた。首を傾げたいのは私の方だ、彼は確か現在は玉狛支部に所属のはず。本部の、しかも医療・救護班区画に用事があるとは思えない。なぜ、なぜ、とそればかり繰り返される脳内とは裏腹に、口から出て来た言葉は「昨日ぶり……」だった。わざわざ自ら昨日を思い出すようなことを言ってしまった。後悔とは、なぜ先に立ってくれないのだろうか。烏丸くんは「そうですね」と言うと私と同じように自販機に小銭を入れて、何か飲み物を買った。そして。 「……いや、待って待って」 「なんですか」 「なんで横に座るの」 「さんがいたんで」 「いや、そうじゃなくて……」 「救護室の担当表見たら今日さんが待機ですし、探してたんですけど、いたんで」 「いたんで、じゃないってば!」 もう一度言う。私は今、目の前の人物と一番顔を合わせたくない。昨日のたったあれだけの出来事で私は変になってしまった。たかだか高校生のやったことだ、と割り切ればいいものを、多分恋愛経験の少なさがそのスキルを私には与えてくれなかった。お陰で変に意識してしまう。落ち着くために買ったレモンティーもまるで無駄になってしまった。それでも冷めてしまえば美味しくないので、烏丸くんから顔を逸らして一気に半分飲み干す。私の隣からも、ペットボトルの蓋を開ける小気味良い音がした。 こんなこと、むきになるようなことじゃない。一晩自分に言い聞かせたことだが、高校生からすれば二十歳そこそこの女というのは珍しくて、ちょっと興味と好奇心が湧いているだけだ。私が特別な訳ではなくて、あの年齢詐称合コンに誘われていたのが私じゃない二十歳過ぎの女だったとしても、同じことを烏丸くんはしただろう。そういう年頃なのだ、思春期と言うのは。私だって高校生の頃は大人の男性に憧れたのだから、それと同じ。けれどそれは結局恋だのなんだのではなくて、単に自分にはない“大人”というものを持った人間に憧れを抱いていただけ。 そう、つまりおよそ誰もが通る道であり、烏丸くんが悪いわけではなく上手くあしらうことすらできない私が悪いのだ。 「さん、怒ってますか」 「……馬鹿な自分にね」 「さん」 「なに」 「こっち向いて下さい」 「無理」 「なんで」 「なんでも」 どんな子どものやり取りだ。思いながら、溜め息をついた。視界の端では烏丸くんがペットボトルの水を飲んでいるのが見える。 多分、彼は一学年に一人はいた所謂“イケメン”というやつだ。私が高校生の時にももちろんいた。本人とは面識がなくても、同じクラスじゃなくても有名で、“王子”と密かに呼ばれていた人物。烏丸くんとはタイプは違うけれど、これだけいい顔立ちをしていたら女子は放っておかないんだろうなあ、と思う。多分、寄って来る女子なんて山ほどいて選びたい放題に違いない。その中にはまたいるものなのだ、学年でも可愛いと評判の女子が。そういう流れというか、高校特有の空気と言うのはいつの時代も変わらないものなのだと思う。 すると、横目で烏丸くんを見ていた私は、同じく横目で私を見た烏丸くんと視線がぶつかった。気まずくて一瞬でまた目を逸らす。 「さん」 「だから、なに」 「さんって呼んでいいすか」 「……好きにすればいいよ」 大好きなレモンティーを飲んでいるはずなのに、全然落ち着けない。落ち着こうとしたはずなのに、烏丸くんが現れた途端に落ち着けなくなってしまった。 やっぱり、こんな年齢で恋愛慣れしていないのは駄目なのかも知れない。気まぐれとか、からかいとか、そんなものに本気になってしまう。きっと慣れていたら「じゃあ私も京介くんって呼ぶねー」くらいの軽いノリで返せたかも知れないのに。本気になるだけ無駄だ、のめり込めばのめり込むほど後で痛い目を見るのは自分の方。どう考えたって高校生と社会人での恋愛なんて成立しないのだから、こうして思わせぶりな態度を取って恋愛慣れしていない私で遊んでいるだけ。それとも、香澄ちゃんに近付きたいだけか。それなら、まだずっと理解できた。 気持ちがどんどん沈んで行く。別に、確実な言葉も何も言われた訳ではないのに、勝手に落ち込んで行く。だから、嫌なのだ。 「さん、俺って子どもですか」 「そりゃ、未成年だもの」 「未成年じゃ話になりませんか」 「……あのね、私は確かに医療部門所属で精神保健の単位も取っているし、ボーダーでの任務にあたってメンタル面の相談には乗るけど、それ以外の話なら、」 「俺がしたいのはそれ以外の話です」 「……勤務中なんだけど」 「じゃあ勤務外で会って下さい、俺と」 彼は、自分の言っていることが分かっているのだろうか。よく知りもしない大人相手にそんなことは言ってはいけない。特に、私のようにそんな子どもの誘い文句に上手く切り返しできないような相手に。だって、真に受けてしまうのだ。頭では十分過ぎるほど理解しているのに。どうせすぐに私に興味なんてなくなってしまう。“やっぱり同年代が良い”と思う時が来るのだ、それも思ったより早く。 自分の年齢を考えてみる。もう引き返せない年齢だ。多分、今好きな人なんてできたら私の方が手離せなくなってしまう。後がない、なんて考えたことはない、恋なんてしなくてもいいとさえ思う。けれどもし、自分でも思いもよらない所で罠に引っ掛かってしまったとしたら、もうどうしようもないではないか。きっと、私はしつこい。もし私に飽きられてしまっても、私が諦めがつかない。ここまで恋愛にブランクのある女が誰かに執着した時どうなるか、たった十六歳の彼は知らないのだ。 「ごめん、私は会いたくない」 私の曲は、大抵Gマイナー。フラットの音階が私の声質によく合う。そして、Gマイナーの中で展開される恋の曲は、全て別れ話だ。大切な人がいて、特別な人がいて、大切にされていた、特別だった―――それら全てが過去になって行く話。けれど、どれもこれもフィクション。もし恋愛というものをするならCメジャーがいい。最初から最後まで大切にされて、たったひとりの特別な人になる。恋愛なんてしなくていいと言いながら、いつまでも夢見るのはそんな少女漫画のような展開。その展開を手に入れるには、相手は烏丸くんではいけない。 そうですか、と言うと、烏丸くんはその場を立ち去って行く。その背中を見て自分にまた言い聞かせる。暗示のようにこれでいい、これで正しかったのだと。 ≪≪  ≫≫
≫≫(2016/03/31) |