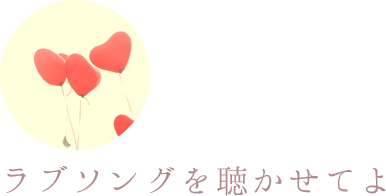 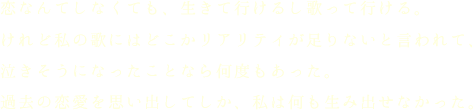 あの年齢詐称合コンの翌日、私を誘ったちゃんから電話がかかって来た。どうやら相当具合が悪そうに見えたらしく、心配してくれていたらしい。実際はかなり乗り気ではなかったため、自然と無口になっていただけなのだが。それに加え、私が烏丸くんと二人で帰ったことも気になっていたようだ。しかし事の顛末をを話せば彼女からも裏返った声が返ってきた。 「高校一年!?」 「そう。だから残念だけどちゃんが期待するようなことはないからね」 「えぇー……」 もごもごとは言うものの、烏丸くんのことを聞いて来た声色には少し好奇心がまざっていた。二人でファミレスに行ったことまで言えばまた何か根掘り葉掘り聞かれそうなので敢えて言わないが、飲み会や合コンよりは気が楽だったとだけは思った。随分歳も離れているのに結構容赦ないことを言うし、今の高校生ってああも物怖じしないものなのだろうか。もし私が悪い大人だったら彼をお持ち帰りだってしていたかも知れないのに。高校生を子ども扱いするつもりはないけれど、一応私は大人で彼は未成年だ。 「私はともかく、あの合コンの後で何か出会いはあったの?」 「いえ。そもそも私、彼氏いますし」 「……だよね」 最近の子って本当に恐ろしい。いや、私の時代にもそんなものだったのだろうか。学生時代に合コンなんて行ったことないけれど、彼氏がいながらそういう場に行くって、彼氏は一体どういう心境なのだろうか。ちゃんとは付き合いも長くなって来たし、大体の性格は分かっているつもりだけれど、未だに理解できない部分は多少ある。これがジェネレーションギャップというやつか。 「ちゃんこそ烏丸くんと何かあれば面白いのに」 「面白いとかじゃなくてね、年齢差考えてみてよ」 「そんなのきっと関係ないですよ!」 「簡単に言うなあ」 二十代も半ばになってみれば、衝動だけで恋なんてできるものではない。段々傷付くことは恐くなるし、当たって砕けてしまえばそれこそ元通りになんてならなくなる可能性がある。未成年と大人、社会人と高校生。どう考えたってお互いに不釣り合いだ。昨日だって、向こうはきっとちょっと歳の離れた姉と話している気持ちだっただろうし、私もそう。多分、弟がいればこんな感じなんだろうな、という程度にしか思えない。 時々、自分でもつまらない人間だなと思う。お酒に酔って倒れたことも記憶を飛ばしたこともないし、終電を逃したことだってない。引き止められたって必ず飲み会では終電の一、二本前に帰っている。もちろん男遊びだってしたことないし、そもそも男遊びできるような目立つ容姿でもない。それでも、それなりに片思いというやつは結構して来た。付き合った相手がいないこともない。けれど、漫画やドラマのような熱い恋愛なんて私は経験したことがなかった。だから、私の書く音楽は全部空想の中にあるのだ。 「だってちゃん、烏丸くんから連絡先聞かれてるよ」 「はい?」 「そう、それが今日の本題だったんだけど、アドレス教えていい?」 「悪くは、ないけど…なにそれ…」 「高校生ってほら、大人の女性に憧れるんじゃない?ちゃんのこと大学生じゃないって見抜いたくらいだし」 「あ、あはは…」 まさか職場が同じだなんて言えない。まあ確かに、高校生なんてちょっと色を使えば簡単に落ちるものなのかも知れない。ただ、断じて私はそういうことはしていない。ファミレスで話したことだって、お互いの仕事のことと、彼の学校のことくらいだ。私と烏丸くんでは所属部門も違うから話を聞くのは面白かったけれど、色恋の話なんて一つも出て来なかった。 「まあでも、恋に発展しなくてもちゃんのお客さんになってくれるかも」 「恋になるよりそっちの方が嬉しいわ、切実に」 「うっ…私も今月がんばろ…既にノルマが危ない…」 アマチュアの音楽活動だってただではない。ハコが儲からない今の時代、出演者に課せられるチケットノルマは厳しい。それでも、どこでも大分緩和はされたようだが、ノルマクリアできなかった分のチケット代は自分で支払わないといけないし、ノーノルマのハコでも流石に集客ゼロが続けば店長に尻は叩かれる。私は今でこそ安定して一定数呼べるようにはなったけれど、ワンマンなりツーマンなりをするとして、なかなかソールドアウトはできない。ソールドにできたのは昨年のレコ発一回だけだったか。彼女も同じようなもので、歳の差と使う楽器の違いこそあれど、同時期に活動を始めた仲間としては応援したい所ではある。 「次いつ?私しばらく予定空いてるし」 「来週の金曜なんだけど、ノルマまであと二枚なの…」 「二枚買うよ、取り置きしといて。誰かつれてくね」 「ちゃん…!ぜひ烏丸くんと」 「行きません」 そんな会話をしたのが丁度一週間前。なぜか私は、通い慣れたハコの前に烏丸くんと二人で立っていた。 結局ちゃんからチケットを買ったものの私も誰も捕まえられず、そんな時にタイミングよく連絡が来たのが烏丸くんだった。「ちゃんの連絡先を聞いて来た」から約一週間、もう忘れられたものかと思っていたが、彼は彼で忙しかったらしい。医療・救護班より戦闘員の方が忙しいのは、一応ボーダー所属の身としては分かっているつもりだ。 そういうわけで、背に腹は代えられぬ、と思い切って烏丸くんをちゃんの出るライブに誘ってみれば、「いいですよ」と軽く言われてしまった。高校生相手に営業してどうするんだ、と罪悪感が胸を刺す。しかも途中、うつらうつらしている所もあったので申し訳ない気分にもなった。バイトも掛け持ちしていると言うし、疲れていたかも知れない。今度またお詫びにファミレスにでも誘おうと思った。 本当は最後までいたかったのだが、全組見ていると時間は二十二時近くになってしまう。流石に烏丸くんをそんな時間まで連れ回す訳にはいかないので、ちゃんのステージが終わってから、軽く声をかけてお店からは出て来た。 「なんか、ごめんね」 「別にいいすよ。さん喜んでましたね」 「良い子でしょ。良い曲も書くし、売れないのが不思議」 「さんもやってるんですよね、歌」 「えっ、あー……まあ、ちょこっと…かな……」 「さんもギターですか」 「いや、私は…鍵盤楽器……」 私に振られるとは思っていなくて、ついはぐらかすような返事になる。隠すつもりもないが、なんせ職場関係の人間に知られることは何となく気恥かしい。 いや、というか私が音楽をやっていると言うこと自体、私からは烏丸くんには言ってなかったはずだ。 「林藤支部長と迅さんが音楽やってるって言ってました」 「え、ちょっと待って何をどこまで言ったの」 「いや、ちょっとそれは……」 「ねえちょっと!私の目を見て言って!?」 玉狛の林藤支部長と言えば何度か話したことはある。迅くんも黒トリガー使いとして有名で、ふらっと本部に来ては医療部にもふらっと顔を出して行くことがあったから顔見知りではある。挨拶をした程度だけれど、迅くんよりも年上なことは確かなので、大学生のふりをしていたなんて知られたらいい笑い物ではないか。ちょっと涙目になりながら腕を掴んで烏丸くんを揺すっていると、逆に私の手を掴まれる。途端に無言になって、じっと私を見下ろして来た。 「なに」 「目、見てるんですけど」 「う、うん、そうだね」 「なんか」 「うん」 「どきどきしますね」 170は超えているであろう身長の彼と、160に満たない身長の私。多分、後ろから見れば誰も彼が高校生だなんて思わない。この暗さじゃ向かいを歩いて来る人からも分からないかも知れない。どれだけ当事者が歳の差を理解していたとしても。 「ど、どきどき……」 「しませんか」 「う、うーん……よく分からない」 「嘘」 言いながら、今度は指を絡めて来る。何の冗談だ、今の高校生って会って二回目の相手にこんなことをするものなのか。その前に冷静になって欲しい、もう一度思い出して欲しい、私と彼の間に一体いくつの年齢の差があるのかと言うことを。 さすがに居た堪れなくなって私の方が目を逸らす。それでも烏丸くんが私をひたすら見つめていると言う視線を感じてしまって、言われた通りなんだかどきどきする気がする。まだ外の風も冷たいのに、なぜか顔だけ熱い気がする。 「さん」 「な、なにかな」 「俺、もっとさんのこと知りたいです」 何の冗談だ。二度目、そう思う。大人をからかうのはよして欲しい。きっと烏丸くんがそう思うのも、滅多に関わることのない二十歳過ぎの女が珍しいだけだ。好奇心に応えてあげられるほどの覚悟なんて、私にはもうない。 高校生は、思っているほど子どもではない。思っているほど何も知らないわけではない。そんなこと、高校生の時代があった私もよく分かっていることだ。彼らは周りが思っている以上に大人で、あらゆることを理解している。けれど、やっぱり未熟な部分はどこまでも未熟だ。高校生が私くらいの歳の女性に憧れの感情を抱くことはあり得る。けれどそれは、きっと恋じゃなくてどこまで行ってもただの憧れ。 「……やめといた方が良いよ」 それだけ言って、私はそっと指を解く。急速に熱が冷めて行った気がした。 ≪≪  ≫≫
≫≫(2016/03/24) |