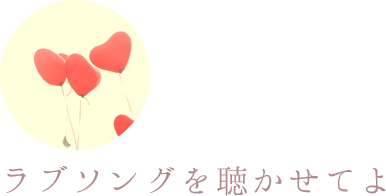 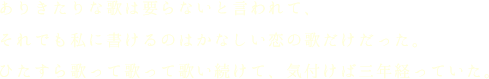 ろくでもない恋愛をした方が、良い曲は書けるのだと言われたことがある。私も多分、そんな曲が書けるくらいの思いはして来ている。けれどお陰で、私はもう何年も恋をしていない。それでも漫画やドラマや他の音楽の影響で恋の歌なんていくらでも書けるし、むしろそればかりになっていた。 この街近辺の音楽界では遅咲きと言われた私も、もう鍵盤を抱えながら歌い始めて三回目の春を迎えようとしている。三年前からそうだが、周りは年下の子たちばかりで、中にはまだ学生をしている子だっている。その中でも私を一番慕ってくれている子から、音楽以外の頼まれごとをされてしまった。 「合コン?」 「どうしても人数が足りなくて、でも頼めるのがちゃんしかいないの!」 パン、と両手を合わせて頭を下げて来る。彼女は音楽系の大学に通っている学生で、合コンなんかに誘われるのも、まあ分かる。可愛らしいし良い子だし、コミュニケーション力も高いとなれば、たとえ合コンに行ったとしてもそれなりに楽しむ子だろう。だが、私は違う。私は大学生ではないし、お酒が飲める訳でもなく、人見知りもすれば男性相手には大学生とはいえ上手くやれる気がしない。なんとか断ろうと、まだ頭を下げている彼女に気付かれないように小さく息を吐いた。 「…ちゃん私の歳知ってるよね?」 「ちゃんなら全然大学生でも通るよ!」 「…………」 そういう問題ではないのだが。確かに、音楽をやっている人は年齢不詳の人間が多い。年下だと思えば年上だったり、その逆があったり、見た目の予想よりずっと上だったりということもよくにある。私がそれに当てはまるのかどうか分からないが、とりあえず見た目はどうであれ、問題は中身だ。今の大学生と会話で渡り合うことなんて私にはできそうにない。普段のお客さんとの会話は共通の音楽の話題や社会人であるということで共感できる部分があるからで、年下相手になれば全くの別問題だ。私がその場で浮くのは目に見えていた。 それでも、よほど彼女は困っているらしく、なかなか引き下がってはくれない。仕事ですか、いや仕事ではないんだけど、じゃあお願いします―――その繰り返しだ。大体、彼女以外の参加者が友人を呼ぶということはできないのか。 「いつも皆が集めてくれるんで、今回は私が、ってことになって……」 「あー……大学生も大変ね……」 「参加費半分私が持ちますから!私も友達少ないんですよー!」 「う……」 痛い所をつかれた。私も彼女も友達が少ないことでこの界隈では有名なのだ。そのため、企画ライブを開催するとなっても演者は大概同じメンツしか集まらず、お世話になっているハコの店長からもそろそろ二人まとめて溜め息をつかれていた。 そんな“友達少ない仲間”の彼女に切実な頼みをされてしまえば、断りにくくなってしまった。私も大概押しに弱い。しかも可愛い大学生の女の子の頼みとなれば。 「参加費は自分でちゃんと出すよ。先月のバースデーライブもゲストに呼んでくれたし、そのお礼ね」 「やった!」 「その代わりこれっきりだから!企画のお誘い以外は今後は受けないから!」 「分かりました!お願いします!」 本当に分かっているのだろうか。まあ、こういう所が大学生の可愛い所でもある。純粋だなあ、と思いながら「ありがとう!」を繰り返す彼女を見つめた。 私にもこんな時期があっただろうか。正直に言うと、私の合コン経験なんて二、三回ほどしかない。職場だってほとんど飲み会がないから、お酒の席の経験もほとんどない。出ているハコでもいつも頼むのはソフトドリンクかノンアルコールだ。大学生―――二十歳になったばかりともなれば、お酒が解禁されて浮かれてぐいぐい飲んでしまう年代ではないのだろうか。私がそういったことと縁がなかったため、どこまで行っても想像でしかないが。 「それにほら、ちゃんも何か曲作りのヒントになる出会いがあるかも」 「何かって、いくつも年下の男の子と?」 「何があるか分からないって」 「まあ、期待しないでおく」 じゃあ次の土曜日に、とお店のチラシを渡される。彼女と別れてからそれに目を通して見ると、最近できたばかりのお店らしい。どうせこういう所に行ってもお酒なんて飲まないから損なだけなんだけどな―――そう思うとまた溜め息が出た。 時計を見ると、そろそろ予約していたスタジオの入り時間だ。憂鬱な気持ちは全部音楽に向く。なんだか今日は、恨みつらみを込めた曲がひとつできそうな気がした。 *** 「あれ、ちゃん随分めかしこんでどうしたの」 職場のロッカールームから出て来ると、出くわした同部署の男にそんなことを言われた。仕事を定時で終わらせて、ロッカールームの中で髪を巻いてみただけなのだが、いつもより違うということは分かったらしい。メイク直しもしたけれど、服だけはどうにも、大学生の子が履くような短いスカートは今や持っていなかった。 「……ちゃんと若作りには見えてますか」 「若づくりって……いつもより洒落てるとは思うけど……ていうかちゃん十分若いじゃん。医療班の平均年齢下げてくれてるのちゃんだし」 私の職場は少し特殊だ。音楽仲間にも本当のことは言わずぼかしてはいるが、ボーダーの医療・救護班の一員である。直接戦闘や防衛任務には関係ないものの、ボーダー所属と言えば一般人から出て来る名前はまず“嵐山”だ。そして会ったことはあるかだの話したことはあるかだのという話が始まる。当然、私は彼とは面識はないが、三門市の有名人なので名前が出ても仕方はないだろう。ボーダーと言えば機密も多い機関なので、あまり突っ込んだ話をされたくないのも職種を明かさない理由の一つだった。ぼんやりと「医療関係です」と言って、守秘義務の四文字を出せば納得されるのだ。間違ったことは言っていない。 「今年もうちの部署は新規採用なしですか?」 「人員不足してないからなあ。というわけでちゃんまだまだ一番下だしがんばってよ」 「まあそこそこがんばります」 「ちゃん仕事以外が忙しいもんね。ああ、今日も音楽?」 「いや今日は……」 「……ああ、ああ!野暮だったごめん!いってらっしゃい!」 あ、多分絶対誤解されたな。あの笑顔は、絶対誤解している。多分、明日出勤したら「デートどうだった?」なんて言われる展開だ。いろいろと面倒なので職場では彼氏がいることにはなっているが、実際そんなものは存在しない。もう何年も恋をしていないと言えば、つまりそういうことだ。学生時代は勉強に追われていたし、働き出してからはこの通りだ。ただ、“忙しい”というのは自分に言い聞かせているだけの単なる言い訳だ。本当はもっと他の所に理由はあって、でもそれを言い出すとますます面倒臭い。二十年以上生きていれば、思い出したくない恋愛沙汰の一つや二つあってもおかしくはないだろう。女の恋は上書き保存とどこかで聞いたけれど、どうもその上書きを私は上手くできなかった。 そもそも合コンなんて誘われもしないけれど、こうして参加した所で期待なんてしていなかった。中には良い出会いをする人もいるのだろうけど、私の周りではあまりそういう話は聞かない。ただまあ、ちゃんも言った通り曲作りのネタになるようなことは、もしかするとあるかも知れない。 何事も経験だ。それが例え、年齢詐称して参加する大学生の合コンだったとしても。…と、ちゃんたちと合流するまでは私も思っていた。 「ちゃん大丈夫?気分悪い?」 「う、うーん、大丈夫だよ」 眩しい、眩し過ぎる。彼女らは大学二回生で、私だけ三回生だという設定にはしたが、たった一年でここまで差が出るはずがない。相手の男の子たちとの話題にもついて行けない。愛想笑いとソフトドリンクを往復していると、口数が少ないことにようやく気付いたちゃんが声をかけて来たのだった。気にしないで、と小声で伝えてまた烏龍茶を一口飲む。すると、「あの」と今度は向かいに座っている男の子が声をかけて来た。名前も聞いたはずだがもう忘れてしまった。覚える気がまずなかったのだ。 「帰りますか?無理しなくていいと思いますけど」 「あー……でも……」 「俺も帰りたいんで」 「……正直ですね」 苦笑いを返す。彼は、何やら上手いこと言いくるめて私と彼は帰宅できることになってしまった。そういえば、彼も最初からあまり会話の中には参加していなかったような気がする。もしや、私と同じく単に数合わせに呼ばれただけなのだろうか。だったら乗り気そうでないのも帰りたがるのも分かる。 外に出ると、お店の中の喧噪が嘘のようだ。やっぱりああいう場は苦手であることも実感した。その場にしゃがみこんで、大きく息を吐き出す。無意識の内に随分気を張っていたらしく、どっと疲労がやって来る。そんな私を見た彼も、同じように隣にしゃがみ込んで「大丈夫ですか?」と聞いて来る。 「大丈夫です、疲れただけなんで……」 「大変ですね、さんも大学生のふりして」 「……え?」 今、何か大変な言葉が聞こえたような。冷や汗が背中を伝う感覚がした。大学生のふり、と確かに聞こえた、彼は言った。やっぱり大学生のふりなんて私には無理があったのだろうか。顔を引き攣らせながら彼の方を見るが、特に表情もなく何を考えているのか汲み取ることができない。 「さんですよね」 「な、んで……」 まさか、どこかで会ったことがあるだろうか。あるとしたら、どこかのハコでだろうか。いや、でも私は結構人の顔を覚えるのが早い。こんな若いお客さんが来ていれば間違いなく覚えている。今、私の知り合いの大学生といえば音楽仲間かお客さんしかいない。プライベートで付き合いのある大学生だってちゃんくらいだ。だとしたら、他に考えられる可能性は一つしかない。 「医療部門のさんで間違ってないですか」 「……間違って、ないです」 「俺、一年くらい前まで本部にいたんですけど」 「ご、ごめん、知らないです…」 「だと思いました」 まさかとは思ったが、ボーダー関係者だった。こっちで知られる方がよほど困る。しかも、私は知らないのに彼は私を知っていると来た。いい大人が大学生のふりをしている所を、見られてしまった。見られた以上に、大学生のふりをしながら同じ空間で過ごしてしまった。彼のことを知らないことについては、別段気を悪くした様子ではないが、もしこれが言いふらされたりでもしたらいい笑い物だ。もし先輩たちの耳に入ったりしたら、「、あの日洒落こんでいたと思ったら大学生のふりを…」なんて可哀相なものを見るような視線を送られるに違いない。そう思うと血の気が引いた。 一年前まで、ということは今はどこかの支部にでもいるのだろう。だが、この世には携帯電話というものがある。いくらでも仲間に情報を送ることができるのだ。「本部のに大学の合コンで会った」と誰かにメールでもするかも知れない。 「あ、あの、このことは…」 「言いませんよ。俺も高校生ですし」 「………はい?」 「さんと同じ数合わせです。バイトの先輩の頼みで」 「あ、そ、そう……」 確かに、大人びてはいるが大学生というには少しまだ足りないような気がした。幼い、とまでは行かないけれども。私は大学三回生のふりをして、彼は大学一回生のふりをしていたらしい。そうすれば彼もお酒を飲まずに済む。お互い年齢詐称ということで、利害は一致した。なんとか言いふらされずに済みそうだ。ほっとして胸を撫で下ろす。すると、彼は立ち上がって私に手を差し出した。 「帰りませんか」 「ひ、ひとりで立てるよ」 「そうですか」 酔ってもいないのに、手を借りるまでもない。立ち上がってスプリングコートの裾をぱんぱんと払う。そういえば、殆ど何も食べていない。お腹空いたな、なんて思いながら今度はお腹を押さえた。飲み会というのはご飯がメインではない。みんなお酒とおしゃべりを楽しんでお腹いっぱいになった気でいるのだ。私はそのどちらも楽しめないからずっと空腹のままなのである。もう今からスーパーで何か買って夕飯を作る気力もない。コンビニで適当に買って帰ろう。腕時計を見ると、二十時半だった。今から電車に乗って最寄りの駅に着く時間を計算する。明日は仕事も休みだということを考えても、やはり自炊する気にはなれない。 多分、本部にいた時から会わなかったのだから、彼ともこれきりだろう。けれど、こういう場合はどうするのだろうか。男とは言え高校生だ、大人として家まで送り届けるべきなのだろうか。まだ補導されるような時間ではないけれど、それでも未成年でこの時間だ。迷いながら、私よりずっと背の高い男子高校生を見上げた。 「お腹空きましたね」 「えっ」 「食べてませんよね、ほとんど」 「食べてないけど…………あー……何か、食べに行く?」 せがまれた訳ではないだろうが、唐突にお腹空いたなんて言われて続いた言葉がそれしかなかった。ちょうど、私もお腹は空いている。幸い、まだファミレスだって開いている時間だ。未成年を連れて行ったって、まだぎりぎり許される時間でもある。そんな私の提案に、彼も「そうですね」と相変わらず起伏のない声で返す。困っている訳でも嫌がっている訳でもなく、それが彼のテンションなのだろう。 「そういや、名前言ってませんでした」 「あー……そういえば」 「玉狛支部の烏丸京介です」 「本部医療部門のです」 「知っています」 「なんか、なんとなく」 「面白いですね、さん」 何も面白いことなんて言った覚えはないのだが。それに烏丸くんも面白いと思っているような顔をしてない。 とりあえず、ファミレスのある方へ足を向ける。ぽつりぽつりと、他愛のないことを話しながら。時々見上げてみるけれど全く目は合わなくて、また私も視線を前に戻す。二人分の足音に合わせて、頭の中では私の好きなCメジャーのコードが流れ始めた。  ≫≫
≫≫(2016/03/24) |