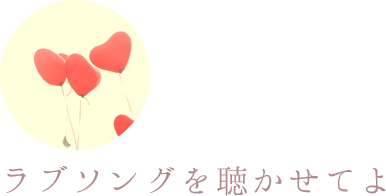 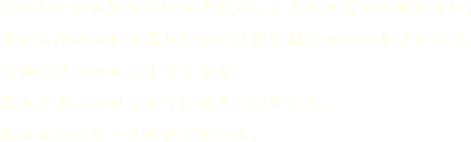 付き合うことになった、ということで良いのだと思う。烏丸くんに好きだと言われて、私もと返した。だから、付き合うことになったと言うことで、合っているのだと思う。けれど、付き合うってそもそも何をするのだろう。今の高校生の恋愛事情なんて私は知らない。 「メールとか、電話とか、会ったりとか…」 「そりゃ、そうなんだけど…」 「ていうか、結局ちゃんと烏丸くん上手く行ったんじゃないですかー!」 専らの相談先はちゃんだった。出会った経緯も事情も知っているのはちゃんだからなのだが、もう一つの理由は、やはり私よりちゃんの方が烏丸くんに年が近いからであった。プライベートでも付き合いのあるちゃんは、こう言う時に年上の私の相談に必ず乗ってくれる。学生だから時間に融通ききますから、とは言ってくれるが、会う度に烏丸くんの話をされてはちゃんもたまったもんじゃないかも知れない。 十代なんて通って来た道のはずなのに、当時どんな風に毎日を過ごしていたかなんてもう思い出せない。だから余計烏丸くんとの付き合い方も分からなかった。頻繁に連絡を取るかと思えばそうでもない。こちらからメールの一つでも送れば返事は来るけれど、やはり忙しいらしく長続きはしない。さっきちゃんが挙げたようなことをするのが“付き合う”ということなら、全く条件をクリアしていないことになる。 「烏丸くんに会いたいとか思わない?」 「…そこまでは」 「何かこう……烏丸くんのことで悩んだり」 「いや、別に…」 満足してしまった、という訳ではないけれど、「こんなものか」と思う自分もいる。会っていないのが原因だろうか。会いさえすれば、またあのどきどきや胸の高鳴る感覚は戻って来るのだろうか。どちらかと言うと、付き合った直後の幸せな気持ちよりも、後悔の一歩手前の気持ちの方が大きかった。私で良かったのだろうか、と。今更だけれど、やっぱり年が離れすぎなんじゃ、と思ってしまう。 「でも、ちゃんが羨ましい…」 「なんで?」 「私より烏丸くんと年近いから」 子どもの我儘のようだ。どうしようもないこと、どうにもならないことに不満を抱く。高校生に戻りたいとまでは言わないから、せめてちゃんと同じ学生になりたいと思う。いや、だからと言って私の学生時代に戻りたい訳ではないが、もし今学生だったら、もうちょっと同じくらいの目線で物事を見ることができたのだろうか。あんなにも拒否する必要もなかったかも知れない。…なんで、一番楽しいであろう時期に溜め息が止まらないのだろうか。 「なんだ」 ぽつりと、ちゃんがこぼす。なんだそんなこと、と。私にとっては結構大ごとなのだが。じとりとちゃんを見れば、違う違う、と慌てて手を振って否定して見せた。 「思ったよりちゃんが烏丸くんを気にしてるってことだから」 「……そうなのかな」 きっと烏丸くんだってそうだよ。そう言われてもなんだか、実感がわかない。何せこの歳の差だ。全てはそこにあった。せめてお互い二十歳を超えていたらさほど気にするようなことではなかったのかも知れないが、やはり社会人と高校生や大学生の壁は高い。だからって、私も好きだと言った言葉や気持ちを今更なかったことにはできない。そもそも嘘でもない。嫉妬をしてしまった時点で、それはもう認めざるを得ない感情となるのだ。 会わなくても平気、なんて嘘だ。好きだと言われたあの日から、余計烏丸くんのことが気になって仕方ないし、知りたくて仕方ない。仕事をしていても、家にいても、今だって、一体烏丸くんは今何をしているのだろうと考えてやまない。特に、学校で女の子とよくしゃべるのだろうか、なんてものは私の一番の気になる所だった。 烏丸くんも同じなのだろうか。私が今どんな仕事をしているかとか、どんな人たちと仕事をしているのだろうとか、どんなことを考えてどんな風に日々を過ごしているかとか、そんなことを気にしてくれているのだろうか。私のことを知りたいと、思ってくれているだろうか。一人では解決しないことばかり、自問自答の繰り返しだ。 「私」 「うん」 「烏丸くんに、会いたいのかも」 好きだと言われてから一週間と少し、本部では一度も姿を見ていない彼の手のひらを思い出した。 *** 日曜の朝、当直が終わって本部から出れば憎らしいほどの快晴だった。当直とはいえ防衛任務のように常に気を張っていなければならない訳ではないので、医療班の当直は楽な方だ。何かあった時のために待機はしているものの、殆どその“何か”がある訳ではなく、昼間の勤務者が残した仕事や研究をしているのが常だった。それでも、普段寝ている時間に起きていると言うのはやはり眠い。本部の関係者用出入り口を抜けてあくびをひとつした所で、「さん」と声をかけられる。 「かっ…!?」 らすまくん、と言おうとして声が続かない。大きなあくびをしている所を見られてしまったらしく、彼は肩を震わせている。 「なんでこんな所に」 「当直だったって聞いたんで」 「いや、聞いたんで、じゃなくてね」 「迎えに来ました」 「…頼んでないけど」 ああ、もう。数秒前に時間を巻き戻して自分を殴ってやりたい。なんでこんな可愛くない言葉しか出て来ないのだろうか。あれだけちゃんには相談して、本音を吐きだしたりしたのに、いざ本人を目の前にすると思ってもないことばかり口からするすると出て来てしまう。 いい大人が何をやっているのだろう。気まずくて、烏丸くんから顔を逸らす。「嬉しい」とか「会いたかった」とまでは言えなくても、せめて「ありがとう」と素直に言えばいいだけなのに。初めて会った日の夜の方が、もっと普通に話せていた気がする。夜のファミレスで他愛もないことを喋ったのは楽しかった。あんな風に話す余裕もないなんて。 「頼まれてなくても来ますよ」 「…………」 「俺がさんに会いたいだけです」 「…………」 また、朝からそんな恥ずかしいことをさらりと言う。いや、普通なのか。そんな風にまっすぐに言葉にしてくれる人にこれまで出会って来なかったせいか、烏丸くんのストレートさには振り回されてばかりだ。慣れない心臓は早鐘を打ち、私に目眩すら起こさせる。 せっかくの日曜にわざわざこんな所に来るなんてとか、なんで私が当直だって知ってんのよとか、最早悪態すら出て来ない。言いたいことは色々あるはずなのに、烏丸くんは私を振り回すだけでなく言葉まで奪ってしまうらしい。簡単に言い表せないこの気持ちを、どう表現すればいいのだろう。私の持っているあらゆる言葉を以てしても、伝わらない気がした。多分、稚拙な言葉しか出て来なくて、それが歯痒くてまた思ってもない言葉を吐く。その繰り返しだ。 「思ったよりちゃんが烏丸くんを気にしてる」というかの相談相手の言葉が頭をよぎる。気にしている、どころではない。明確なきっかけなんてどこだったかなんて自分でも分からないけれど、私はきっと、自分が思っているよりずっと烏丸くんを意識しているし好きなのだ。好きと言ってしまえば簡単なのに、唇に乗せてしまえばそれまでな気がして、余りに軽い気がしてぐっと言葉を呑み込む。じゃあ、私が伝えたい言葉は一体何なのだろう。 「…あのね」 「はい」 「……なんでもない、ごめん」 ぎこちない愛想笑いを乗せて、「せっかくだしどっか行く?」と声をかける。言いかけた言葉をなかったことにしたくて。けれど、それを許さないのが烏丸くんだ。通り過ぎようとした私の右手を、すかさず捕える。 「言って下さい、なんでも」 「え?」 「さんの話、なんでも聞きたいです」 「なんでも、って……」 「俺の知らないさんのこと、もっと知りたいんです」 そんなの、私だって同じだ。知らないことはたくさんある。ボーダーのパソコンを使えば出て来るパーソナルデータなんかではなくて、もっとプライベートな、個人的なこと。それを、こんな風に言葉にできたなら。彼のように、もっと言葉にすることができたなら、もう少しくらい可愛げが出るのだろうか。こんなにも素直じゃないのに、きっと私を知れば知るほど面倒臭い人間だと分かってしまう。だからって、嫌われたくないからと言って取り繕うことも上手くできない。 もっと、嬉しいものだと思っていた。誰かに好きだと言われることも、思われることも、幸せなことのはずだった。それが、なんで今回に限ってこんなにも苦しいのか。これまで私のして来た恋は、こんなのじゃなかった。 「烏丸くん」 「はい」 「眠い」 「じゃ、寝ましょう」 「うん」 掴まれていた手を繋ぎ直す。ただの我儘を言っただけなのに、斜め下から見える彼の顔は、心なしか嬉しそうに見えた。 ≪≪  ≫≫
≫≫(2016/04/27) |