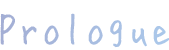  と初めて喋ったのは入学式の時だった。自分の席についていると「すみません」と女子の声が後ろからかかる。振り返ると無表情、というか険しい表情のやつがいた。体格は小柄、流石に入学式とあって制服のカッターシャツは一番上まできっちりとめられていて、スカートも膝丈。 「そこ、私の席だと思うんですけど」 「そうだっけか…っと、座席表。お前名前は?」 「おま……」 「、……や、お前俺の一個前」 それは失礼しました。口だけはそう言って悪びれもしていない。カタン、と静かに音を立てて自分の席についた。背筋はぴんと伸びていて、教室のドアが開く度に後ろ髪がさらさらと揺れる。 自分から話しかけるなんて、しかも入学初日にそんなことする柄でもないのに、気になって背中をボールペンでつついてみた。 「うひゃぁっ!?」 「お、いいリアクション」 「何ですか!」 「中学どこ?」 「後でどうせ自己紹介の時間があるでしょう」 「早かれ遅かれ聞くことになるんだったら今聞いてもいいだろ?」 「……どこにあるの、って聞かれるくらい田舎の学校ですよ」 捻くれた答えに笑うと更にむっとしてみせた。そういうあなたはどこ出身ですか―――そう返して来るに「東京外出身のやつに言っても知らないとこ」と言ってやった。もっと噛みついて来るかと思ったものの、そうですか、の一言で終わらせられてしまった。そしてまた前を向く。 相当田舎ということは、もしかしてスポーツ推薦か何かで入って来たのだろうか。青道を目当てに遠い田舎からやって来ると言うことは、それなりに何か目的があるのだろう。しかしまあ、今聞いた所で答えてくれそうな気配はない。あんまり押しても嫌がられそうなタイプだ。結局、それ以上は何も追及しなかった。 そしての言った通り入学式が終わってからの自己紹介に、俺は驚いた。 「、他県出身です。バドミントン部に入るために入学して来ました」 なんだそりゃ。教室が静まり返った。なぜなら、青道はバドミントン部はぱっとしない部活だからだ。私学で運動部に力を入れているとなれば、まあバドミントン部は大概ある。そんな中、なぜバドミントンが目当てでこの学校に来たのだか。正直、椅子からずり落ちたくなった。けれど周りのクラスメートの視線など気にする様子もなく、再び着席する。 ああ、これ友達いないタイプだな。なんとなく、自分と同じにおいがした。 「さん、さん」 「…なんですか」 「いや、敬語はいーって。仲良くしようぜ」 「は?」 「せっかく席前後だし」 「私、人間関係の構築下手くそですよ」 「はっはっはっ、仲間だな」 これが、俺との始まりだ。 (2014/06/07)  → →
|