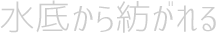|
に俺を待っていたと言われた瞬間、言おうと思っていた言葉が全て消えた。いつもは同じトーンながらも尽きない会話も、その日ばかりは何も話すことができなかった。まさかからそんなことを言われるとは思っておらず、が待っていたこと自体が予想外だったのだ。静かに俺の後ろをついて来るも何も言わず、落ち込んでいるようにも見えた。 それから土日を挟んで月曜日。二日ぶりにと顔を合わせることに初めて緊張した。声をかけても以前と同じように返事をくれるだろうか、目を逸らさないでいてくれるだろうか、様々な不安が頭を駆け巡る。そう思うと、教室に入るのが憂鬱になって来た。かなり重い足取りで教室に向かっていると、教室の前で一人、立ち止まっているを見付けた。なんでこんな所で、と思っても、俺も教室には入らないといけない。 「」 「あ…烏丸くん、おはよう」 「…おはよう」 「入らないのか?」 「入るよ、今から」 そう言って笑い、見え透いた嘘をつく。本当は俺と同じように教室に入るのを躊躇っていた癖に。 なぜは隠そうとするのだろうか。今のような些細なことから、もっと大きな彼女自身のことについて。本当に嫌がるなら踏み込まないが、多分は違う。本音は違う所にあるはずだ。拒絶だって、好きで拒絶したのではない、そういう癖がにはついてしまっているのだろう。その凄まじい記憶力のせいでこれまで気味悪がられて来たが、自分が傷つかないために張った防衛線。それは本当にを思ってくれている人間をも篩いにかけてしまっているのではないか。 何でもなかったかのように、教室のドアに手をかけて中に入る。その細い背中が、俺と同じように緊張しているように見えた。 「烏丸くん」 席についてから、俺の方を見ることもなくが俺を呼ぶ。まだ授業の始まる前、教室が賑やかだったせいで、呼ばれたか呼ばれていないか分からないほど、それは小さな声だった。 「この前、迷惑だった?」 「金曜のこと?」 「うん」 「そんなことないけど」 「…それなら、いいんだけど」 俯くの睫毛が震える。机の上に置かれた両手はぎゅっと握られている。不安そうな横顔はこちらを向くことはない。 そんなことを、この土日に考えていたのだろうか。顔を合わせづらいと、教室の前で立ち止まっていたのだろうか。そんなことはが気にすることではない。確かに驚きはしたが、自分を待っていてくれたのがでよかったという気持ちもあった。いや、が待っていてくれてよかったのだ。 金曜日は疲れていた。緊急招集がかかり授業を抜けて、本部で後処理をして、終わってみればもう授業も終わっている時刻。職員室に顔を出して、机に放置したままの教科書を回収しに行くだけだった。そこにがいてくれて、それまで感じていた疲労が消えて行くような気がしたのだ。の顔を見て、ようやく戻って来たのだと思えた。安堵を覚えた。迷惑だなんて一ミリも思っていない。ただ、俺も言葉足らずだったとは思うが。 「はもっと、やりたいようにやればいい」 「…………」 「少なくとも俺にそこまで気を遣う必要はない」 「…………」 「は俺にどうして欲しい?」 それでも、はこちらを見ようとはしない。俺が言葉足らずだったとしても、はでその言葉を信じられないに違いない。だから全てを伝えることはしなかったが、ひたすら言い続けることでが信じられると言うのなら、何回でも言う。何か言いたそうにする癖に、いつも本当の言葉を呑み込んで、違う言葉を吐き出す。その呑み込まれて消えるはずだった言葉を、俺は聞きたい。そこにしかの本当はないのだ。 「………し、い」 「え?」 「そばに、いてほしい」 確かに、そう言った。そう言って、は自分の口を塞いでいた。小さく震えて、嗚咽を漏らす。きっと昨日今日生まれた言葉ではないのだろう。ずっと誰かに言いたくて我慢して来た本心がそこにある気がした。 こんな状態では授業を受けるのは無理だろう。適当なクラスメートにの体調不良を伝えて二人で教室を出た。腕を引っ張れば抵抗もしない。保健室ではない所へ向かっていても、は俺を止めなかった。ただ、しゃくり上げる声はまだ止まらない。適当な空き教室を見付けて、二人で潜り込む。泣きじゃくるの顔は既に真っ赤になっていて、まるで泣き方を覚えたばかりの子どものようだ。 そばにいてほしい―――それは、最初は誰に宛てた言葉だったのだろうか。肩を震わせるをそっと抱き寄せながら、そんなことを思った。  ⇒
⇒(2016/01/27) |