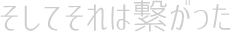|
しまった、と呟いた声は、本当に小さなものだったはずなのに、気付かれてしまった。殆ど話したことのない隣の席のさんだ。うちのクラスは学期ごとにしか席替えをしない方針らしく、入学以来今までずっとさんとは隣り同士だが、挨拶さえしない時もある。それほど、俺とさんは名前を知っている程度の同級生だった。そんな関係が少し変わったのは、その呟きのせいだった。どうしたの、と一応聞いて来た。 「教科書忘れた」 「次の?古文?」 「ああ」 「貸してあげる」 「え?」 すると、さんは簡単に俺に古文の教科書を差し出した。いや、自分の教科書はどうするんだ、と思うのは誰もが同じだろう。教科書を二冊持っているとは考えにくい。これからサボる気か、と思ったけれど、さんは授業も学校も休んだことがない。 差し出されたそれを受け取りかねていると、促すようにもう一度「はい」と言う。 「私、もう一冊持ってるから」 「いや嘘だろ」 「頭の中に。予習して来たから大丈夫」 適当な教科書広げておくし、と続ける。言っている事の意味がよく分からない。そうこうしている内に、古文の先生がチャイムと同時に教室に入って来る。そこまで言うのなら、と取り敢えず受け取ってみる。教科書をぱらぱらとめくってみると、確かに随分先まで予習はしてあるようで、書き込み量も多い。 そうだ、さんと言えば成績は学年でも上位だった。これだけ努力をして掴んでいる学年上位か、と納得する。けれど、頭の中に、とはさすがに意味が分からない。読んで全てまるまる頭の中に入るような能力があるのならともかく。 「じゃあ、62ページ読んで」 「はい」 待て、教科書はここだぞ。ピンポイントで62ページなんて当てられて大丈夫なのか―――そんな心配をよそに、さんは62ページをまるごとソラで読んで見せた。教科書が手元にないことは先生も気付いていない。だから意地悪で当てた訳ではないのだろうが、それにしても一体何がどうなっているんだ。 授業が終わって教科書を返す時も、さんは何でもない風だった。 「本当に頭の中に教科書があるんだな」 「ね、言ったでしょ」 「暗記力がすごいってことは分かった」 「そんないいものじゃないよ」 古文の教科書をしまいながら、さんは小さく笑った。窓際の席のさんは、いつも眩しそうに目を細めていたけれど、ちゃんと表情が動いたのは初めて見た。物静かで、いつも一人でいるさん。昼休みも、他の休み時間もあまり席から動かず、放課後もすぐに帰ってしまう。いや、部活に入っているのかも知れないが、そこまでは知らない。有体に言えば、このクラスには友達がいないようだった。 けれど、こうして話していると人見知りではなさそうだし、人と話すのが苦手でもなさそうだ。話を振ればちゃんと答えが返って来る。 「さん」 「さんなんていいよ、同い年なんだから」 「」 「うん」 「教科書、助かった」 「あはは、今更?」 その瞬間だったと思う。陽の光の眩しさのせいじゃない、普通に笑ったの顔を見て、何かが胸の中にすとんと落ちて来た。まだその落下物の名前を俺は知らない。  ⇒
⇒(2016/01/15) |