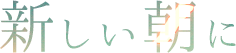|
連休を使って、私は久し振りに宮城に帰って来ていた。大学生の時もなんだかんだ東京にいることが多くてたまにしか帰らなかったけれど、就職してからは余計足が遠のいていた。あっちには、思い出が多く残り過ぎている。どこへ行っても何を見ても影山くんを思い出してしまって辛かった。自分の故郷を見るのが辛くなる日が来るなんて思わなかった。だから宮城に帰っても家からほぼ出ない。地元の友達から会おうと誘われても、返事をする時はいつも暗い気持だった。東京には影山くんもいるはずなのに、そこには二人の思い出なんて一つもないから気持ちはずっと楽なのだ。 「ちゃん!久し振りだね!」 「お久しぶりです。…その節はご心配おかけしました」 「元気になったならいいよ!」 宮城には、まず仁花先輩に会いに来ていた。菅原さんとの関係に一番悩んでいた頃、仁花先輩には一度メールで相談したことがある。思い出すと恥ずかしい、かなり長いメールだった。今思えばあの時、既に私の気持ちは菅原さんに傾き始めていたのだ。そうでなければ悩むことなんてなかった。影山くんとの間で板挟みにもならなかった。仁花先輩に「菅原先輩が気になっているんじゃないの?」と言われなければ、今もまだ私は悩み続けていたかも知れない。 時間が惜しいからと、ゆっくり話すために仁花先輩の車で適当なファミレスに向かった。車内でもあれからのことを大まかに話した。ちゃんと自分とも菅原さんとも向き合って出した結論も。それを聞いた仁花先輩は「やっぱり…」と呟いた。 「どう考えても菅原先輩はビジネスライクな交際できる人じゃないよ」 「そうなんですか?」 「それを言われた時、もう菅原先輩はちゃんを好きだったんじゃないかなあ」 「…そこまでは、聞いてないんですけど」 「聞いてないの!?」 身を乗り出して叫ぶ仁花先輩。そういえば、菅原さんに初めて抱かれた日も、それ以降も、特に改めてそう言った話をしていない。これまで通り、会える日に会って、連絡を取れる日に取る。仕事終わりに夕飯を一緒に食べたり、菅原さんの部屋に泊まったりする回数は増えた気がするけれど。菅原さんも、気持ちを確認するようなことは一切しなかった。すると、「言わなかったからもだもだしてたんじゃん!」と頭を抱える仁花先輩。確かに、そのせいで仁花先輩も巻き込んでしまっていた。 「見捨てられたらどうしよう、て思った時点で好きだったのかも知れませんね」 「そうだと思うよ。好きでもない相手にそんなこと思わないってば」 「私、馬鹿でした」 ファミレスの駐車場に着いて、仁花先輩は車を停める。キーを抜いたのを見て、私もシートベルトを外した。 しがみついていた思い出は、とうの昔に遠くにあった。いくら綺麗な思い出でも、もう私の手の届かない所に行ってしまっていたのだ。それでも、二度と取り戻せないと分かっていても、それを追いかけて走り続けていた。息が切れても、何度転んでも、泣いても泣いても。ぼろぼろになった私を止めてくれたのが菅原さんだった。もう自分から傷付きに行く必要はないと言ってくれたのが菅原さんだったのだ。 いつしか菅原さんを影山くんと比べることもなくなっていたし、何かの拍子に影山くんを思い出すことも殆どなくなっていた。代わりに、気がつけば思い浮かべてしまうのは菅原さんのことで、久し振りに抱く感覚に舞い上がっている自分もいる。また初恋のように。 「だからって、思い出を全部埋め立てちゃう必要はないんだからね」 「え?」 「影山くんと別れた時のことは辛かったけれど、そういうのも全部覚えておくんだよ」 「そういうものですか?」 「思い出を思い出として残しておくことを、菅原先輩は非難はしないと思う」 「…はい」 塗り替えようとしていたから余計辛かったのだろうか。忘れようとしたから時間がかかったのだろうか。どうせ忘れられないし、捨てられるはずもないものなのに。どうやったって切り離すことなんてできないのだ。あの頃を土台にして今の私があるのだから。多分、そういうことを仁花先輩も言っているのだと思う。 「東京に戻ったら、菅原さんに会いに行きます」 「うん、それがいいよ」 宮城に帰って来るのは、ずっと辛かった。影山くんと出会ったのも別れたのもここだったから。けれど、ここにいたのは影山くんだけではない。菅原さんもここで生まれて育ったのだ。 今度は菅原さんとここに来よう。菅原さんの高校生の頃の話や、部活のこと、どの道を通って登下校していたのかを聞きたい。もっと菅原さんの話を聞きたい、菅原さんのことを知りたい。それはまた、別の思い出として私の心の中に残って行くはずだから。  ≫≫
≫≫(2016/01/29) |