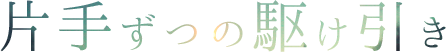|
何もない一晩をさんと過ごしてから一週間、俺たちは少し気まずくお茶をしていた。俺が清水にさんの連絡先を聞いたとほぼ同じタイミングで、彼女も谷地さんに俺の連絡先を聞いていたらしい。かくして、今日会うことになった訳だが、会った瞬間から気まずさばかりが募っていた。「こんにちは…」「どうも…」それ以降なかなか会話が続かず、待ち合わせた駅の改札前からも動けず。喧噪に呑み込まれる沈黙の中、先に口を開いたのは彼女だった。とりあえずお茶でも、と。 会って特別何か話したかった訳ではない。いや、話したいことならたくさんあるはずだが、ずけずけと聞いて良いことではないことは分かっている。それくらいのデリカシーは弁えているつもりだ。それはさんも同じらしく、適当に入ったカフェで注文をすると、また沈黙が訪れてしまった。 あれから大丈夫だったのか、真昼とは言え酷い二日酔いでまっすぐ帰れたのか、―――気持ちは落ち着いたのか。落ち着いていないことなど容易に想像できるが。 水の注がれたコップを持ったり置いたり、口をつけたり置いたりを互いに繰り返す。やがて、沈黙を破ったのはやはりさんの方だった。 「す…菅原さんって、結構近くに住んでたんですね」 「あ、ああ…二駅先だっけ」 「就職で、こっちへ?それとも、進学で?」 「就職かな。さん、職場は」 「………ミツハシスポーツ…」 「……そっか」 思いもよらない回答に、そうとしか返せなかった。話を聞くと彼女は広報や宣伝に関わっているらしいが、どこまでも影山の背中を追って生きているのだと改めて気付く。彼女の出身大学だけ聞けば、あまり就職に困らなかっただろうに。 そこでようやく注文したコーヒーが運ばれて来た。彼女の前には紅茶と小さなシフォンケーキが置かれる。 「…菅原さんはどこで働いてらっしゃるんですか?」 「アオイデザインって知ってる?」 「デザイナーをされているんですか?」 「いや、俺はただの事務職だけど」 「でも倍率高いですよね、あそこ」 「よく知ってるね」 「同期の子が受けて落ちましたから」 そう言ってようやく彼女は少し笑う。よかった、普通に会話できている。意識しなければ簡単ではないか。 彼女もようやく紅茶に口をつけ、ケーキにフォークを刺した。その甘い香りはこちらにまで漂って来るが、俺がコーヒーを口にするとその苦さで消えてしまった。 その後も他愛のない会話を繰り返した。仕事はどうかとか、怖い先輩がいるだとか、後輩に手を焼いているだとか。ただ、全て仕事の話ばかりで彼女のプライベートがまるで見えて来ない。今日会うのだって、二つ返事だった。休日は大体暇しているんです、とメールには書かれていたが、それでは埋められるものも埋められないのではないか。何かで紛らわせるものも紛らわせないのではないか。 けれど意外にも―――いや、今日の流れからすれば自然な事だろうか。オフの話題を振ったのはさんの方だった。 「でも、いいんですか?」 「何が?」 「私と二人で会ったりして、彼女に叱られません?」 「あはは、彼女なんていないよ」 「へえ、意外…」 「いたらあの夜だってさん放置して帰ってるし」 「それも…そっか……」 みるみる内に小さくなって行ったシフォンケーキは、とうとう最後のひと欠片が彼女の口の中に吸い込まれて行った。綺麗になったお皿の上には、ケーキの欠片は少しも残っていない。それをぼんやりと眺めながら、俺も残り少なくなったコーヒーを含む。 なぜか申し訳なさそうに視線をテーブルに落とすさん。彼女の手の中で紅茶が揺れた。知っている、この表情は“後悔”だ。そういう話題を出したことを彼女は後悔している。そこから広がる話なんて、俺たちの間にはないのだから。 けれど、そんなさんとは逆に俺はもっと、と思っていた。もっとプライベートな話をして欲しいと。同級生でも直接的な先輩後輩でもあるまいし、仕事の近況報告なんてするために彼女とこうしてここにいる訳ではないのだ。彼女にそんな、あの夜のような辛い顔をさせたいわけでもない。 「さんこそモテないの?」 「私なんて、宮城から出て来たただの田舎娘ですし…」 「それを言ったら俺も同じだけどね」 「すみませ、そういう訳じゃ…!」 「あのさ、俺と付き合う気ない?」 それを言いたかった。彼女が戸惑うことも、困惑することも、躊躇うことも、全て分かった上で。けれど、もういいじゃないか、と思う。確かに影山とのことは大きな事件だっただろうし、手離せないのも分かる。けれど、もう思い出にしてもいいじゃないか、と。そうして前に進んで、ちゃんと笑えるようになればいいじゃないか、と。彼女は一体何にどこまで、どうやって縛られているのだろう。どんな理由があって、新しい恋をしようと思えないのだろう。 そんなもの、言葉にできないことも分かっている。できないから泣くしかなかったのだ。それでも、いつまでも涙を零し続けていては、すぐ傍にある幸せにすら気付かずに通り過ぎてしまう。どこかでその涙を一旦引っ込めないといけないのだ。 カップを持つ手に力のこもる彼女を見て、俺は言葉を続けた。 「ビジネスライクな付き合いでいいんだ。やたら飲み会の類に引っ張られるんだけど、断る理由が苦しくなって来てさ。彼女でもいるって言えば楽に断れるだろ」 「それって、つまり合コンじゃ…」 「…まあ、そうだけど」 「モテますね、菅原さん」 あ、かわしたな―――微笑む彼女を見てそう直感した。 「その中から適当に見繕おうとは思わないんですか?」 「ああいうのに来る女なんてみんな本気だろ」 「私なら、丁度いいと」 「…有体に言えばね」 その瞬間、彼女の肩から力が抜ける。あまりにも分かりやす過ぎて、バレない程度に苦笑いしてしまった。あれだけ無防備を晒しておいて、一途という一言では表せない恋をしておいて、かわし方と断り方だけはまるでプロだ。それは、こういう場面を彼女が何度も経験していることの表れに違いなかった。 転がしているのか、転がされているのか。会話の主導権を互いに握ろうとしているのがじわじわと分かって、柔らかくなりかけた空気がまた張りつめて行くようだった。 弱っている彼女につけ入る隙なんて、上手くすればいくらでもある。これまで彼女にアプローチして来た奴らはそこを見極めて上手く使えなかっただけで。これだけ影山を引き摺っているさんには、優しくすればするだけ逆効果だ。弱みに付け込もうとしているのが見え見えである。だから、今は優しい言葉は要らない。彼女もそれを欲してはいない。自分から弱音を吐き切って、泣き切って、本当の言葉を欲するまで。 「…まあ、私もお局様がうるさいですし…」 「じゃあ、交渉成立ってことで」 「まるで営業ですね」 「言っただろ、ビジネスライクだって」 そう言って笑いかければ、彼女もようやくカップから手を離して「そうですね」と苦笑いした。互いのカップの中身はいつの間にか空っぽ。俺は伝票を持って立ち上がると、彼女も慌てて鞄を持って立ち上がる。財布を取り出そうとするさんをやんわりと制して会計を済ませた。 店を出る頃には、どちらからということもなく手を繋いでいた。これでよかったんだよな、と自分に言い聞かせながら、俺たちは歩いた。  ≫≫
≫≫(2015/12/04) |