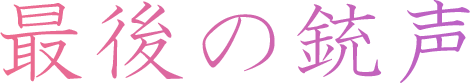
|
人身売買が当たり前のように行われている町に、私は住んでいた。家を襲われ、人身売買の商人に誘拐されるのも珍しい話ではない。自分にその危険がないだなんて思ったことはない。けれどいざそのような目に遭ってみると、あまりにも悲惨だった。 そこで買われるのを待っている間に、私は20歳を過ぎたけれど、目の前で13歳の子どもが買われていくのを見た。ここまで来てしまうと諦めるしかない。まるで牢屋のような檻のある地下室から地上に出られるのは、どこの誰かも分からない奴に“お買い上げ”されるその時だけだ。それなら死んだ方がましだと思いながらも、死を選ぶことすら私たちには許されない。淡々と、ただ淡々と毎日を震えて過ごす。 ここに連れて来られるまでに私は激しく抵抗したため、体中に痣ができるほど殴る蹴るを繰り返された。そして気付けば、左耳は聴力を失っていた。更には声も完全に出なくなり、益々反感を買ったらしく暴力は激しさを増して行った。その為、もう半年ほど売れ残っている。だが、未だにこの地下室で同じ境遇の少女たちと共に自分が買われるのを待っている。このままここにいることも、どこかへ売られることも同じ地獄だ。ここのリーダーが客を連れて石の階段を降りて来る足音は、地獄へのカウントダウンなのである。 「今なら誰の予約も入ってませんし、“どれでもお好きなもの”をどうぞ」 「……そうか」 その日、品のない笑みの主と共に降りて来たのは、意外にも若い男だった。大体、買いに来るのは豪商など金を持て余した親父ばかりだ。その男の身分こそ分からないが、若いがきちんとした身なりであり、なぜこのような場所へ足を踏み入れたのか謎である。彼くらいなら結婚したばかりか、これからする頃ではないだろうか。私は視力も片方が打撃を受けており、しっかりとその男の顔を判別することはできない。目を細めてドアの付近にいる男を見たその時、彼と目が合う。そして彼は口を開いた。 「おい、あの―――……」 ぼそぼそと話すその内容は、片方の耳では聞き取ることができない。私の話でもしているのだろうか、それとも目が合ったのは気のせいで、左隣の少女、サリーを見たのだろうか。サリーはまだほんの13歳で、二週間前にここへ連れて来られたばかりだ。声の出ない私とは、暗いながらも地面で筆談をかわしていた。サリーも私と同じように家を襲われたらしい。このような街でなければ未来があったかも知れない少女。非力な女子どもは力のある者に逆らうことはできず、ただじっと黙って耐えるだけ。悔しいが現実なのだ。事実、私にはなんの力もない。客が来る度にがたがたと震えて怯えながら私の腕を掴む少女一人、私は守ることはできないのだ。サリーは今もまた恐怖に青くなっている。 しかし、檻の鍵を開けると共に呼ばれたのはサリーではなく私だった。 「、お前だ」 「や…やだ……行かないで…」 「おい早くせんか!!」 背後から怒号が飛ぶ。私は服の裾を掴むサリーの手をやんわりと外すと、頭を撫でて微笑んだ。ごめんね、と唇だけ動かすと、サリーの目から大粒の涙が溢れて地下室の冷たい地面に落ちる。ぎゅっと彼女の痩せた手を握り、もう一度唇を動かす。残酷ではあるが私がサリーに伝えられるのはこの一言だけだ。 ―――生きるのよ。 そして私は牢屋の狭い入口を出る。若い男は私を上から下まで眺めると顔を歪めて見せた。けれど、最早どのような視線を向けられようと何も感じることはない。私は誰かに支配される運命なのだと受け入れるだけ。きっと、抗えば抗うだけ傷は増え、生きにくくなるだけなのだ。 男はその場で現金を渡すと、「行くぞ」と言って地下室の階段を昇りはじめる。後ろからはまだサリーの泣き声と、私の名を叫ぶ声が聞こえていた。 |
 →
→(2013/06/16)