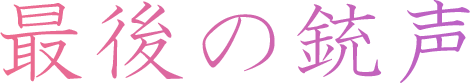
繋いだ手から、熱
|
兵舎―――兵団の敷地の外に、私とリヴァイが借りている家がある。住宅街の一角、ほんの小さな一軒家だ。リヴァイは非番の前夜にこの家に戻って来る。私がこの家に戻って来る回数はそれよりも多いが、兵舎で過ごすにしろリヴァイと居られる時間はごく限られたものであるため、その少ない回数に不満はない。 だが、寂しくないかと言われればそれは別の話だ。私も兵団の医務室職員。リヴァイと仕事で話す機会がなくはないが、そうではない。プライベートな時間を過ごしたいと思うのは恋人として当然の事だろう。 今日もまた、借家で一人寂しく夕食に口をつけていた。私が借家で過ごすのはかなりランダムだ。仕事が遅く終わってもここに帰って来る時は帰って来るし、早く終わっても兵舎で過ごす事もある。つまりはその時の気分だ。 けれど一つだけ理由を挙げるとすれば、リヴァイの空気を感じたい時にここに帰って来る、というのはある。兵舎にある私の部屋は個室で、私以外の空気はまるでない。けれどこの借家には例えば食器が二つずつあるし、タオルの数も多い。ベッドだって一人用の小さなものではない。そのベッドに潜り込めば、例え一人でもリヴァイに包まれているような安心感が得られる。だから、ベッドに入るまでの我慢なのだ。 (なんか変態くさいかしら…) 食器を片付けながら頭を掠めた一つのワード。自分で恥ずかしくなりながら、さっと食器の水を切った。 ふとテーブルを振り返って、その先にリヴァイがいてくれたら、と思う。明日は非番ではないし、今日も会議やら何やらかなり業務が多忙だと聞いた。我儘は言えない。彼には大切な使命があり、多くのものを背負っている。それはもう、私なんかでは想像ができないほど。それを誰より理解しなければならないのは私であり、支えるのも私でなければならない。分からないからこそできる事もあると、常々自分に言い聞かせているではないか。 けれど湧き上がるこの寂しさを埋める事は、やはり彼にしかできないのだ。 * 色々と考え過ぎてしまい、昨晩は眠れなかった。まだ会議中かしら、それとも書類仕事をしているのかしら、もうちゃんと眠れたのかしら―――私の心配は耐える事はない。そんな自分が寝不足では人の事を言えた立場ではないのだが。 そういう訳で、兵団に出勤するのがいつもよりも随分早かった。まだ上の兵士たちは出てきておらず、しかし食堂からは若い兵士たちの元気な声がこんな早くから聞こえている。私はそれを聞きながら医務室の鍵を開けた。しかし鍵が回らない。もしや誰かが侵入しているのか。医務室の中には、金庫の中に劇薬を保管もしている。それを盗難されたとなれば一大事だ。 私は、護身用にと渡されている小さなナイフを取り出し、ドアノブに手をかける。できるだけそっと、音を立てないように扉を開ける。が、首だけ入れて中を見渡して驚いた。私のデスクの上にリヴァイが突っ伏しているのだ。 「どういう事…」 ぽかんとしながら、彼に近付く。制服から着替えもしないまま、深い眠りに落ちている。起こすべきか否か。彼の出勤しなければならない時間まではまだ猶予があるが、ぎりぎりまで寝かせるには身支度やら朝食やらの時間が足りない。 きっと昨夜も遅くまで仕事をしていたのだろう。しかしなぜまたこんな所で休んでいるのか。調査兵団本部から兵舎まではさほど距離もないはずなのに。こんな体勢で、こんな硬い木製の机の上で身体が休まるはずがない。それでも眠り続けるリヴァイを観て、思わず呆れてしまった。 いつだって借家ではリヴァイの方が目を覚ますのが先で、私の方が先に起きた事はない。だから、彼の寝顔を見られるのは非常に珍しい。このままずっと見つめていたくもなる。けれど、起こさなければ。勤務開始時間を越えてしまえば私がこの人に怒られる羽目になる。 「リヴァイ、ねえリヴァイってば」 「…なんだ…」 「なんでこんな所で寝ているのよ」 「うるせぇな…」 どうやら頗る機嫌が悪いようだ。会議が延長したのだろうか、それとも随分と揉めたのか。眉間の皺がいつもに増して深く、そして目付きも悪い。やや充血しているようだ。 別に、この部屋を使う事は構わない。贔屓かも知れないが、気の知れた友人やこうして恋人が多忙の中で、ここで休息がとれると言うのならば文句は言いたくない。けれど驚いたのは机に突っ伏して寝ていた事だ。ここは医務室。リヴァイの部屋ほど良いベッドではないが、簡易ベッドならいくつかここに置かれている。そこで休めばいいものを、無理な体勢では身体のあちこちが痛むだろう。何より、十分に疲れが取れない。 「ほら起きて、朝礼もあるでしょう」 「起きるから耳元でごちゃごちゃ言うんじゃねえよ」 自分はよく耳元でごちゃごちゃ言う癖に。そんな言葉を呑み込んで、ようやく顔を上げたリヴァイから離れる。彼は椅子から立ち上がり大きく腕を伸ばすと、頭をがしがしと掻いてからようやく私を見た。やはりその顔からは全く疲れが取れていない。近しい人間なら疲労だと分かるだろうが、新兵などが見たら近付く事もできない形相だ。 私は棚から真新しいタオルを出すと、医務室のすぐ外にある井戸から水を汲み、冷水にタオルを浸す。再び医務室に入り、それをリヴァイに渡した。 「目が覚めるでしょ」 「悪い」 「でもなんでこんな机で、きゃっ」 急に思い切り手を引かれたため、体勢を崩した私はリヴァイの胸に倒れ込む。彼の右手と、私の左手は繋がったまま。さすが、私一人くらいは余裕で支えられるようで、彼はよろめきもしない。転倒するかと思った私の心臓は早鐘を打っており、言葉を発する事もできない。 しかしそれ以上に驚いたのは、彼が私の髪に顔をうずめ、頭、前髪、額、頬と次々に唇を落として行った事だ。最後に、繋がった私の左手に音も立てずに口接ける。そうして私の顔を覗き込むように見られ、思わぬ彼からの愛情表現に羞恥でいっぱいになった。顔に熱が集まるのが自分でも分かり、思わず彼から目を背ける。未だ離されない手はどんどん温度が上がって行き、じわりと汗をかくほどだ。 「あ、の…」 「早く慣れろよ」 そう言ってくしゃりと私の前髪を撫でると、踵を鳴らして機嫌良さそうに医務室を出て行く。 なんだったのだ、今のは。まだ赤い顔のままで閉じられた扉を見つめる。へなへなとその場へへたり込み、頭の中で先程の光景をリプレイする。手を引かれた、あちこちに口接けられた、そしてあの眼。私の心の内を全て見透かすような鋭い眼。一瞬、何もかもを持って行かれるかと思った。意識も、声も、呼吸さえも支配されるかと。 体中が熱い。心臓の喧しさも収まらない。そして何より、最初に引かれた左手が熱を持って止まない。私はもう、どうしようもなく彼を愛してやまないのだと思った。 |

(2014/05/14 進撃夢小説企画「ゆめをみていた」さまへ)
Title by しあわせになくさま