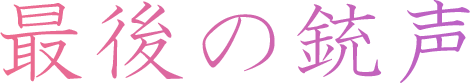
二人の樹海
|
部屋が揺れたのではないかと思うほど、えらく乱暴な音を立てて彼は扉を閉めて出て行った。医務室に残った空気も大変重たいもので、私はため息をついてデスクにもたれた。 喧嘩は、珍しいと思う。普段は些細な言い合いを分かっていてするくらいで、ましてや私から吹っ掛けることはない。彼を怒らせると面倒なことは十分に分かる。それは、これまで不機嫌な彼を宥めて来た私の経験に基づくものだ。けれど私は今日、彼―――リヴァイを怒らせた、故意に。 「何て言うか、っていつも兵長と言葉で命のやり取りしてるよね…」 「…そうかしら」 「見てるこっちがひやっとするわ」 「そんなつもりはないのだけど」 カーテンを開けて、ベッドに座ったまま声をかけて来たのは、体調不良と嘘をつき、ただ寝に来た友人だった。昼休みはいつもがらんとしており、彼女の押しに負ける私はいつも彼女がベッドを占領することを許してしまう。彼女がいたということは、つまりさっきのやり取りを聞かれたということだ。私は構わないが、リヴァイほどの人間なら彼女がいたことも察知しただろうに、他人の前で私とあれだけ下らない口喧嘩をするのも珍しかった。 煽った自覚はある。多分、こんなことを言えばリヴァイは怒るだろうと、私は予測していた。言っておくが私はマゾではない。彼を怒らせたかった訳でも、私が怒られたかった訳でもない。約三年に渡る曖昧な関係を確実なものにしたのはまだ最近だ。それなのにわざわざ、私は亀裂の入るようなことをした。それは、今生きるこの場所が余りにも脆い平和の中にいると分かっていたからだ。 「“私を殺せる?”なんて、もし冗談だとしてもリヴァイ兵長には通じないでしょ」 「意外と冗談言うわよあの人」 「うそ」 表情はあのままだから分かりにくいけれど、と心の中で呟く。 私は仮初の平穏の中で生きている。医務室から一歩外に出れば兵士たちがいて、厳しい訓練に生傷を絶やさない。壁外調査の度に失われる命は数え切れず、誰がいつ消えるとも知れない。百年の平和すらかりそめなのだと思い知らされた巨人の侵入も、私が必ず無事に生きられるという保証をあっけなく握り潰したものだ。 様々な可能性を考えることは容易い。けれど、じゃあ私は今更何が不安なのだろう。 「早く兵長のとこ行って弁解して来なよ。いつ何があるか分からないのはだって分かってるんでしょ」 「……私、死にたいのかな」 「はぁ?幸せ絶頂が馬鹿言わないでよ。エンゲージブルーにでもなってんじゃないの」 婚約した覚えはないのだが。…ともあれ、こんなにも気持ちが不明瞭のままリヴァイの前に立つことは、更に神経を逆撫でることにしかならない。それでも行かないよりはましだろうが、今日はなぜか躊躇われた。 死に場所を選べないのなら、その前にあなたの手で殺して欲しい―――そう彼に告げた私は、何が恐いのだろう。何に怯えているのだろう。 「ねえ、次の壁外調査、もうすぐらしいわよ」 また、眠れない夜が来る。 *** ずきりと、左耳の痛みで目が覚めた。浅い眠りには悪夢が付き纏い、決まって痛みで目が覚める。気持ち悪いと思えば冷や汗をかいていて、額も背中もべたべたしている。どうもこのままでは寝られそうにない。私はカーディガンを羽織り、夜風に当たりに兵舎の外へ出た。丸い月が私を見下ろしており、それはいっそ眩しいほどだ。 ぼんやりと、今日のやり取りを思い出した。 彼は、リヴァイは強い。彼に勝てる人間はこの世にいないと言われている。それは私もよく知っていることで、現に彼ほど軽傷で壁外調査から帰還する人間はいない。だから私もリヴァイの手当なんてこの三年でもさほどしていない。けれどこれからもそうだとは限らない。 たくさんの遺体を見て来た。友人も、よくしてくれた兵士も、可愛がっていた新兵も、いなくなってしまった。物言わぬ体になって戻って来た彼らを見ることに慣れることはなく、無事を祈る私を嘲笑うかのように犠牲は止まることを知らない。 (そっか…) 私は恐いのだ。彼が冷たい体になって戻って来るかも知れない可能性を消せないことが。いくら彼が人類最強と言われようと、何があるか分からないのが壁外調査。壁の一歩外は私の想像を遥かに超える壮絶な世界なのだ。だから私は、彼の冷たい体を見るくらいなら彼より先に死にたいと思った。 「違う、私…っ」 「?」 呼ばれた名前に、振り返る。そこには、怪訝そうな顔をしたリヴァイが立っていた。なんで、と思わずこぼせば、後ろの兵舎の窓を指した。 「丸見えだ、馬鹿」 「……ごめん」 「それは何に対する謝罪だ?」 ぎくりとした。今日の昼間のやり取りで私の中は今更、自責の念でいっぱいだ。あんな風に怒らせたい訳じゃなかった。それなのに、仲間の死を見続けて来た彼にとっては地雷に値する言葉なのだと分かっていたはずなのに、私は敢えて言った。馬鹿言うな、と叱ってくれればそれで良かった。それだけで、私の不安も少しは消えるはずだった。 言葉に詰まり、唇を噛む。段々と、この空気の雲行きが怪しくなって来た。リヴァイの表情も険しさを増す。なかなか答えない私に苛立ちを募らせているのだろう。やがて、痺れを切らしたかのように彼の方が口を開いた。 「一人で勝手に迷路に突っ込んで行くな」 「え……」 「どうせまた下らねぇことうじうじ考えてたんだろうが」 「く、下らないって…!」 反論しかけると、彼は私の頭を掴んで押さえつけた。痛い、と抵抗しても彼は一向に力を緩めない。足が地面に食い込むのではないかと言うほど力をかけられる。頭頂部を押さえる腕に手を伸ばすと、ふっと力が緩められた。しかし相変わらず手は離れておらず、顔を上げることはできない程度に力がかかっている。そんな奇妙な体勢の中、ぽつりと彼は言った。 「下らねぇだろ。、俺にお前が殺せると思っているのか」 その声に色はない。いつも通り、平坦な声だ。動揺も困惑も焦燥もない、いつもと変わらない落ち着いた声。 そう問われて私は初めて、愚かな問いをしたのだと思い知った。いくら私が心臓を預けた相手とはいえ、私を生かしてくれた彼が私を殺すはずがない。彼を疑った自分に後悔する。ごめんなさい、もう一度そう言うと、彼は大袈裟な溜め息をつく。しかし今度はその言葉の意味が伝わったらしい。頭に置いていた手を退けて、代わりに私の頬を撫ぜる。 「聞いて来た内容に怒ったわけじゃねぇ。今更分かりきったことを聞いて来るから怒ったんだ」 「…うん」 その手から伝わる温度は確かで、私の不安を掻き消して行く。それでもこの温度を当たり前だと思ってはいけない。そう思った瞬間から、私は今日みたいな過ちを繰り返してしまうだろう。彼の優しさに甘えて。 思い込んでしまえばそこは迷路だ。泥沼にはまった思考回路から一人で抜け出すことは容易ではない。けれどそれがもし一人ではないのなら。手を引いてくれる誰かがいるのなら、容易くないことはない。頬に触れている彼の手に自分の手を重ねる。この手を信じていれば、きっとどんな深い森の中でも恐くはない。甘えるのではなく信じよう。私たちの歩く道が正しい出口へ辿り着けるように。 目を閉じて、もう二度と一人では迷わないと誓った。 |

(2013/08/05)