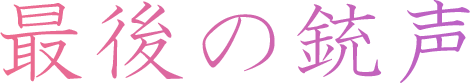
線を引いた向こう側
|
最近、彼が医務室に来る回数が増えた。割としょうもない理由で訪問して来るものだから、本当の怪我人や体調不良者が近付けなくなり、遠回しに「何とかし てくれ」と頼まれてしまった。しかし彼が私の言うことなど聞くはずがなく、今日も「昼休みに俺が何をしようと勝手だろうが」と言って医務室で読書を始めた。ここは図書館ではない。 「医務室には目的があります。健康なあなたが来る場所じゃないでしょう」 「最近疲れてんだ。休ませろ」 「あのねぇ…」 天下の兵長様がまるで駄々をこねる子どもだ。確かに最近は彼でさえ仕事を持ち帰る始末。どうやら報告書やら計画書やら、私には理解できない書類の仕事に 追われているらしい。それは日に日に濃くなる目の下の隈に現れている。それに気付いていながら追い出せる私でもない。彼もそれを知っているのだろう。 私は溜め息をついて「兵長さん」と呼びかけた。本から顔を上げ、まだ何かあるのかとでも言いたげな目で私を睨む。 「追い出さないからベッドで寝てちょうだい」 「…………」 黙った理由はただ一つ。医務室のベッドが共用であるからだ。あからさまに嫌そうな顔をされた。 「寝不足なのは分かってます。そんな体調で訓練に出て怪我しても困るわ」 仕方なく、真新しいブランケットをベッドの上に敷き、枕の上には洗濯したばかりのタオルを敷いた。せめてもの優しさだ。ここまでしてしまう辺り、私は随分彼に弱いのだと思う。 それを見た彼は、観念したように本を閉じ、どかりとベッドに乗った。安っぽいベッドの安っぽい錆びた金属のスプリング音がした。彼の自室のベッドはさぞ かし良いものなのだろう、険しい顔をする彼。しかしこれで私のミッションは終了だ。カーテンを閉めればまさか中に上司がいるとも思うまい、怪我人が正しく 医務室を利用することができる。私はデスクに向かって今月の医務室利用票を整理しながら待った。だが、今日に限って誰も来ない。いや、誰も来ないのは良い ことなのだが。 すると、カーテンの向こうから声が飛んで来る。 「…」 「なんですか」 「今月は行ったのか、墓参り」 「昨日行きました」 私は毎月、両親のお墓参りに行っている。月命日に休みとは限らないため、日はばらばらであるが。それは彼も知っていることで、これまで特に言及されたことはない。いきなり何だろうか。 「…お前の両親、どんな人だったんだ」 「へ…?」 思いも寄らぬ質問に、ついペンを持つ手が止まる。カーテンの方を見てみるが閉ざされたままで、彼がどんな顔で聞いて来たのか窺い知ることはできない。まさかあんな大きな寝言もないだろう。 「父は、無愛想で医者にしてはつっけんどんで…けど冷たい訳ではなく、責任感の強い人でした。きっと、あなたと似てる」 「はぁ?」 「うん、似てる似てる。あっ、母はそんな父をいつも広い心で受け止める優しい人だったわ」 「話逸らすのも上手くなったじゃねぇか…」 ちくちくと言葉に棘が見えるようだ。けれど構わず私は続ける。 「優しいだけではできない仕事だったから。時には人の死を看取らなければならない仕事だったから、優しいだけでは潰れてしまう」 彼は黙った。眠ってしまったのだろうか。静かにベッドに近付いてカーテンを少しだけ開けると、小さな寝息と共に彼の胸郭は規則正しく動いていた。私は苦笑いしてカーテンを戻す。 「あなたの仕事もそうでしょう?」 信頼している仲間が当たり前のようにいなくなる現場で、優しさだけでは正気が保てなくなる。厳格さも冷酷さも、時には優しさに先行した方がいい時がある。優しさを一番奥へ追いやり、自分を保たなければならない時があるのだ。 安全な仕事ばかりしている私には、それはもう憶測や想像の域を出ることはない。だが、両親の手伝いをしていた頃を思い出すと、私にもまた一種の冷たさが戻って来る気がした。時には、諦めなければならない判断を下す冷たさが。どれだけ熱心に診ても、もう手の尽くしようがない患者。もうどれほども生きられないということを知らされず、未告知のまま生きる患者。家族に看取られながら亡くなる患者。それら全てを背負うには、優しさだけでは潰れてしまうのだ。 医療のことならまだしも、私に兵団のことなら分からないから、それを一緒に背負ってあげることができない。だからこうして、休む場所を空けておくことが、私にできる精一杯なのだ。この人が潰れてしまわないように。 「おやすみなさい」 呟いて、私はカーテンに背を向けた。 |

(2013/06/28)