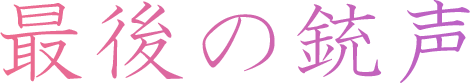
|
医務室が暇な時、何もすることなく部屋で過ごす時、考えるのはいつも彼のことだった。今どうしているんだろうか、どんな訓練をしているのだろうか、そろそろ会議が終わる頃だろうか―――呆れるほど、私は彼のことばかりを考えていた。それなのに、それを知られてしまえば彼に見放されるんじゃないかと怖くて、何でもないふりをした。何事もないということは、それだけ綱渡りなのだと初めて知った。何事もないように振る舞うことは、何かあるからに決まっている。知られないようにしようとすればするほど、嘘をつくのが下手な私は自分の首を絞めて行く。そうして、今回のようなことになったのだ。 「友達…っていうのかな?元気だった?」 「…はい」 「じゃあさ、次は彼に会いに行ってあげてよ。最高に不機嫌で誰も手をつけられないから」 苦笑いをして頷いて返す。まだ涙で濡れる目元を袖口で拭って、私は元来た道を走って戻った。 機嫌が悪い、と言われた日には、大概いつもより帰りが遅くなるのが彼だ。それならまだ執務室にでもいるはず。そこにいなければ兵舎に行けば良いだけの話だ。 大した体力もない癖に、私は息を切らしながら走った。私服で中をうろつくことは流石に気が引いたため、医務室に寄って白衣を羽織って執務室に向かう。かなり遠回りをしたため、執務室の前に着く頃には足も心臓も、あちこちが痛い。壁に手をついて息を整えようとするも、慣れないことをしたためなかなか呼吸は元に戻らない。汗も大量にかいているし、髪も乱れ放題乱れている。こんな格好で入ったら怒られるだろうか―――躊躇っていると、先にドアが開かれた。出て来たのは調査兵団の団員だ。医務室から殆ど出ない私がなぜここにいる、と奇妙な顔をされたが、「あの、リヴァイ兵長は…」と聞くと「…中に」と答えてくれた。この際、相手の愛想など気にしない。緊張しながら改めてノックをして、そっとドアを開ける。すると、ハンジさんに聞いた通り、至極不機嫌な彼がそこにはいた。 「なんだ」 「謝りたくて」 「………」 「あと、お礼を言いたくて…サリーのこと…」 サリーの名前を出すと、隠すこともせず彼は舌打ちをした。大方、自分の名前は出さないようにとサリーに念を押していたのだろう。 機嫌は悪いが、出て行けと言われない辺り追い出そうと言う気はないらしい。机に片肘をついたまま、「…で」と低い声で先を促した。 この人の何にもなれないのだと気付いて、消えてしまいたくなったことは数え切れないほどある。けれどその度にこの人に救われたこともまた事実で、消える勇気さえ掻き消されてしまった。ごくたまに、私を離すまいとする素振りも見られたけれど、かと思えば彼の方が簡単に遠くへ飛んで行きそうで、見え隠れする彼の真意に歯痒い思いもした。彼の視線を振り払って行方を晦ますことができたなら、知らずに済んだ苦しさもある。待つことしかできない日々は不安の繰り返しで、何の力も持たない私には祈ることしかできない。彼が壁外調査に行っている間は、とこで息をしているかすら分からないのだから。 「一つだけ我儘を言うから、それが聞けないことだったらここから追い出して欲しい」 既に大きな責任と期待を背負う彼に、私のようなちっぽけな存在だとしても、これ以上何かを背負わせてはいけない。そう自分に言い聞かせながら、心のもう半分ではいつも願っていた。私をちゃんと彼のものにして欲しいと。 「私の心臓を、あなたに預けさせて欲しい」 彼の心臓はもう私の手の届かない所へ捧げられたものだから、欲しいだなんて言わない。だからその代わりに、私の心臓を預かって欲しい。私の心はここにある、心臓と共にある。だから私の心も、私の命も、彼に託したい。決して、この人の預かり知れぬ所で私の息が絶えることがないよう、心臓ごと縛りつけて欲しい。それが無理なら、私はもうここを出て行く覚悟だ。ここまで私の中にたくさんの住処を作っておいて、それでもこの人のものになれないなんて、これ以上は無理だ。 私は心臓の拍動する辺りでぎゅっと両手を握り締め、彼を見つめる。私の言葉を聞いても、彼は眉ひとつ動かさない。部屋の薄暗さは私の気持ちを映しているかのようで、翳って行く夕陽のお陰で部屋はどんどん暗くなって行く。沈黙を裂いたのは、彼が立ち上がった音だった。無言のまま、表情も変えないまま私に近付く。思わず身構えると、私の前でぴたりと止まった。 「とんだ規律違反だな」 「…私は、兵士じゃないから」 「それでも調査兵団で働く人間だろ」 「じゃあ、私の上にいるあなたに捧げるわ」 「馬鹿が、それじゃ同じだろうが」 調査兵団のトップは団長だ―――そう言うと共に、私の左腕をぐいっと引き、バランスを崩すとそのまま私を抱き締めた。初めてのゼロ距離に、私は目を見開いたまま固まる。彼の肩越しに見える部屋の風景も全て固まり、私の心臓だけが動き続けているような錯覚に陥った。 「リヴァイ…?」 「その言葉に嘘はねえな、」 「え…」 「嘘はねえかって聞いてんだ。はいかいいえで答えろ」 「はっはい!」 返事をすると、更に腕に力が込められる。私も恐る恐る手を伸ばし、彼の背中にしがみつく。「他の誰にも心臓を渡すな」、そう右耳の傍で言われた瞬間、私の両目から涙が溢れた。物騒な言葉とは正反対に、頭を撫でる手は至極優しい。言葉の銃口を左胸に突き立てられながら、私の心は穏やかだった。ようやく掴まえてもらえた、曖昧な関係に終止符を打てた、そんな幸せがじわじわと胸の中に広がる。長い三年間だったと。関係を聞かれも曖昧な言葉で濁し、苦笑いで追求させない。それの、どれだけ苦しかったことか。ばっさりと切り捨てられる訳でもなく、堂々と認められる訳でもない。私は彼の何なのだろうと、彼に訊ねる代わりに何度も何度も自分に問うた。けれどそれももう終わりだ。 「あなただけの私になります」 「後悔しねえだろうな」 「しないわ、きっと」 あの地下室に捕らわれた時、私は一度死んだ。そんな私に二度目をくれたのがこの人だった。だから私は全てを捧げられる。何を言われても従おうと思った。白か黒かはっきりしないなら要らない、私の我儘が彼にとって聞けない内容なら出て行く覚悟もあった。けれど拒まれることがなかったから、私はもう一回この人の隣で生きて行ける。 宛がわれた銃口は、まっすぐに私の心臓を狙う。生きるも死ぬもこの人次第で、私の全てを掴んでいるのはこの人。最後にゆっくりと、彼は引き金を引いた。 「お前の心臓は俺の物だ」 銃声が右耳を掠めて行った。 |
←
 →
→(2013/06/22)