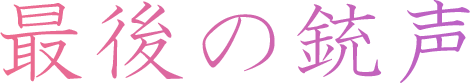
|
この人を好きなのだと自覚したのは、一体いつだっただろうか。言葉は乱暴だし、無愛想だし、最初はかなり怯えていたと思う。調査兵団の人間だと聞いても、身分で女を買う買わないは決まっている訳ではない。貴族があそこで少女を買って行く所だって見ているのだ。 あの地下室を出て連れて来られたのはこの借家で、今度はここに閉じ込められてしまうのかと絶望を抱いた。けれど彼は閉じ込めるどころか触れようともせず、私とある程度距離をとって会話をした。私の声が出ないことを聞いていたらしく、首を振るか頷くかで答えられるような質問ばかりされたが、決して苛立つような素振りは見せず、そんな日が暫く続いても私を面倒臭がらなかった。あの売人たちですらそろそろ私を疎ましがっていたというのに、次第に彼の印象は“変わった人”になっていた。そうして彼とは何もないまま、久し振りに穏やかに過ごした後に、私の声は急に戻って来た。 私は当時、彼に借家の一切を任されており、今と同じく非番の前日しか戻って来ない。好きに使えと言われていたため、食事も作っていたし、掃除も洗濯もしていた。所謂、売り物とされる以前の生活と殆ど変らないような生活をしていたのだ。そんなある日、包丁の先で指をついた。その瞬間、私の喉から声が出たのだ。 (そうだ、あの時も…) あの時も、私の声を聞いた彼は、耳を澄まさなければ聞こえないような小さな声で言ったのだ。「良かった」と。右耳の鼓膜を震わせた安堵の声と、少し乱暴に頭を撫でた手。武器を握るその手のひらは硬く、けれど優しかったことを覚えている。 今、私の腕を掴む彼の手と、問い掛ける声には躊躇いが見えた。本人は気付いていないだろうが、僅かに震えている。彼の声を聴き逃すまいとして来た結果、私はそんな些細な変化にも気付くようになっていた。だが今はそれどころじゃない。私に求められているのは“回答”だ。「わ…私は…」彼以上に私の声が震える。 答えを間違う訳には行かない、けれど正直に言えるはずがない。 「リヴァイの、好きにしたら…良いと、思う」 私の言葉を聞くと、徐々に手の力は弱まり、彼は私から離れた。舌打ちして背中を向けられ、私はようやく焦る。けれどもう遅かった。 「兵舎に戻る。鍵閉めて寝ろ」 「待って…!」 「俺の好きにすれば良いんだろ」 間違えた。答えを間違えたんだ。だって、他に何を言えば良かったと言うのか。私の望みを訴えたとして、彼の不本意とする所だったらそれこそどうしようもない。それに、さっきの答えには少し期待を込めた。もしかしたら、真意を汲み取ってくれるんじゃないかと、勝手に期待をしたんだ。最初から期待をしなければこんなにも落ち込むことはないのに、自分の馬鹿さ加減に嫌気がさす。 乱暴に閉められた家の扉。その向こうで彼が何を考えているのかなんて分からない。どんな顔でいるのかも分からない。ただ、こんなにも扉を分厚く感じたのは初めてだった。 *** 翌朝、私はいつも通りに出勤した。違うのは、夜通し泣き続けたことで目が腫れているのと寝不足なことくらいだ。腫れぼったい目を擦りながら医務室のドアを開ける。するとそこには既に人がいた。 「おはよう、酷い顔してるね」 「…分かりますか」 「バレバレ」 ハンジさんが、私の椅子に座り、なにやらデスクを物色している。とはいえ、特に見られて困るものを置いてはいないので、わざわざ声をかけることなどしないが。 私と彼の関係を知る人間は限られており、その一人がハンジさんであるため、まさか彼が何か言ったのかと勘繰る。ここへ来ることが珍しい人間がいれば、誰でもそう思うだろう。けれどあの彼が他人に私との何かを言うはずがない。しかしそれにしてはタイミングが良過ぎる。…私は緊張しながら、何を言われるのかを待った。 「今日、仕事終わってから暇?」 「予定は何もありませんけど…」 「あなたに会わせたい人がいるんだけど、時間貰っていいかな」 「………」 「心配しなくても、にとっては良い知らせだと思うんだけどな」 「分かりました」 それだけ言うと、ハンジさんは医務室を出て行った。 何も聞かれなかったことにほっとしながら、彼のことを聞けば良かったと後悔する。昨日、あの後彼を見たかとか、何か言っていたかとか、気になることは山ほどある。彼のことで気分はこんなにも憂鬱なのに、結局考えてしまうのは彼のことばかり。 あれはきっと、怒っていたのだろう。ただ、あれだけでは何に怒っていたのかが分からない。私が本心を言わなかったことが問題なのか。けれど言ったら言ったで気まずい以上にもう彼の傍にはいられない。なのに、それ以外の答えを言ってもこんなことになってしまった。次に顔を合わせた時、どうすればいいのだろうか。理由も分からないのに謝るなんてことはできず、そんなことをしようものなら益々彼を怒らせるに違いない。 (でも、会いたい…) まさかずっとこのままではないだろうが、じゃあ一体いつが元に戻るタイミングなのか。何もなかったかのように戻れるのだろうか。私は、どこに戻りたいのだろうか。本当は進みたかったはずだ。現状から抜け出して、名前のつけられない関係になんとか終止符を打ちたかった。そうして、ちゃんと彼と向き合いたかったはずだ。時々、私に勘違いをさせるような言動の裏側を知りたかったはずだ。もしかして、と勘繰るのは期待していたから。その期待通りの言葉を、彼に望んでいた。 あなたの気持ちこそを知りたいのだと、そう言えば良かったのかも知れない。そう後悔した所でもう遅い。今更、彼に合わせる顔がない。しかも今日は彼は非番で、偶然出会うなんてことはない。何もかものタイミングが悪かった。 そんなことを延々と考えていると、あっという間に一日が終わってしまった。私の勤務時間が終わると、ハンジさんはすぐに医務室に現れる。私とは逆に随分と機嫌が良く、楽しそうだ。何か研究で新たな発見でもあったのだろうか。生憎、今日は人の話を聞くほど余裕がない。申し訳なく思いながら、私は少し後ろをついて行った。 「すぐそこまで来てもらってるんだけどね。あ、ほらあそこ」 兵団を出て少し歩くと、ハンジさんは前方を指差す。それに従って顔を上げると、こちらに背を向けた女性が一人、立っている。見覚えのない後ろ姿に首を傾げると、「おーい!」とハンジさんはその人物に声をかける。振り向いた彼女を見て、私は息が止まった。 「…!」 3年経っていても忘れるはずがない。そこにいたのは、短い期間だったがあの地下室で一緒に過ごしたサリーだった。3年分成長し、女性らしくなったサリーが笑顔で駆け寄って来る。驚きが喜びを上回り、私は声も出せない。飛び込んで来たサリーを抱きしめ返すも、まだ信じられない。あの、怯えてばかりだったサリーが、地上で笑っている。夢のようだ。 あれから、ずっとサリーのことは気がかりだった。実際、苦しくなどない生活を送っていた私は、彼女に対して後ろめたさもあった。サリーを置いて来てしまったと、何度も悔いた。今頃どこで何をしているだろうか、今もまだ泣いているのだろうか、それ以前に生きているのだろうか―――私を慕ってくれたサリーを忘れた日などない。 「、私ね、今は姉夫婦の所で一緒に暮らしているのよ。ちゃんと仕事もしてる」 「嘘…なんで、サリー…」 「あ、の声初めて聞いたわ!元に戻ったのね!」 「え、ええ…あそこを出て、少ししてから…」 サリーが生きている。二週間だけ、私の妹のような存在だったサリー。あの時のような怯えた目もしておらず、16歳の少女らしい笑顔をしている。彼女もちゃんと生活を取り戻していたのだ。 良かった、と何度も繰り返した。安心すると同時に、涙が止まらなくなる。昨日散々泣いたのに、それでもまだ涙は枯れていないらしい。泣かないで、とハンカチで私の涙を拭うサリーは、あの頃のぼろぼろだった面影などどこにもない。 「あの後…が行ってすぐにあそこは摘発されたの。だから私は売られずに済んだのだけど、が誰に買われ…どこに行ったのかはずっと分からなくて…」 「なら、なぜ今…」 「リヴァイ兵士長よ」 「え…?」 サリーの口から思いもよらぬ名前が飛び出す。昨日、喧嘩別れのようなことをした相手の名前が出て、私は動揺する。私がサリーの話をしたのは、声を取り戻してすぐのたった一度だけだ。しかも、いつも山ほどの仕事に追われていたと言うのに、一体いつの間にサリーを探してなどいたのだろう。彼が私を買ったことは、サリーを見付けた際に聞いたらしい。しかも、サリーの話によると、私を買ったお金は全て彼に返金されているのだという。独断で囮捜査のようなことをして、上からは厳重注意を受けたことも、サリーから初めて聞いた。 優しい人なのね、というサリーの言葉に、驚きで引っ込んだ涙が再び溢れ出す。私はそんなこと、一つも知らなかった。何一つ知らずにこの3年間過ごして来た。職を与えられ、食べるものも住む場所も着るものにも困らず、その上傍にいてくれる人がいた。なんて呑気だったのだろう。いや、それ以上に私は最低なことをしてしまった。 「、私は今幸せよ。辛いことはたくさんあったし、もう生まれた家がないことは悲しいけれど…。ねえ、は幸せ?」 ぎゅっと手を握って、サリーは訊ねて来る。 「私、は…」 あの地下室から連れ出してくれた人。片耳が聞こえず会話中に聞き返しても嫌な顔一つしない人。声が戻るまで待ってくれた人。休みの度に私と過ごしてくれる人。私に選択肢を与えてくれた人。 私は与えられてばかりだ。彼に返せたものなんて一つでもあっただろうか。買った者と買われた者だと自分に言い聞かせ、線を引いたのは私の方だ。けれど実際、私を買うために払ったお金は全て彼に戻っている。情けで私を買ったのなら、それ以上私を傍に置いておく必要なんてない。 もしかして、と思っても良いのだろうか。 「私も、幸せよ。大切な人ができたから」 彼に会いたい。会って謝りたい。そして言いたいことがある。ずっと傍に置いて欲しいのだと、与えられるだけでなく私も返して行きたいのだと。そして何より、あなたのことがずっと好きだったのだと伝えたい。 幸せだと言いながら泣く私に、サリーはただ微笑んでいた。 |
←
 →
→(2013/06/19)