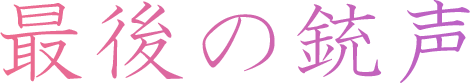
|
彼は、意外と優しい。左耳が聞こえない私には、決して左からは話しかけない。並んで歩く時は必ず私の右側にいてくれる。声を失っていた頃は治療させたり話すことを強要せず、私の声が回復するのを待ってくれた。あの地下室も外の世界もどうせ地獄だと思っていたのに、牢屋から出た私は思いもよらぬ自由を得た。 けれどいざそれを手にすると、どうすれば良いか分からなくなる。解放された両腕は何を掴んで生きて行けば良いのか。自由を得ると共に、恐怖で埋め尽くされていた心全てが空っぽになり、今度は大きな孤独に苛まれる。所有されているはずなのに、酷く、酷く空虚だ。 「おい、手が止まってるぞ」 「あ…うん」 スプーンを持つ手が静止していた。まだ湯気のたっているスープでも、直に冷めてしまうだろう。贅沢のできない生活の中で、それでも私はなかなか食思が湧かずにいた。 彼の非番の前日は、こうして彼の借家で過ごしている。さすがに兵舎で二人で会うことは、それこそ変な噂を撒きかねない。私はさほど厳しい業務でないため、借家から医務室へ通勤することは困難ではない。だからいつも彼の非番に合わせて借家へ帰って来るのだ。彼くらい階級も上がると、割と外出や外泊も自由が利くらしい。 よくこんなことが年単位で続いていると思う。“私はお買い上げされた”という一種の確認業務のような気がしてならないが、元より拒否権などない。私のことはともかく、彼は面倒ではないのだろうか。手を出す訳でもなく、ストレスの発散に拳を振り上げるでもなく、ここへ帰って来るだけ。食事をして、持ち帰った仕事をしたり少し話したりして、シャワーを浴びて寝る。たったそれだけ。自分と彼の年齢を疑いたくなる。 「体調でも悪いのか?」 「そんなことは、ないんだけど…」 「言いたくねぇのかよ」 「言いたくないって言うか、言いづらいっていうか」 「ハッキリしねぇな」 私より先に夕食を食べ終えた彼が、かちゃん、と音を鳴らしてスプーンを置いた。私は生温くなって来たスープを見つめ、そんな私を彼は怪訝そうに見る。 一人じゃないのに、一人でいるような感覚とでも言おうか。最低限の生活をできる職を手に入れたのに、この手の中は空っぽだ。毎日大勢の人に囲まれながら、心の真ん中はぽっかりと穴が空いている。それはきっと目の前の人物のせいで、こんな生活が続く限りは解放されない。これ以上解放されても私は更に行き場をなくすだけだが、もっともっと、分かりやすく占拠して欲しい。所有なんて生温いものじゃなくて、独占して欲しい。 けれど、それもこれも一方通行なのだろうか。私を買ったこと自体が情けをかけただけで、仕方ないから今まで続けているのだろうか。 ごめん、という言うと、彼は少し間をおいて口を開いた。 「…隠し事が増えたな」 「そういうつもりじゃなくて」 「やめるか、そろそろ」 「え……?」 やめるって、何を。この生活をやめるというのか、私を所有することをやめるというのか。 一瞬で頭が真っ白になる。彼は「仕事も落ち着いて来ただろ」だのなんだの言っているが、人より半分の聴力のため、いつもなら一言一句逃すまいとしている彼の声が、何一つ入って来ない。彼の言葉を、私は初めて拒絶している。 「、」 「や…やだっ!!」 勢い余って立ち上がると共に、ガタン、と大きな音を立てて椅子が倒れた。 唇が震え、喉が引き攣る。この世の絶望を見たような、そんな気がした。三年前のように声が出ない訳でもない、何かを言わなければならないのに、言葉と言う言葉が出て来ない。何かを言いかけた彼を遮ってまで叫んだのに、その先に続ける内容など私は持っていないのだ。ただ、弱く頭を横に振った。 「やだ…やだ……っ」 「…んな顔すんな」 「だって、リヴァイ、私、」 「が辛いのがこことの往復だってんならやめるかって言っただけだろ」 「そんなの…!」 そんなこと、冗談でも言わないで―――絞り出した声と共に、テーブルに涙が落ちた。 彼のことで悩めば悩むほど、身動きが取れなくなる。自分がどうすることが最善なのか、そんなもの見出せない。そもそも、私に能動的に動く権利があるかどうかも分からない。それなのに一人前に拒否を叫んだ。 あの頃よりずっと色んな事が出来るようになった。仕事も覚えた、知り合いも増えた、コミュニケーションの取り方も上手くなった、耳はもう戻らないけれど声は戻って来た。それなのに、一つ何かを得る度に彼といつか離れなければならないのではないかという不安に、いつも襲われる。もしも彼から正しく人身売買の通りの扱いを受けていたなら、きっと覚えることのなかった不安だ。尚も私は自由を求めて抗っていたかも知れない。 けれど現実は違う。驚くほどに彼は優しく、私を縛りつけたことなど一度としてない。私を外へ連れ出したのは彼なのに、いつか私は捨てられてしまうのか。私が上手く懐くように接したのは彼の癖に、それに気付かないふりをされてしまうのか。 これ以上泣き顔を見られたくなくてその場を飛び出し、別の部屋へ入る。力いっぱい閉めたが、このドアには鍵がない。簡単に開けられてしまうに決まっているのに、無駄な抵抗と分かりながら私は必死でドアノブを握って向こうから開けられるのを拒んだ。 「お前の気持ちはよく分かったから、ここを開けろ」 「でも…!」 「それ以上拒むんなら無理矢理開けるぞ」 「や……っ」 容易にドアは開いてしまう。少しの動揺も困惑も見えない二つの目が、私を見下ろす。 苦しくて仕方ないのだ。ちゃんとあなたのものにして下さい、なんて言えず、曖昧なままでいることが。よく私の心配をする癖に、自分は心配させてくれない。狡い。もう、この首輪は外れる寸前なのではないだろうか。二度と外れないようにつけ直して欲しいけれど、それを願うことは私に許される権利なのだろうか。 ドアノブから離れた行き場のない手を、彼は急に掴んだ。そしてぐっと引き寄せると、聴力の残っている右耳のすぐ傍で私に問うた。 「どうして欲しいのか言ってみろ」 彼は意外と優しい。けれどそれ故に生まれた不安がある。果たして今与えられた選択肢は、優しさと呼べる類のものなのだろうか。 |
←
 →
→(2013/06/17)