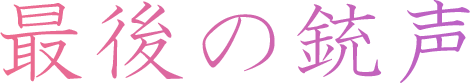
|
かくん、と頭が落ちて目が覚めた。私が人身売買小屋で商品として売られていた頃の夢だ。もう三年ほど前になるが、あの凄惨な光景は今でも鮮明に覚えており、思い出す度に左耳の奥がずきりと痛む。眉間に皺を寄せ、左耳を押さえていると医務室のドアが乱暴に開かれた。 「、いるか」 「ノックをして下さいって何度も言ってるじゃないですか…」 入室して来たのはあの日私を買った人物で、調査兵団のリヴァイ兵士長だ。何やらいつもに増して険しい顔で入って来た彼は、私の机までつかつかと歩み寄ると腕を捲くって見せた。そこにはざっくりと大きな切り傷がある。打撲や擦り傷が絶えないのはいつものこととして、こんなにも派手な怪我は訓練では珍しい。一体何があったのかと聞けば、訓練中に他の兵士がミスをしてそれに巻き込まれたのだと言う。それにしたって、尋常ではない反射神経を持つ彼が、本当に珍しい。 「疲れているんじゃないですか?」 「馬鹿言え」 「普段の兵長なら有り得ないことですよ。水道で先に傷口を洗って下さいね」 薬品棚から消毒薬を出しながら指示する。 きっと疲れているのだろう。日に日に隈が濃くなっていっているのは目に見えて分かった。たとえ訓練とはいえ、体調が万全でない中では怪我の確率も上がる。しかし、どれだけ私が心配して止めようとした所で彼は見ないふりだ。当然だろう、彼には責任と言うものがある。それなら尚更健康管理には気を付けて欲しい。そう強く言える立場ではないため言わないが、いつだって彼に願うことはもっと自身を顧みて欲しいと言うことだけだ。 再度差し出された腕、もういくつもの消えない傷跡に、また一つ新たな痕が残る。私は傷口を避けるようにガーゼで周囲の皮膚を消毒した。 「他に怪我人は出なかったんですか?」 「ああ」 「兵長ってば運の悪い人ですね」 「黙れ、医務室が怪我人で溢れ返っていいのか」 「これでも心配してるんです」 真新しい包帯を巻きながら口を尖らせれば、頭の上から降って来るのは小さな舌打ち。「それより…」苛立った声がそれに続いた。 「誰もいない時くらいその喋り方はやめろ」 「誰かが入って来ないとも限りません」 「お前の敬語は気持ち悪い」 「酷いわ!」 反撃のつもりで傷口を軽く叩いてやると、睨みながら頭を叩かれた。彼は手加減したつもりだろうが、兵士でもなんでもない私が受ければ十二分に痛い。 彼の言うとおり、勤務外ではこんな風に敬語を使って話したりはしない。彼が私を買ったその日から、私が敬語を使うことを酷く嫌った。しかし、とりあえず職場では誰に見られているか分からない。本来ならば、階級のずっと上である彼を相手に砕けた口調で話すことは周りが許さないことだ。一介の医務室看護師に過ぎない私の階級は、下から数えた方が早い。衛生班に所属していればまた話は別だが、私は訓練を全く受けていない人間のため、調査兵団の衛生班への異動は認められていない。そのためこうして、あらゆる部隊、階級のものが分け隔てなく使う医務室の管理を任されている。 村で医者をしていた父と、看護師をしていた母に教え込まれた知識があり、診療所の手伝いをしていたから医務室担当になれた。しかしこれも、彼やエルヴィン団長の口添えがなければ叶わなかった仕事である。あの日、彼に買われて最初に聞かれたことは、「何ができる」だった。この時、医学の知識があると聞いた彼が掛け合ってくれたのだ。 「ねえ、覚えておいて。骨折や切り傷は治るけれど、千切れた腕は元には戻らないのよ」 「んなこと常識だろうが。…そういや、今日は仕事が早く終わりそうだ」 「リヴァイ!」 ずっと両親の仕事を見て来たから分かる。人間と言うのは脆い生き物だ。例えどれだけ強くても、いつ何が起こるか分からない兵士をしている彼を、私が心配しないはずがない。彼の壁外調査が近付き、無事帰還するまで私の眠れない日々は続く。必ず、絶対などと言う言葉は、この世界では通用しないのだ。昨日まで隣で笑っていた友人が、突然いなくなることなんて珍しくなかった。 手を伸ばしかけて空気を掴んだ手を引っ込め、ぎゅっと握り締める。事実、私は彼の所有物だが、それゆえに干渉は許されない。心配するのは勝手だが口出しするな、ということなのだ。私はいつだって、首輪をはめられながら鎖に繋がれていない放し飼いに近い。どこかへ行きたい時に好きに出て行けるし、逃げようとすれば逃げられる。言わば彼は私に自由を与えている。けれどそれこそが私には苦しかった。どうせならどこへも行けないようにきつく縛っておいて欲しいのに。 感傷に耽っていると、遠慮がちに奥のベッドのカーテンが開く。一時間ほど前、熱があるため休みに来た兵士だ。 「あの…さん…」 「あ、ああ、ごめんなさい、気分はもう大丈夫ですか?今日は早く休んだ方が良いですよ」 「はい、あの…あの、さんは、その……」 何か言いたげにもごもごと口を動かし、視線を彷徨わせる。この兵士は新兵だ、聞きたいことは何かすぐに分かった。 「リヴァイ兵長とは何もありませんよ。こういう仕事をしているから関わる機会が多いだけです」 「そ、そうなんですか…」 彼に聞きにくいことは、大概私に回って来る。その多くが「さんはリヴァイ兵長の恋人ですか」であり、次いで多いのが「今日のリヴァイ兵長の機嫌はどうですか」だ。多くの者が勘繰る通りに、恋人であればどれだけ良かっただろう。名前のつけられないこの関係のせいで、私は未だに、三年前なぜ私を買ったのか、人身売買の場に彼が現れたかすらも聞けない。 恋人でなければもしや…、と更に下世話な妄想を繰り広げる兵士もいるが、全くもってそのような事実はない。誰に聞かれても答えようのない私と彼の間柄は、こうして新兵が入って来る度に話題に上がり、尾ひれがついてしまうこともある。それを否定するのはいつだって私ばかりで、彼は泳がせているだけ。 いつだったか、「勘違いされるでしょ」と言った私に、「勘違いさせておけばいい」と言われたことがある。そんなことを言われてしまえば、私こそ勘違いをしてしまう。違うのよ、と何度も言い聞かせる。本音も建前もなにもない、私たちの間にあるのは三年前に買った者と買われた者という事実のみ。 膠着状態のまま三年間、私は彼の温度どころか、唇の感覚すら知らないのだ。 |
←
 →
→(2013/06/17)