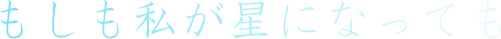
|
昔から繰り返し見る夢がある。その夢には必ず私と、会ったこともない男の人が出て来る。私とその人は、ある時は喧嘩をしていて、ある時は幸せそうに寄り添っていて、ある時は悲しい顔をしていた。けれど、どれだけ夢の中で私が地獄の底に突き落とされても、彼が引き上げてくれるのだ。「覚えておけ、何度でも引っ張り上げてやる」と言い、その乱暴な言葉とは裏腹に私を優しく抱き締めるのだ。 ただの夢ではないことは薄々気付いていた。まるで連ドラのように繰り返し見る夢など聞いたことがないし、毎回あまりにもリアルなのだ。ただの夢と疑ってかかるには、できすぎな夢だった。あれはもしかすると、前世の記憶だとか、パラレルワールドを生きる私を見ているのだとか、そんなメルヘンなことを考えなければどっちが現実なのか分からなくなるくらいなのである。 「まただ……」 「姉ちゃん遅刻するぞ!」 「うーん…」 寝起きは悪い方ではない。けれど今日は妙に体が重かった。ノックもせずに部屋のドアを開けられたら、いくらエレンとはいえいつもなら怒るところだ。けれど今日は怒り飛ばす元気もないくらいに疲れた。しっかり寝たはずなのに得られない熟睡感、寧ろ入眠前よりも感じる疲労感に、げっそりしながら上体を起こす。 「俺の入学式に遅刻しないでくれよ…」 「しないってば…今起きる…」 「おー」 社会人になって三年目の春は、大きく生活が変わった。うちの高校に入学するために、従兄弟のエレンがうちにやって来た。心配性なエレンのお母さんは一人暮らしをさせたくなかったらしく、うちで預かることになったのだ。まだぴかぴかの制服を来たエレンがそわそわしながらドアからこちらを覗いていた。…着替えられないではないか。 「エレンは私に着替えさせない気なのかしら」 「は………ちっちっげぇよ!!」 エレンはドアが壊れるのではないかと言うほど、勢いよく扉を閉めると騒がしく階段を降りて行った。若いなあ、と苦笑いしながら、自分だって言うほど歳をくってないことに気付く。 あの夢を見続けているせいで、実年齢の倍は生きているような気になる。最初は、あの男の人の顔もぼんやりと、靄がかかったかのようだった。鮮明ではなく、声だけが頼りだった。けれど、最近はやけにはっきりと彼の顔が見える。もし現実にいるなら見分けられるほど、鮮明に。夢と言うのは恐ろしくないものであればあるほど、忘れてしまうものだ。けれど私は覚えている。幸せな瞬間も、楽しいことも、嬉しい時も、彼と過ごすその時間の全てを、まるで生身の私がその場で体験したかのように刻み込まれているのだ。 記憶は倍になる。けれど人には記憶のキャパシティがある。だからか、私はよく頭痛を起こすのだ。 (もし…) もしも夢に出て来る彼が現実に生きているのなら、そして私が彼に出会えたのなら、繰り返される夢も、この頭痛もやんでくれるのだろうか。 高校の養護教員になり二年。そんな私は、夢に出て来る彼のせいで、未だに恋人の一人もできたことがない。 |
←
 →
→(2013/08/13)