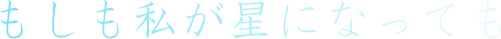
|
空を見上げて見ても、あの頃のように星の瞬く空は見えない。都会の空は明るくて、月もぼんやりしている。けれど、景色がぼやけて見えるのは決してこの街の明るさのせいだけではなかった。 「いい加減泣きやめ」 「だって…っ」 「泣かせるために来たんじゃねえんだからな」 涙で濡れた頬を包み、まっすぐに私を見下ろす。その向こうに、ぼんやりとした半月が見えた。 きっと今の私の顔は涙でぐしゃぐしゃで酷いことになっているだろう。とんでもなく不細工で、見られたもんじゃない。けれどリヴァイさんは何も言わず、ただ苦笑いをした。それでもいい、とでも言うように額に一つ、唇を落とす。そこからじんわりと伝わる熱と優しさ。 「確かにお前は、俺の記憶の中にいるとは全く違う」 「はい…」 「けど、前世で恋人だったからお前を好きになった訳じゃない」 あれはただのきっかけだ、と彼は言う。そう言ってハンカチを取り出すと、私の目元を少々乱暴に拭った。ああ、こういう夢も見たことがあるな、と頭の片隅を掠める。夢の中で私はあまり泣かない人間だったけれど、時々出て来るのだ、泣いている私が。そんな私が泣きやむまで傍にいてくれるのが彼だった。何も言わず、ただ寄り添ってくれる存在。 夢の中と今目の前にいる彼は違う。けれど、やっぱりどこか同じような所もあって、懐かしいような気がした。彼もそう思う部分はあるのだろうか。 「喜怒哀楽が激しくて、簡単に俺に振り回されて…ようやくお前は自由になったんだと思った」 「自由…?」 「自分の感情を押し殺すしかできなかったからな、あの頃は」 リヴァイさんは、私のように夢という曖昧なものではなく、前世の記憶としてはっきりと残っているらしい。懐かしむように目を細めて、けれどその目にはしっかりと今の私を映してくれている。 最初から、この人は私を見てくれていたのだ。私の中にある前世の私を透かして見ながら、今の私のことを考えてくれていた。何も考えていなかったのは私の方だ。夢の中ばかりを気にして、今を生きる彼をちっとも見ていなかった。もしも、という仮定ばかりを浮かべては、自分で可能性を潰して来た。もっと早くからまっすぐにこの人を見ていればよかったのだ。この人の好意を素直に受け止めていればよかったのだ。何も疑うことなく、屈折することなく。 「今のが好きだ」 「私も、今のあなたが好きです」 再び引き寄せられて、その肩越しに流れ星が一筋流れる。私の涙を映したかのように、それは綺麗に弧を描いて消えた。 ここがエントランス前だと言うことも忘れ、キスをする。今の彼とのキスなんて初めてのはずなのに、とても懐かしい気がした。今の彼が好きだというのに、初めてじゃない感覚。矛盾していると分かっている。けれどきっとお互いに、その矛盾も含めて愛しいと思っているに違いない。前世も、夢の中も、今も、全てが今の私たちを象るもの。結局は、そのどれか一つが欠けてもこんな風に再会できなかったかも知れない。もしかすると擦れ違いでさえも大切な過程の一つだったのかも知れない。 「もう離してやらねえ」 「こっちこそ、離してあげませんから」 ようやく、笑い合うことができた。前世の何もかもを取り払って、笑い合うことが。あの頃、この人を置いて行くしかできなかった私は、もうここにはいない。もう二度と、この人の手を離したくない。今度こそ最期まで添い遂げたいと思った。 *** 「人は死んだら星になるんですって」 「はぁ?」 は突然、訳の分からないことを言い出した。の両親の墓参りの帰りだった。辺りはもう暗く、満月が輝き、星は夜空中に瞬いている。ああ、そういえばこうしてゆっくり空を見上げることすら最近はなかった。書類と睨み合うばかりの毎日。そんな中で、無理矢理の墓参りに付き合わされたのだ。もしかしたらこいつなりに俺に息抜きをさせようとしたのかも知れない。 久し振りに仰いだ空。は一つ二つと星をなぞり、あれは誰それ、これは誰それ、と壁外調査で死亡した団員の名前を次々に挙げて行く。適当だろ、と言えば、それでもいいの、と言う。真面目な医務室職員だと思えば、時々こんなぶっ飛んだことを言う。どちらが本当の顔なのかと言われれば、まあどちらも本当なのだろうが。 「見ていてくれると思えば、寂しくないでしょ」 「寂しい?」 「私たちも、あの人たちも。みんな、同じ世界にいると思えば」 だから大丈夫よ。そう言って、は俺の手を引く。その「大丈夫」の言葉が、近い将来の別れを示唆しているような気がして、不安になる。だから、逆にの手を掴み返した。どこへも行くなと、そんな意味を込めて。きっとあの後、の手首には赤い痕がついていただろうと思う。それくらいの危うさを含んだ言葉だったのだ。 「ねえ、私も死んだら星になるわ」 「縁起でもねぇこと言うな」 「いいえ、言うわ。そうしたら、ね。一番眩しい星になってあげる。こうして空を見上げた時、一番にリヴァイが見付けられるでしょう」 空に手をかざし、目を細めた。そして、不安が確信へと変わる。きっと、彼女の命を蝕む何かがあると言うことに。 「星になって、いつか流れて、また私たちの魂は巡るわ。そして出会うの、私とリヴァイはまた」 「夢のような話だな」 「信じていれば叶うわ。ね?」 だから、もしも私が星になっても悲しまないで。はそう言った。それに頷くしかことしかできず、涙を流す訳にも行かず、そもそも俺に流す涙などなく。がどう言った覚悟で、どういった気持ちでそんな言葉を俺に残したかは知らない。だがたった一つ、俺より先に死ぬのだと言うことを悟った時点で、俺に残したい言葉全てを置いて行くつもりなのだろうと思った。重いものも、軽いものも、の内にある全てを俺に托す気なのだと。 だから俺は言った。お前がもしも星になったら俺が最初に見つけてやる、と。 |
Fin.

(2014/06/17)