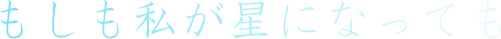
|
待合室には人はまばらだった。エレンは薬局に薬をもらいに行ってくれているらしく、待合室を見渡してみても見つからない。今動いても入れ違いになってしまうかもしれない。大人しく適当に座って待つことにした。 隣を見ると、近所の公立高校の制服を着た女の子が本を読んでいる。エレンと同い年くらいだろうか。春だと言うのに、首には赤いマフラーが巻かれていた。まだほんの高校生だというのに、病院に通わなければならに何かを抱えているのはさぞ大変だろう。大人でも参っているくらいだ。 「…何か」 「あ、いや、…その赤いマフラー素敵だなって」 「ええ…」 短く答えながら、彼女はマフラーで口元を隠した。ほんのり頬が赤くなっているのは、照れていると言うことだろうか。すっかり俯いてしまった彼女とは会話が終了する。そうして数秒、鞄の中の携帯が震えた。開けてみると、エレンからの「外にいるから出て来い」というメールだった。思えば今日は平日。身内だからと言って高校生を付き添いに病院に来たのはまずかったかも知れない。急いで外に出ようとすると、立ち上がりかけた私の腕をぐいっと引っ張る何かが現れる。その力の元を辿れば、赤いマフラーの彼女だった。 「え、と…」 「どこかで会った気がする」 「ど、どこだろう…前は病院に勤めていたから、」 「そうじゃない、もっとずっと前」 頭の奥が疼く。傷みではない、何かを思い出させようとするかのように疼く。頭を押さえていると、今度は彼女が診察に呼ばれたらしく、診察室へ入って行った。残された私は呆然とする。初めて会うはずなのに、何かが胸の中で引っ掛かる。彼女もまた、私の夢の中に関係のある人物なのだろうか。 ぼうっと突っ立っていると、痺れを切らしたエレンがやって来た。行くぞ、と言って私の腕を引っ張って行く。病院前にタクシーを呼んでおいてくれたらしい。しかしそのタクシーはまだ到着しておらず、私はエレンと病院の入り口付近で並んで待った。 エレンもそうだ、幼い頃から頭痛に悩まされていた私は、エレンが生まれてからそれが少し和らいだ。私とエレンの実家は近かったけれど、私が就職のために実家を離れたらまた頭痛は再発し始めたのだ。そして一緒に住んでいる今、頭痛は減っていたはずだった。 (リヴァイさんと離れて平穏に過ごす方法はないのかな…) いつからか、逃げ道ばかりを探すようになっていた。前の職場で大きなミスをして、どんどん居場所がなくなって行って、退職せざるを得なかった。あれからだ、いろんなものに対して逃げることばかりをして来た。職場の人間関係もそう。深く関わらなければ欠けた部分を知られることはないと、親しくなることを恐れた。そして何より、リヴァイさんから逃げている。 夢の中に出て来る私は、今よりずっと大人で、強くて、芯のある女性だ。今を生きる私とはまるで違う。けれど、リヴァイさんが見ているのは、夢の中にいる強い私だ。私であって私でない、もう一人の私。そんな私と重ね合わせて見られた時、今の私の弱さに失望されることが怖い。お前じゃない、と否定されることが怖い。ぶつかって行くしかない、と先生は言ったけれど、ぶつかるだけの勇気もないのに。 「なあ、姉ちゃん」 「なに?」 「リヴァイさんと喧嘩でもしたのか?」 「え…?」 「最近連絡取ってないだろ」 あんまり携帯触ってないから、と前を向いたままエレンは言う。私が家で携帯を触ることはほとんどなく、使う時と言えばリヴァイさんと連絡を取っている時くらいだった。エレンも随分目敏くなったらしい。そんな所まで見られているとは思わなかった。 喧嘩ではない、私が一方的に避けているだけだ。けれどそれをどう説明すればいいのか分からず、私は黙った。 「心配するんじゃねえの、姉ちゃんが病院に運ばれたなんて聞いたら」 「…………」 「あの人、姉ちゃんのこと好きみたいだし」 「…は?」 「姉ちゃんも好きなんだろ、あの人」 突拍子もない言葉に、思わずエレンを見上げる。違うのか、と何の疑いもない目で見られて私はまた返事に困った。エレンとリヴァイさんは一度しか会ったことがないはずなのに、エレンはどうしてそこまで察してしまうのか。確かによく連絡はとっていたし、家に押し掛けられたこともあった。休日、突然用事に駆り出されたこともある。それを見ていたら何かあるとは察するだろうが、友人関係とは思わなかったのだろうか。或いは、仕事の関係だと。 「何があったかは知らねえけど、話もしないで仲直りは無理じゃないのかよ」 「…うん」 その通りだ。エレンの言っていることは正しい。先生の言ったことも正しい。向かい合ってみなければ分からないことはたくさんある。ただ、そこには大きな覚悟を伴う。リヴァイさんにがっかりされたくない、という気持ちが前面に出て来ているのだ。いや、既にメールを無視し続けている時点で私への印象はマイナスを極めているだろうが。 私にとっては、これが初めての恋なのだ。ずっと夢の中の彼がちらついて離れず、好きな人の一人もできなかった私が、現実で初めて心惹かれた人。やっと出会えた人なのに、こんなにも苦しい思いをするとは思わなかった。記憶が何もかもの邪魔になって、私を臆病へと突き落とす。いつまで続くか分からない頭痛を抱えるのは本当はとても怖くて、誰かに分かってもらいたくて、傍にいて欲しくて、それがリヴァイさんだたらどれだけ幸せだろうと思った。 口が悪くても、目付きが悪くても、無茶ばかり言って来たって、その実、心配性で私のことを気にかけてくれるリヴァイさん。本当は、メールも電話もできないこと、会えないことが辛い。会って全てを話してしまいたい。一人で抱え込んで来た時間はあまりにも長かった。甘える先が欲しいのだ。 「エレン」 「ん?」 「ありがとう」 「おう」 学校に着いたら、リヴァイさんに連絡しよう。謝らなくてはならないことがたくさんある。それから、伝えなければならない大事なことも。本当は会いたくて仕方なかったこと、リヴァイさんが好きなこと、だから怖かったこと。あの人から逃げていては、いつまでもこの頭痛からは解放されない。頭痛が続く理由も、胸が痛む理由も、全てはリヴァイさんにある。もうこれ以上逃げてはいけないのだ。 |
←
 →
→(2014/04/23)