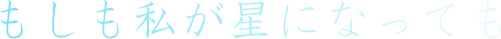
|
この前の日曜日にリヴァイさんと出掛けて以来、私はまた頭痛が治らなかった。薬を飲んでも一時的に軽くなるだけで、頭の奥から響くような鈍痛はすっきりしてくれない。どれだけ寝ても、どれだけ薬を飲んでも治らない。それは、今の職場に変わって来る前と同じ状況だった。 今朝もまた、起きた時から頭痛が続いている。夜もほとんど眠れていない。寝不足も続き、そろそろ顔も酷いことになって来た。 「姉ちゃん、病院行って来た方がいいんじゃねえ?」 「んー…定期受診、明後日だし…それまでがんばる」 「とか言ってる内にまた倒れたらどうするんだよ」 レントゲンを撮ってもCTやMRIを撮っても異常がなく、脳波も異常がない。原因が分からず、医者もお手上げだ。けれど、その後紹介されたのは心療内科。そこで出会ったのが親身に話を聞いてくれる先生だったため、カウンセリングを中心に定期的に診てくれている。 ちょうど明後日が次の受診日であり、私の頭痛は命に関わるようなものではないため次の受診日まで待とうと思っていた。しかし、エレンから強く反対されてしまう。仕方なく今週十何錠目かの鎮痛剤を鞄から取り出して、口に放り込もうとしたら今度は腕を掴んで止められた。 「それ今週で何錠目だよ、昨日の晩も飲んでたことくらい知ってんだぞ。もうやめとけって」 「でも飲まないと仕事…」 「だから先に病院行けって!午後から出勤でもいいだろ!」 「ちょっと、あんまり、叫ばないで…病院、行くから」 「あ…いや、わり…」 じゃあタクシー呼ぶからな、と言うと、エレンは冷蔵庫に貼ってあるタクシー会社の電話番号を見に行く。電話をかけるエレンの声を遠くに聞きながら、机の上に突っ伏した。ここ3、4日間、無理矢理身体を起こして仕事に行っていたが、やはり今日はもう無理そうだ。学校にも電話をかけなければならない。こういう時、誰にかけたらいいのだったか。誰を呼べばいいのだったか。 携帯を取りに立ち上がると、途端にぐにゃりと視界が歪んだ。強い眩暈に膝がかくん、と折れる。 「姉ちゃん!!」 駄目だ―――そう思った時にはもう遅く、私は床に倒れ込んだ。頭を打って余計痛いが、それよりもまだ続いている眩暈と頭痛の方が辛い。焦るエレンの声が近付いて来るけれど、自力で起き上ることもできない。更に、どんどんと重くなる瞼。もう目を開けていられなくて、私はそこで意識を手放した。 *** 「あ、目ぇ覚めた?」 数回瞬きを繰り返し、ゆっくりと首を巡らせると、ここは通い慣れた病院であることが分かった。主治医である先生は私の顔を覗き込んで笑いかけて来た。 ひんやりと空気に触れる左腕は剥き出しで点滴が繋がれていた。100mlの輸液ボトルの側面には、鎮静剤を混注した証として薬剤のシールが少々雑に貼られている。私の頭痛が強い時にいつも投与してもらう薬だ。その内容量はもう残り僅かのようだ。滴下もゆっくりになっている。 「とりあえず、いつも通り鎮静剤入れたからね。…?」 「あの、エレンは…」 「エレンなら前の待合で待ってるよ。それよりあなたは自分の心配をしなさい」 倒れるまで我慢するなって言わなかった?と厳しい声で言う。私は素直に「ごめんなさい」と口にした。 頭痛はすっきりとはいかないものの、大分おさまっていた。まだ耳の奥で鈍痛が響く気はするが、耐えられないほどではない。鎮静剤のせいでまだ少しぼんやりとする意識の中、痛みに絡んで声が聞こえる。夢と今の狭間で揺れる声はリヴァイさんのものだ。それを拒もうと頭を振れば振るほど痛みはまた強くなる。 こめかみを押さえてぎゅっと目を瞑れば、困ったように先生が溜め息をついた。そしてこれまでの私の経過を整理するように話し始める。 「の頭痛は極めて特殊だ。幼い頃から続いていて、けれどある一定の条件を満たすとそれは軽減する。その条件が満たされない時に頭痛は強くなり、ついには事故が起こり君を退職にまで追い込んだ」 「あれは、私のミスです」 「そのミスを引き起こすきっかけになったのはその頭痛であることに違いはないよ。けど、お陰で新しい職場ではさほど頭痛に悩まされなくなった」 輸液ボトルはとうとう空になる。先生は「抜くよ」とだけ言って点滴を抜針した。左腕の違和感がなくなり、顔の前で手を開いたり握ったりしてみる。ずっと腕を伸ばしていたせいで感覚が鈍い。 「その“ある条件”が何か分かる?」 「いえ…」 「人だよ」 その言葉に迷いはなかった。これまでもそれらしいことは言われていたが、恐らくだとか、もしかするとだとか、そういった曖昧な言葉が頭についていたのだ。それを今回は言い切った。ということは、何か理由があるのだろう。私が薬で眠っている間にエレンから何か聞いたのかも知れない。 先生の肩越しに見えた壁時計はもうすぐ十二時を指そうとしていた。午後からは出勤しなければと思っていたのに、どうもそんな気が起こらない。このままもう一度眠ってしまいたいような気にもなる。とにかく身体が重くてだるい。本当はこうして先生と話していることすら億劫なのだ。 もしかするとそれは、ぼんやりと先生の言葉の続きを察していたからかも知れない。 「、君の夢に関係する人物に近付いた時、その頭痛は軽減する。けれど離れようとすればするほどまた頭痛は増強する」 「そんなこと……」 「君には随分詳しい生い立ちを聞いた。初回のカウンセリングからの記録を何度見直してもそれしか考えられないんだ」 まるで、拒もうとする心を戒めるかのようだ。どれだけ関わりたくない、もう離れてしまいたいと思ってもそれを許されない。私の頭痛の軽減と増強の鍵を握っているのは、今ただ一人しかいない。それを認めたくない。どうしても受け入れたくない。私が見る夢だとか記憶だとか、そういったものとは関係ない所にいて欲しかった。ずっとこの頭痛に振り回されて来て、私は自分が傍にいる人すら自分で決められない。 「でも、嫌なんです…っ」 何が、と問われれば具体的に説明することはできない。私に近付いてくれる人を、触れようとしてくれる人を拒みたい理由なんて、子どもじみた我儘でしかない。理由にすらなれない。手を差し伸べてくれるのに、素直に手を重ねられない。何も考えずに飛び込んでいたならきっと楽だ。けれど、このもやもやとした気持ちを押し込めたまま、これ以上彼に近付いてしまうことは、自分が許せなかった。 そんなこと、とあの人だって気にしないかも知れない。けれどそれはあの人が今ここにいる私を見てはいないからではないのか。そう思うと、どうしても最後のラインを超えることができなかった。確かめることすら怖かった。あなたは私を知っているの、と訊ねることなんてできやしなかった。多分これは、意地と我儘だ。 ひくり、と喉が引き攣った。涙が目尻を伝って流れて行く。頭の中はぐちゃぐちゃだった。訳が分からなくなると泣いてしまうのも、私の悪い癖だ。 「だったら、ぶつかって行くしかない」 「むり、できない…」 「じゃあずっとその頭痛を抱えて生きて行く?今は良いけど、また同じような事故を起こしたら?」 「それは…!」 「、きっと思っているより難しいことじゃないはずだよ」 先生は私の頭を撫でると、優しく笑った。 ぶつかるなんて、そんなことできるだろうか。臆病で逃げ回ってばかりの私が、あの人にぶつかって行くだけの勇気を出せるのだろうか。その時、彼から何を言われるか考えるだけで不安になる。自分から拒んでおいて、拒まれた時の心配をするなんて随分と自分勝手な話だ。 あれから、リヴァイさんには碌にメールもしていない。それでもまだ、お願いすれば私の幼稚な言い訳を聞いてくれるのだろうか。 |
←
 →
→(2014/02/02)