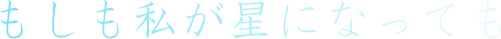
|
女性向けの腕時計のショーケースを見ていると、「待たせたな」と後ろから声を掛けられた。その手には、電池交換待ちの番号札が握られている。 「買わなかったんですか?」 「思ったようなのがなかった」 「ああ、それで電池交換待ち…」 一頻り店内を見たが、しっくりくる時計がなかったようで、結局は壊れたと言っていた時計の電池交換をしてもらったらしい。途中までは私もリヴァイさんについて回っていたのだが、店員さんに「彼女さんですか?」などと言われ、勝手に気まずくなった私は「じゃあ私!あっち行きますね!」と一人行動していたのであった。とはいえ、さほど広くない店内、はぐれることはまずないのだが。 「お前も買うのか?」 「いえ、私は今のが気に入っているので」 「それか」 私の左手首を見て言った。文字盤が淡いブルーである以外、さほど装飾のないシンプルなシルバーの時計は、高校に入学する時に両親がプレゼントしてくれたものだ。かれこれ八年は使っているため愛着もあり、私の手によく馴染んでいるため手離せない。 あまりにも彼からの視線を感じたため、ぱっと腕を後ろに隠す。すると、彼もふいっと顔を逸らした。細ぇ腕、そんな呟きが降って来て顔を上げると、彼とぴたりと目が合う。そして何かを言い掛けて彼が閉じていた口を開いた時、「番号札6番でお待ちのお客様ー」と空気を読まない店員の声がかかる。リヴァイさんは小さく舌打ちをして、「ここで待ってろ」と言うと時計を引き取りに行った。 何かを言い掛けて止められると、気になって仕方なくなる。戻って来たリヴァイさんはもう何も言わなかった。「行くぞ」とだけ言うと車に戻るよう促したが、例え些細なことだとしても、私に向けられた言葉は全て拾いたい。けれど、今更「さっき何を言い掛けてました?」と聞くのもくどいような気がして、結局聞けない。 来た時と同じように助手席に乗り込み、シートベルトをすると、彼からとんでもない一言が飛び出した。 「この後、どうする」 「……え、ノープランですか」 「ああ」 「堂々と頷く所じゃないでしょう…」 まさか、先程言い掛けたのはこれだったのだろうか。本当に時計を見に来ただけだった事実に呆れる。とはいえ、彼に「お任せします」は通じなさそうだ。しかしこの短い付き合いの中でも、彼が人混み嫌いなのは十分承知している。まさか、休日の昼間に買い物に付き合わせるなんてできるはずがない。 「じゃあ、行きたい所が…」 *** こんな所で良かったのか、と車を降りてリヴァイさんは言った。私が笑って頷くと、不可思議だとでも言いたそうな顔をする。連れて来てもらったのは、海に面した広い公園だった。天気も良いし、ここならたくさんの人がいると言えど、ショッピングモールほど人混みではない。私の提案は正解だったようで、彼は相変わらず難しそうな顔をしているが嫌そうではない。 「休日くらい、ゆっくり時間が流れる場所で過ごしたいと思いません?」 「時間の長さは変わらねぇだろうが」 「そういう意味じゃなくて!」 いつも通りのリヴァイさんに吠える。きっと私の言いたいことは分かっているだろうに、いちいち揚げ足を取って来るので私もつい言い返してしまう。 雲ひとつなく晴れ渡っているとはいえ、さすがにまだ風が肌寒く、私はストールを巻き直した。そして、海岸線に沿って微妙な距離を空けながらゆっくりと歩き出す。すぐ隣でもなく真後ろでもない、一、二歩斜め後ろを私はついて行った。 海に目を向けると、水面に反射する太陽の光がきらきらと眩しく、私は目を細めた。私がこの公園に誘ったのは、海を見たいからだった。特にここは家から離れた場所でもなく、来ようと思えば多少時間はかかるが自転車で来られないこともない。けれど、この人と海を見に来たかった。「どこへ行きたい」と聞かれて、最初に浮かんだのが海だったのだ。 特に会話もなく、ゆっくりと歩き続ける。それは、「ゆっくり時間の流れる場所で過ごしたい」という私の願いを聞き入れてくれているようだ。そんな中、私の少し前を行く彼が不意に口を開いた。 「…お前、なんで養護教諭なんかしてんだ」 「え?」 思いもよらなかったあまりに唐突な質問に、私は変な声が出た。思わず立ち止まると、彼も立ち止まり、そして振り返る。その目は別段、責めたいわけでも問い詰めたい訳でもないらしい。私が言葉に詰まっていると、続けて彼が言葉を繋いだ。 「前の仕事の方が給料いいだろ」 「うーん…向き不向きの問題でしょうか…。私は保健室で生徒たちの話を聞いたり、学校の衛生環境を管理する方が向いてると思ったんです」 「ふうん…」 回答の内容に納得したのか、それだけ返事をするとまた前を向いて歩き出す。私も遅れないように速足で追いかけた。 追いついたその瞬間、呟くよりも小さく微かな声で「変わらねぇな」と彼は言った。そして、ぱっと顔を上げて彼の横顔を見てみれば、いつも崩れることのない表情が、きつく結ばれた口元が緩んでいる。そんな彼を目にして、私はまた足が止まってしまった。 この人が見ているのは私じゃない、と思った。私と彼の間には確かにどこかで何かがあって、それはきっと科学なんかで証明できるようなものでも、理屈なんかでもなくて、もっと次元を超えた話なのだろうと思う。けれど、彼の全てが昔から記憶にある訳ではない私は、確かに今目の前にいる彼に恋をしていた。きっと記憶なんてものは、夢なんてものはきっかけに過ぎなくて、今ここで生きている彼こそを、私は思っているのだと。 (でも、この人は違う…) きっと私よりもっと明確な何かを掴んでいるのではないだろうか。はっきりと、鮮明な記憶を持っているのではないだろうか。だから、言葉の端々に引っ掛かりを覚えるのだ。記憶の中にいる私ではない私と重ねて、比べて、そうして紡がれた言葉に、私は唇を噛んだ。 違う、私を見て、私に話しかけて―――そんな言葉を言えるはずもなく、私は口を閉ざす。さっきよりも二歩後ろを歩くことしかできなくなってしまう。 すぐ目の前で警戒心の欠片もなく晒された左手を掴もうとして、けれど、どうしても掴めなかった。 |
←
 →
→(2013/11/30)