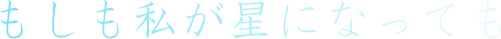
|
あれから、私とリヴァイさんは連絡を取り合うようになっていた。どういう心変わりかは知らないが、メールにしろ電話にしろ彼は優しく、まるで別人のようだ。そんな変化に戸惑いつつ、現実で彼と繋がりを持てたことに嬉しさを感じずにはいられない。そこに、夢の中の彼と、リヴァイさんをどこかで重ねてしまってはいないかという後ろめたさがありながら、彼を無碍にすることも、振り切ることもできない。彼の優しさに、私はすっかり甘えてしまっている。彼に今、特定の恋人もいないと知ってしまっては、なおさら。 仕事は終わったのか、気を付けて帰れ、まだ寒いからあまり手足を出すな―――私を心配する言葉ばかりが並ぶメールを見て苦笑いする。もう帰ろうと、トレンチコートを羽織ろうとしている時だった。ちゃんとコートを着てから、私は少し悩んで返事を打つ。リヴァイさんからのメールにすぐ返事を打たなければならないと、初回に無視をした時に学んだ。これから帰るので大丈夫です、そこまで打って、また悩む。事務的な感じはしないが、律義にもほどがあるメールへの返事にはいつも時間を要する。ようやく、「リヴァイさんも体調には気を付けて下さい」という一文を加え、送信ボタンを押す。送信完了の画面に切り替わってから、私は鞄に携帯をしまう。 「いつも嬉しそうにメールするねぇ、先生」 「へっ!?」 向かいの席の先生が、私のデスクの向こうから首を伸ばして面白そうに笑った。どきりとして思わず鞄を握り締める。そんな私をからかうように、「いいなあいいなあ、例の教材メーカーの人なんでしょー」などと図星を言い当てるものだから、途端に顔が熱くなる。 そんなに分かりやすい顔をしてメールをしていただろうか。聞けば、「最近退勤時はとっても幸せそうか残念そうかのどちらかだから」と言われてしまった。 「まあ、幸せなのはいいことだね。頭痛も減ったみたいだし」 「あ…そういえば…」 夢を見た翌朝などは、よく頭痛を起こしていた。ズキズキという可愛らしいものではなく、ガンガンと頭の中に響くような痛みなのだ。最近は、夢を見ても頭痛を起こす頻度は少なくなったように思う。もしかしてリヴァイさんと近付いたことと関係があるのだろうか。このまま夢も見なくなると嬉しいのだが。何せ、なかなか濃い夢を見た翌朝は寝起きが頗る悪く、リヴァイさんと近付いてしまった手前、凄まじい罪悪感に襲われもするのだ。しかしそれをまさかリヴァイさん本人に相談する訳にも行かない。ずっとリヴァイさんの夢を見続けていることも言えていないのだ。 私の部屋に彼が押しかけて来た一件以来、私はほぼ確信している。リヴァイさんも私を知っているのだと。そして向こうも、私が彼を知っていることに気付いている。だって、そうでなければ出会ったばかりの人間にあそこまでするはずがない。エルヴィン先生に私の家を聞いてまで、休日の朝に押しかけて来るはずがないのだ。あの出来事で、ようやく私は確信を得ていた。携帯のアドレスを回りくどいやり方で以て聞き出したこと、あの夜一緒に帰ってくれたこと、その裏にある理由を。言わないのは気まずさからか、優しさからか。 一歩を踏み出し損ね、タイミングを見失い、私は立ち止まってしまっている。 *** 「買い物ですか?」 「どうせ暇だろ、付き合え」 「…暇ですけど、言い方…」 横暴だなあ、と思いながらも、実際に予定がないのだから仕方がない。私があまり休日に出歩かないことを知っているリヴァイさんは、こうして急に朝になって電話をして来ることがある。本当に突然だ。せめて前日にでも連絡してくれれば断りなどしないものを、毎度脱力してしまう。家の中にいたって特にすることはなく、日がな本を読んだり掃除をしたりするだけなので、突然電話が来ても困りはしないが、それならちゃんとメイクだってするのに、と溜め息をついた。 私とは逆にエレンは休日の度に外に出て行っており、部屋の中は非常に静かだ。ただし夕飯までには帰って来ると言っていた。エレンを預かっていることをリヴァイさんも知っているため、そう遅くまで付き合わされたことはない。むしろ、私とエレンと彼と、三人で食卓を囲むということがここ最近の休日の夕飯の風景となっていた。 「あと五分でそっちに着く。エントランスまで出て来てろ」 「え!?ちょっ五分!?」 「後でな」 ぶつりと一方的に切られた電話。五分、五分で外出用の服に着替えて、メイクももうちょっとして、鞄を用意して―――なんて全部はやっていられない。携帯をソファの上に放り投げると、部屋に駆け込んで真っ先に服を着替える。次に洗面所にダッシュして適当に後ろで結っていた髪をほどき、クリームを付けて整え、綺麗にサイドで結び直す。ピアスを付け替えている暇はない、もうメイクも直せない、せめてルージュは、と思い、部屋に戻って鞄をひっくり返し、メイクポーチからルージュを取り出す。コンパクトの鏡を見て塗りなおしていた時、ピンポーンと空気を読まないインターホンが鳴った。早い、早すぎる。 「は、はいっ!」 「遅ぇ」 「ま、ま、待っ…!」 「俺の機嫌が悪くなるまでに降りて来い」 「わ、わああああ…!」 お財布と、メイクポーチと、携帯と、ハンカチと。それだけ外出用の鞄に入れ替え、急いで部屋を出る。こんなに急かされたのは初めてだ。いつもは大概、「これから家を出る」だったのに、今日は既にすぐそこまで来ているだなんて。さすがに顔を見たら文句の一つや二つ、いや、三つや四つ言ってやらなければ気が済まない。いくら年上相手と言えど。 エレベーターを待っていては更にリヴァイさんを待たせることになるので、階段を使って六階から駆け降りる。転げるようにエントランスに走り込んだ時には、仁王立ちで彼が待ち構えていた。何か言ってやろうにも、息切れで何も言うことができない。髪も結局ぐしゃぐしゃになってしまい、額やら背中が汗でべっとりしている。朝から何をさせるんだこの男は、と睨んでみても「ぎりぎりだ」とだけ。 「ちょ…っと…!」 「なんだ」 「つかれ…っ、待っ…!」 「…情けねぇな」 「は…!?」 息も絶え絶えに抗議の声を上げると、彼は溜め息をついて私をひょいと担ぎあげた。「なっ!はなし…!」「うるせぇ」問答無用でそのままエントランスを出る。そして、マンションの前に停めてあった車の助手席に、文字通り放り込まれた。これが知人でなかったら拉致と言えると思う。 ドアも外から閉められると、私はガラスにゴン、と頭をぶつけながら凭れた。まだぜえぜえと肩で呼吸を繰り返していると、運転席から乗って来たリヴァイさんが「これでも飲め」とペットボトルの水を差し出す。これで許そうとは思わないが、喉から手が出るほど飲み物が欲しい私は、ひんやりとしたそれを受け取り、一気に三分の一ほど飲んだ。 「だ…っ、大体リヴァイさん、あなたねえ…!!」 「少しでも早く会いに来たかったんだ、これくらい見逃せ」 「は……、は、え、い、いや、見逃せません!」 「…相変わらず細けぇな」 舌打ちをすると車のエンジンをかける。もうこれ以上は何を言っても無駄だ。無理矢理で、あまりにいきなりで、自分勝手な注文をつけ放題だったのに、それでも、目が合った瞬間最初に浮かんだのは怒りではなく嬉しさだった。せっかく彼が買い物の相手に私を選んでくれたのだから、機嫌を損ねることもしたくない。既に疲れているし、これ以上歩ける気もしないが、どうしても私は甘いらしい。運転するリヴァイさんの横顔を見ただけで、「まあいっか」と思えてしまうくらいには単純だ。 暫く道を走らせ、何度目かの赤信号に捕まっている時に、私はタイミングを見計らって話しかけた。 「…ところで買い物って何ですか?」 「仕事で使ってる腕時計が壊れた」 「買うんですか?電池交換すればいいのに」 「もう何年か使ってる。そろそろ買い換えてもいい」 「お金持ちの発言ですね…」 時計でも携帯でも、壊れるまでは使うようにしている私には、ちょっと理解できない。そういえば、この車も結構良い車だったと思う。車内もとても綺麗だし、随分とまめに掃除をしているのだろう。何度か食事も一緒に行ったが、随所に潔癖とも言えるほどの綺麗好きを発揮しているのを見る限り、きっと彼の家も相当綺麗なのだろう。そう思うと、彼を家に招く時はもっと綺麗にしておこうと思った。 「疲れたか、」 唐突に、そんなことを聞く。なんて今更な、と顔を引き攣らせつつ、「そうですね」と答えればこつんと頭を小突かれた。いや意味が分からない、と今度は目をぱちぱちさせながらリヴァイさんを見る。けれど当然、運転中の彼と目が合うことはなく、私が見つめるのは横顔だけ。小突かれた所を自分でくしゃりと撫でてみる。 許すつもりなんてなかったのに。早く会いたかった、なんて言葉で騙されるつもりなんてなかったのに。どうしてか、たった二人でいるこの空間があまりにも心地良くて、急かされたし走らされたし散々だった癖に、ああこの人が好きだな、と、ふと思った。 |
←
 →
→(2013/10/26)