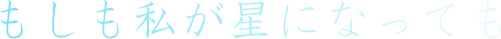
|
「私、心配だわ」 「何がだ」 「私がいなくなったら、あなたを心配してくれる人はいるのかしら」 徹夜で机に向かうリヴァイを前に、大きな溜め息をついた。何杯目か分からないコーヒーを渡すと、またそれを口にするリヴァイ。しかしそろそろカフェインも効かないらしく、眠気と苛立ちで不機嫌も最高潮に達したリヴァイの顔は険しい。ただこちらを見返しただけなのに睨まれたかのようだ。益々呆れる。部下には体調管理をしっかりしろと口煩く言っておきながら、自分はこれなのだ。 「心配してくれる人はいても、止めてくれる人こそ必要ね」 「…余計なお喋りで邪魔すんなら帰れ」 「私と過ごせる時間を仕事にとられてるんだと思うと妬けちゃう」 「頭でも湧いたか」 「失礼ね!」 たまには甘えさせてくれても良いじゃない。欠伸混じりにそう言えば、とうとう彼は大袈裟に溜め息をついてペンを置く。どうやらもう仕事は諦めたらしい。どうせこの様子じゃいつもの倍は時間がかかってしまう。恐ろしい形相で近付いて来たかと思えば、私の頭をいきなり掴んで上を向かせた。頭を、というよりは髪を引っ張られ、そんな乱暴なことをされたことがなかった私は戸惑う。 「いなくなったら、なんて縁起でもないことは言うな」 「いた…っ」 「分かったか、」 「わ、分かったってば、んっ」 直後、キスをしたかと思えばガリッと嫌な音がする。同時に広がる唇の痛みと血の味。顔を歪めると今度は傷口を舐め、満足そうな顔をする。この男とは暫くキスをしないでおこうと思った。 *** かくん、と頭が落ちて目が覚めた。どうやら転寝をしてしまっていたらしい。ずっと下を向いていたせいで首の後ろが痛む。痛む箇所を擦りながら、壁にかかった時計を見ればもうお昼前。随分長い転寝をしてしまった。後ろで寝ている彼も起きる気配がないことから、お互い眠れない夜を過ごしたらしいことが察せられた。 多分、夢の中の私は彼に恋をしている間ずっと幸せだったのだ。他愛のない会話も、些細な良い争いも、恋人らしく過ごした時間も、何もかもが宝物だったのだ。それを私自身のものと、私と目の前にいるこの人のものだと思ってはいけない。夢の中の自分と重ねているのは私だけで、この人は違うかも知れない。それを確かめない内は余計な期待を抱いてはいけないのだ。それなのに、あまりにもこの人が夢の中の彼と同じだから困惑してしまう。私に近付いてくれたのは、私を心配してくれたのは、もしかして、もしかしてと、愚かにもそんなことを考えてしまう。 その時、唸るような声が聞こえ、とうとう起きたかと後ろを振り返る。まだ眠そうに目を擦りながらゆっくりと体を起こす彼に、私はソファから離れた。 「お、はよう、ございます…」 「…お前も寝てたのか」 「お恥ずかしいながら…」 「泣いたのか?」 目が赤い、と言って私の目元に手を伸ばす。そして優しく、親指で撫でた。彼からの視線が気まずくて、思わずそっと目を伏せる。 泣かなかったと言えば嘘になる。けれど目が腫れるほど、赤くなるほど泣いた覚えはない。きっと寝不足が原因の大半を占めるだろう。だけどそれを言うとなんだか言い訳がましくなるような気がして、私は黙った。相変わらず彼は私の目元を撫で、そしてしまいには頬を撫でる。華奢な癖に、やはり女の私より大きな手は、頬を包んでもなお余る。私は、ごく自然に彼の手に自らのそれを重ねた。 「ごめんなさい」 するりと出て来た言葉に、彼は目を丸くした。きっと、彼が欲しているのは謝罪なんかではない。けれど謝らなければならない気がした。昨日のことだけでなく、もっとたくさんの、私が勝手に抱いた希望に対して。ここで、「だからもう会わないでおきましょう」というのが賢い選択なのだろうと思う。私にあの夢が付き纏う限り、どうしても彼を重ねてしまう。どちらを好きなのか分からなくなってしまう。前世の記憶など、邪魔なだけだ。本当に巡り会ってしまうなら、こんなもの要らなかった。本物の運命だとしたら、記憶などなくても出会った瞬間に分かるものではないのか。 けれど、ごめんなさいの続きを言うより先に、彼はソファを降りて、私の肩に頭を乗せた。そして酷く憔悴した声で言ったのだ。心配掛けさせるな、と。 「もう勝手にいなくなるな」 「…………」 「返事は」 「…はい」 私は確信する。この人も私と同じように夢を見ているのだと。夢の中で私と出会っているのだと。けれどそれを口に出して確認するのは何か違う気がして、私は開きかけた口を真一文字に結んだ。聞けない、聞いてはいけない。“もう”勝手にいなくなるなという言葉を深く考えてはいけない。夢の中で見る前世の私と彼は、今の私と彼とは全く違うものなのだ。そう考えなければいけないのだ。 ずきんずきんと、頭の奥から鈍痛が響く。覚醒したまま前世のことを考えるといつも起こる頭痛だ。それはきっと警鐘。これ以上考えてはいけないのだと言う危険信号。けれど離れずにはいられなくなってしまった。あまりにも悲しそうに、そんなことを言うから。「いなくなるな」と言うから。 未だ私から離れようとしない彼に腕を回し、何度も何度も頭を撫でた。小さい子をあやすみたいに。夢の中で何度もこの人がしてくれたみたいに。 |
←
 →
→(2013/10/17)