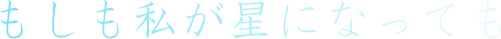
|
頭で理解するよりも先に、それは感覚としてやって来た。一目見た瞬間、身体の真ん中を突き抜けて行った感情、溢れそうになった言葉、そしてたった一つ、私の頭の中に浮かんだ言葉は、“運命”。それ以外になんと言えば良いのだろう。これまで、彼の出て来る夢は夢でしかなかったが、彼に現実で出会った瞬間、あの夢は私のもう一つの現実なのだと思った。 会いたかった人、会えなかった人、望んでいた人、待っていた人、求めていた人。私の全ての恋慕の情が一気に溢れ出す。けれどそれを理性でぐっと抑えつけた。夢の中の私と現実の私は繋がっているけれど、夢の中の彼と目の前の彼が同じように繋がっているとは限らない。それを言葉で確認することに、私は臆病になった。 それを後悔して泣いた昨夜。流石に大声を上げて泣くとエレンに不審がられる。枕に顔を押し付けて、やり場のない気持ちを吐き出すように泣いた。誰かを好きでこんなに泣くだなんて思わなかった。もちろん、その夜見た夢も最悪だ。私と彼は酷く喧嘩をして、仲直りもしないまま彼は壁の外とやらに赴き、ただ自分は下らないことで喧嘩したことをひたすら後悔していた。彼の安否を知ることなく、私は目が覚めたのだ。 (ああ、結局あの人にメールの返事をしていないわ…) 朝になると可哀想なほど真っ赤に腫れてしまっていた目。酷い私の顔を見てエレンは目を丸くしたが、そこはさすが鈍感な従兄弟君である、「蜂にでも刺されたのか!?」とすっとぼけたことを聞いて来た。私はもう、曖昧に笑うしかない。けれどお陰で少し目は覚めた。 そして土曜日のため少しのんびりと朝ご飯を作っていると、エレンが慌ててキッチンに戻って来た。 「姉ちゃん!大変だ!」 「なによ、変な顔して」 「家の前に不審者がいる!」 「不審者?」 こんな朝早くに不審者だなんて、不審者も大したものである。おかしな勧誘やセールスがこんな時間に動き出すはずがない。不審者と見せ掛けて私の知人でも訪ねて来たのだろうか。とりあえず、フライパンの中のフレンチトーストをお皿に盛り付けると、エレンに先に食べておくように促す。 管理人や友人だとしたら遠慮なくインターホンを押すだろうし、まさか本当に不審者なのだろうか。私は恐る恐る、玄関の覗き穴からドアの外を見た。するとそこには驚くべきことに、玄関前の柵にもたれた彼がいた。低血圧なのか、その表情は昨日よりも更に恐ろしく見える。出るべきか、出ないべきか、けれどこのまま彼を放置しておくといつまでいるか分からない。しかもいつからいたのか不明である。放っておけば彼の眉間のしわが更に深くなるような気もする。 私は、覚悟を決めて玄関のチェーンを外し、鍵を開けた。意味もなく音を立てないようにドアを開けると、携帯を触っていた彼がこちらを向く。すると、その瞬間ドアに手と足を差し込んで閉められないように固定をした。 「ひぃ!!」 「オイ、てめぇふざけんじゃねぇぞ」 「な、なななななんですか」 「ほう…とぼけるつもりか…。家に着いたら連絡入れろと言ったことを忘れたとは言わせねぇ」 「わ、わすれて…」 「忘れてねえよな?俺のメールも読んだんだろう?」 怖い。凄まじく怖い。学校一怖い教師に「教室の窓を割ったのはお前だな?お前なんだろう?白状したらどうだ?」と尋問されているようだ。今朝とは違った意味で泣きそうになった。果たして、メールの一通や二通送らなかったくらいで、ここまで怒られなければならないものなのだろうか。昨日も言った通り、私は道も分からぬ小学生ではない。それに、そこまで心配されるような中でもないはずだ。 (それより、なんで私の部屋を知ってるの!?) 教えた覚えはないはずだ。彼が知っているのは私の名前と職場、メールアドレス、それと電話番号くらいのもので、それ以上の個人情報は何も知らないはず。 「てめぇの部屋なんざエルヴィンに聞いた」 「エルヴィン先生!?」 「…なあ」 ドアをどれだけ引いても彼の力には叶わない。ドアのこちら側に押し入ろうとすると彼を防ごうにも、防ぎようがない。とうとう身体をねじ込み、大きな音を立てて玄関の扉は閉まる。そして、思わず後ずさった私の腕を掴み、逃げられないように腰にまで手を回して来た。 エレンの言っていた通りこれでは不審者だ。しかもまだ現実では大した付き合いのない彼とこんなにも密着してしまっている。恥ずかしい話、夢の中ではそれ以上のことも数えるのが嫌になるほどしているが、夢の中で味わう感覚と今とでは全く違う。恥ずかしいやら恐ろしいやらで、私は顔が引き攣った。血の気が引いたり熱くなったり、きっと彼から見れば私の顔は百面相を繰り広げている所だろう。しかし私の動揺なんて微塵にも気にせず、彼は詰め寄った。 「俺がどれだけ心配したか分かるか」 「あ、あの…っ」 「送らせてもくれなかったてめぇのせいで俺は寝不足だ」 「いや、あの…っ」 「どう落とし前つけてくれんだ、あぁ?」 ただのチンピラだ!!―――心の中でどれだけ叫んでもエレンに届くはずがなく、きっと今頃呑気に一人で朝ご飯を食べているのだろう。私も一緒に食べるはずだった、昨晩泣きながら自棄になって作り、一晩寝かせたフレンチトーストを。 だが今は自分の朝ご飯を心配している場合ではない。目の前の恐ろしい男の気が済む方法を、ない頭を使って考えなければならない。せっかくの土曜日だと言うのに、本当についていない。 とりあえず、目の下に濃い隈を作った彼を見ると、顔に書いてあることはただ一つのような気がした。 「う、うちで、寝て行かれ、ます…?」 何でも良いから寝かせろ。そう言われているように感じた。すると彼は大袈裟に舌打ちをし、「それでいい」と言って私をようやく解放した。 ああそうだ、夢の中でも彼は強引な人間だった。駄目だと言っても無理矢理押し通し、無理だと言ってもやれと言う。そして結局、私は逆らえずにそれを受け入れるしかないのだ。けれど裏を返せばそれは彼の我儘で、唯一彼が好きに我儘を言える相手が私だと言うことに、夢の中の私は密かに喜んでいた。他の人では務まらないその役目に、優越感を抱いていたのも事実である。どうしても彼の我儘には弱い夢の中の私は、「仕方ないわね」と笑って最終的に全て許すのだ。 しかし今の私にはそんな余裕はない。なんで、どうしてと疑問ばかりが浮かんでは頭の中でぐるぐると回っている。夢と現実は違うのだとあれだけ昨夜は泣いたと言うのに、彼はまるで、そんな事は関係ないとでも言うように私の領域に入って来る。その癖、確かめさせてはくれない。その隙を作ってくれない。聞くなということなのだろうか。ここまでされてしまうと、もう彼が何も知らないとは思えなくなって来た。 「姉ちゃん…その人、知り合いだったのか…?」 「えっと、あのね…」 「別にどうでも良いだろうが。その内説明する。それより早く休ませろ。俺は一睡もしていない」 「はっはいっ!」 なかなか戻って来ない私を不審に思ったのか、ようやくエレンがキッチンから顔を出す。もっと早くに助けに来て欲しかった。しかしそんなエレンを煩わしいとあしらい、会話を無理矢理切る。とりあえずリビングへ彼を通し、ソファへ横になるよう促した。すると、私の後ろにいたエレンをじっと見たかと思えば。 「おい、俺はこの女にだけ用がある」 さすがにエレンも意味を汲み取ったらしく、無言で何度も頷くと、慌ててリビングを出て行った。そして何やら慌ただしくしたかと思えば、すぐに「いってきます!」と叫んで部屋を出て行く。こんな土曜日の朝から一体どこへと思ったが、今日日二十四時間オープンの店などいくらでもあるし、いざとなればアルミンの家へ転がり込むのだろう。しかし私としては、せめてこの居住空間のどこかにはいて欲しかった。彼の言うとおりに、そこまで忠実にしてくれなくてよかった。「なかなか話の分かるガキだな」と言いながら私を見る彼は、どこからどう見ても極悪人だ。この人のために泣いたり悩んだりしていたのかと思うと自分の神経を疑いたくなる。 そして、彼は遠慮なくソファに横になった。私は傍に寄って行き、すとんとカーペットの上に腰を下ろす。なんとなく、近くにいなければまた怒った声が飛んで来そうな気がしたからだ。しかし、ほんの数秒で彼は眠ってしまったらしく、既に規則的な寝息が聞こえてきており、瞼も開かれることはない。 「なんでなの…」 それは、いろんな問いを含んだ言葉。聞きたいことがたくさんある、けれど何から聞けばいいのか、どう聞けばいいのか分からない。こんなにも横暴なのに、常識外れなのに、それなのにここをエルヴィン先生に聞いてまで探してくれた嬉しさ。 彼は私をどこまでも振り回す。こんなことをされても嫌いになれない。夢の中で強く恋い焦がれてしまった人と出会い、それを少しでも幸せだと感じている。やっと出会えた、という気持ちは、幸せから来るものだったのだ。 なんで―――それは自分にも言えることだ。なんでこんなにもこの人を思ってしまうのだろうか。何をされても拒めずにいるのだろうか。夢の中でも、そして今も。 「なんでなの、リヴァイ…」 私の気持ちも生活も掻き乱す。突然現れては嵐のように物事を掻き回す。それがさも当然だとでも言うように。けれどそれを、嫌だと思えなかったのが私の最大の過ちだ。懐かしいと、そう思ってしまった。彼もそうであればいいと願ってしまった。 私とこの人が同じ気持ちであることを、こんなにもこんなにも強く願う。彼の落ち着いた寝顔を見ながら、私の気持ちはこの人に束縛されているのだと気付いた。夢の中でも、今この瞬間も、私の心臓はこの人のものなのだと。 |
←
 →
→(2013/10/04)