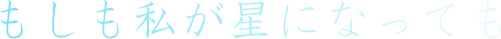
|
エルヴィン先生からのお誘いを受けてから気付いたが、私はお酒が飲めない。はてさてどうするべきか、と考えている内に仕事も終えて、職員駐車場で先生と合流した。エレンにはメールで少し遅くなる旨を伝えると、真っ先に夕飯の心配をされたのだが、冷蔵庫に昨日の残りがあることを伝えると、それっきり返事はない。男の子ってそういうものなのだろうか。少し心配になったが、あまりしつこくメールを送っても鬱陶しがられるだけだろう。エレンが無事、電子レンジを使いこなしてくれることを祈った。後片付けまでは望まない。 「へえ、従兄弟を預かっているんだね。大変じゃないか、この時期の男の子は」 「まあでも、十五歳の割に素直ですし大丈夫です」 「確か、B組の子だったかな…ああ、ここだよ」 連れて来られたお店を見て固まった。所謂、ちょっとお高い感じの、まだ社会人も四年目に足を突っ込んだばかりの私には、それは敷居の高い雰囲気のお店だった。「私、こんなお洒落な所は来たことありません!」と逃げ出す訳には行かないが、思わず後ずさってしまいそうだ。どうしようか、こういうお店のマナーも何も知らない。そして服もいつも通りの通勤スタイルだ。ちょっとお洒落なワンピースが無難だった、と後悔している友人の話を聞いたことがある。 しかし、顔の引き攣る私をよそに、お店へと促すエルヴィン先生。もうどうにでもなれと、縮こまりながらお店に入る。先生の後について行き、通されたテーブルには先客がいた。 「やあ、リヴァイ」 「エルヴィン、お前人を待たせ……」 先日、学校で会った例のメーカーさんだ。私を見るなり、エルヴィン先生への文句が止まる。私たちはお互いを見て顔を引き攣らせた。彼の顔には「なぜここに」と書いてある。恐らく私もそうだろう。 謀られた―――そう思ってエルヴィン先生を見ても遅い。何も知らないとでも言うようににこにこと笑う先生に、私も彼も文句を言えるはずがなく、大人しく三人で席についたのだった。 しかし空気が重い。非常に重い。水を運んで来て去って行くだけの店員になりたいと思うほどに、居た堪れない空気だった。メーカーさんの顔はずっと険しいままで、しかしそれに気付かないふりをするエルヴィン先生。二人を交互に見ても私とは一切目が合わず、もういっそ「用事を思い出しました!」とここで不自然なドタキャンを自己申告したい。 その時、空気の読めない携帯が鳴った。しかしそれは私のものでもメーカーさんのものでもなく、エルヴィン先生のものだった。「ちょっと失礼するよ」と言いながら、その言葉とは裏腹に嬉々として退場するエルヴィン先生。初めて先生のことを恨めしく思った。 「…………」 「…………」 気まずい。何の会話もない。相変わらず彼の表情は険しく、こちらを一切見ない。ここで「決められました?」などと聞くのは空気を読まなさすぎる。さすがにそれは憚られた。そのため、私の視線はメニュー表の同じ所をかれこれ十数回行ったり来たりしている。彼の方から何か切り出してくれないだろうか―――そう願うも、ふと彼を見ると貧乏ゆすりを始めていた。もう逃げたい。 「おい」 「はっはいっ!」 「お前、エルヴィンとはよくこういう所に来るのか」 「え?いや、いえ…」 「エルヴィンとはどういう関係だ」 「職場の上司…ではないですけど…先輩と後輩、ですか?」 「俺に聞くな」 再び沈黙が訪れる。そろそろエルヴィン先生も戻って来て良い頃なのに、一向に現れる気配がない。そわそわして店の中を目だけで見渡すも、その姿は見当たらず、もしかして、嘘だと信じたいが、帰ったなどということがあるのだろうか。いやいやまさか、と首を振るが、なぜかその可能性を捨て切れず血の気が引いて行く。 そんな中、再び沈黙を裂いたのは彼の声だった。 「おいお前」 「はいっ」 「付き合え」 「え!?」 *** 腕を引いて店から連れ出された時、ようやく「付き合えってそういうことか」と察した。帰りの遅いエルヴィン先生を放って、彼と共に飛び出した店。その辺のコンビニに入り、コーヒーを奢ってもらったが、生憎ブラックコーヒーの飲めない私は熱を持った缶で手を温め、弄んでいた。 「今日は迷惑かけたな」 「あなたのせいじゃ…」 「エルヴィンの野郎、何考えてやがる…」 私の言葉などまるで聞いておらず、舌打ちをしてぶつぶつと文句を吐き続ける。しかし、もしこれがエルヴィン先生の謀った流れなら、あまりにチープな気がした。 ひたすら苦笑いをして彼の後をついて行く。お腹は空いたが、彼とこのまま別の店へ、という気分にはなれず、何も言わずとも私たちの足は駅に向かった。駅の手前の交差点まで来て、それまで順調に歩いていた私たちは初めて赤信号に邪魔をされる。 そこでふと、私の思考も立ち止まった。今日を逃せば、次はいつ会えるのだろうかと。また私は勝手に期待をした。この次を、勝手に期待した。彼にしてみれば、今日は彼の方こそいい迷惑で、私なんて会うつもりのなかった人間なのだ。次々と先生への文句が出て来るのは、つまり、そういうことなのだろう。私には“やっと会えた相手”でも、彼がそうだとは限らない。アドレスを知っているくらいで、私は何をどこまで期待するつもりなのだろう。 「わ、私、ここで…」 「あぁ?女一人で返す訳にはいかねぇだろうが」 「いつも一人で帰ってますし、大丈夫です」 「今日もそうだとは限らねぇんだよ」 「あなたにそこまで迷惑をかける訳にはいきません」 「ここまで来りゃもうどこまででも同じだ」 送る、結構です、送るったら送る、いいえ本当に結構です。そんな不毛なやり取りを繰り返す。お言葉に甘えて、とただ一言、そう言えば良いだけなのにそれができない。 私たち二人を置いて、青に変わった信号を渡り始める人々。邪魔だとでも言うように過ぎて行く人たちが肩にぶつかるけれど、私たちはその流れに流されることはなかった。傍から見れば奇妙だろう。こんな往来の真ん中で立ち止まるなど、それこそ迷惑も良い所だ。けれど、このやり取りに決着がつくまでは動けない。最後には、頑固な私に彼が折れた。 「その代わり、家に着いたら連絡入れろよ」 「……」 「返事は」 「…小学生じゃないんですから」 その言いようはあんまりだ、と拗ねてみると、同じようなもんだろ、と言ってくしゃりと頭を撫でる。その手はなぜか酷く懐かしく、ほんの一瞬だったのに胸をぎゅっと絞め付けられた。 知っているのだ。彼の手も、声も、顔も、彼の存在自体を私は知ってしまっている。夢を夢で片付けられないがゆえに、現実に期待をしてしまう。私の名を呼んでくれるのではないかと。何度も夢の中で聞いたあの優しい声音で、私の身体をそっと引き寄せながら、右の耳元で「」と。 そんな都合の良いことがあるはずなく、彼は私の名前を呼ぶことも、それ以上触れることもなく駅の改札で別れた。私が改札を通って、振り返ってみてももう彼の姿はそこにはない。帰路を急ぐ人の群れに流されて、私の目では彼を捉えることができない。重い足でホームに辿り着き、のろのろと歩いて電車の到着を待つ列に並んだ。 なんでこの世で出会ってしまったのだろう。ただの夢であれば良かったのに、なぜ巡り会ってしまったのだろう。夢の中で彼に恋をしている私は紛れもない私で、だから現実の私も夢の中の彼を好きじゃないはずがなくて、現実で彼に会ってしまえば、無条件で惹かれてしまうに決まっている。 全く違う性格ならまだ良かった。なのに、現れた彼は夢の中の彼そのものなのだ。口調も、仕種も、性格も、夢の中と何一つ変わらない。そんな彼を好きになるなという方が無理なのだ。初めて会った瞬間にはもう、私は長い間彼に恋をしている最中だった。 「なんで…っ」 けれど彼もそうとは限らない。だから余計に罪悪感がある。彼にもし恋人がいたら、結婚していたら、その可能性を考えると押し潰されそうになる。アドレスを聞かれたくらい、なんだというのだ。それは決して決定打にはならない。 混み合う電車から降りて、改札を抜けた途端、緊張の糸が切れたように私は泣いた。 好きです、好きなんです―――何度も何度も心の中で繰り返す。でも所詮、私がずっと見て来たのは夢の中の彼だ。彼からすれば私のこの気持ちは気持ち悪いだけかも知れない。それでも止められないこの気持ちは一体どこへ流せばいいのだろう。 今はエレンと二人暮らしの部屋に着いた途端、まるで見計らったかのように彼から届いたメール。「まだ着かねぇのか」と一言だけなのに、嬉しくて嬉しくて、でも悲しくて苦しくて、余計泣けた。 |
←
 →
→(2013/09/18)