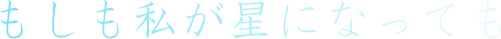
|
もしかしたら、聞き間違いかも知れない。同じ名前の誰かに似ていたのかも知れない。だって、彼はすぐに表情を元に戻し、「いつもありがとうございます」と軽く礼をしたのだ。そして教材の受け取り手続きをして、私一人では重いからと運ぶのを手伝ってくれ、最後に中身の確認まで一緒にしてもらった。 その間、彼は一度も私の方を見ず、私もまた気まずい気持ちでいっぱいだった。彼は違っても、私は意識せざるを得ない。ずっと夢で見ていた彼が目の前にいるのだから。生きて、この世にいるのだから。…そんな私の視線が鬱陶しくて、彼は私を見なかったのかも知れないが。 「全部揃ってるな」 「あ…エルヴィン先生に伝えておきますね」 「連絡先知ってるのか」 「い、いえ…明日…」 その時初めて、じとりと私を見る。確かに噂に聞いていた通り、近寄りがたい容姿だ。目つきは鋭く、にこりともしない。言葉遣いも丁寧ではなく営業とは思えない。そう思い彼のネームを見れば、彼の名前の上には“営業部”とは書かれていなかった。まさか、エルヴィン先生の知人と言うだけで届けに来たのだろうか。 「それじゃあ遅いだろうが」 「は、はいっ、あの、ではお手数ですがあなたから…」 「俺はこの後会社に戻って会議だ」 「ではどうすれば…」 「携帯貸せ、エルヴィンの連絡先を送っておいてやる。事情はお前から話しておけ、いいな」 「は、はあ…」 私の手から携帯を奪い、私のアドレスを彼の携帯に映し、彼の携帯から私の携帯にエルヴィン先生のアドレスが勝手に送信されるまでの一連の動作は鮮やかなものだった。私に決して口を挟ませず、携帯を操作し、私に返却する。呆然とその様子を見ていたが、後から考えると、その間にエルヴィン先生に連絡すれば早かったのではないだろうか。彼は随分と遠回りで面倒な方法を選んだような気がする。それに、せめて私の携帯に直接エルヴィン先生のアドレスを登録すれば良いだけの話ではないか。きびきびとしている割に、かなり無駄のある過程だ。 結局、彼は最後までにこりともせずに帰って行った。最初に微かに私の名前を呟いた以外は、私を呼ぶことはしなかった。やはりあれは聞き間違いだったのだろうか。私に追及することもさせてはくれなかった。彼にはそれだけの隙は一ミリもなかったのだ。 玄関まで彼を見送り、職員室に戻って来ると、「随分恐い人が来る」と私を脅した先生がニヤニヤと笑いながら私を見て来た。 「目を付けられたようだね、先生」 「え?」 「先生、鈍いなあ。彼、必死であなたのアドレス聞き出そうとしてたじゃない」 「え、えっ?えぇ?」 「ほら、やっぱり気付いてない。先生って騙されやすいでしょ」 そう言われて、私は携帯と睨めっこする。アドレス帳の一番新しい登録番号には、彼のものと思しきメールアドレスと番号。しかしどういう訳か名前が登録されておらず空白だ。これでは使い勝手が悪いため、“教材メーカーの人”と書き換える。そして、頼まれていたエルヴィン先生への連絡用メールを作る。けれどその間も彼のことが頭から離れない。 顔や背格好が同じなだけでなく、声も同じだった、喋り方まで同じ。強引さも同じだった。夢の中にだけ住まうはずの彼が目の前に現れたことで、私が動揺しないはずがない。けれど実際にこの目で見て、会って最初に浮かんだ気持ちは、「夢の中だけの人のはずなのに」ではなかった。「やっと会えた」だった。まるで、ずっと前から彼を知っているかのような気持ちだった。私が幼い頃からずっと夢で見ているからではない。もっとずっと昔、私が今の私として生まれるよりも以前に、彼と知り合っていたかのような気持ちなのだ。 「ちょ、ちょっと先生!?」 「あ、あれ…」 ぼろぼろと、涙がこぼれた。嬉しいのか、悲しいのか、色々な感情がないまぜになる。会いたかったはずの人、夢でしか会えなかった人。けれど同時に思い出したのだ。私は決して夢の中で、幸せな恋愛ばかりをしていた訳ではないことを。 |
←
 →
→(2013/08/18)