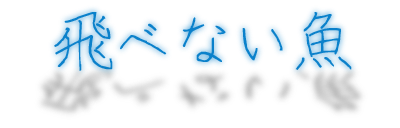
|
しっかりと意識を取り戻したのは、手術をした翌日だった。当日にも目を覚ましたらしいけれど、その時のことは覚えていない。まだ半覚醒だったのかも知れない。両親は心配したらしいけれど、看護師さんによるとそういうものらしかった。涼太くんも来てくれたようだけれど、当然それも覚えていない。だから、ICUから一般病棟に戻って来た今日が、手術後初めての涼太くんとの対面だった。 まだ傷口は痛み、体中が重い。それでも瞼は開けられるし、違和感は残るも声は出せる。まだ酸素マスクを外せないまま、私はかすれた声で涼太くんの名前を呼んだ。 「りょうた、くん…」 「…、ほんとに、良かったっス…っ」 泣きそうな顔をしていた涼太くんが、とうとう本当に泣いてしまった。剥き出しになっている私の手を力強く握り、何度も何度も私の名前を繰り返し呼ぶ。けれどその一つ一つに返事ができるほど体が回復していなくて、私はただ呼吸を繰り返すばかり。がんばったね、と言いながら、額に張り付く私の前髪を避ける涼太くん。そのまま額に触れられて、ようやく戻って来たのだと実感した。また涼太くんに会えたのだと。 冷房が利き過ぎている訳でもないこの部屋で、涼太くんの手はやけにひやりとしていた。私が本当に目覚めるのかどうか、随分不安だったらしい。私が声も出さずに小さく笑うと、まだ涙目の涼太くんもへらりと笑って見せた。そして、ぽつりと零すように言う。負けたんだ、と。 「、俺、負けた」 「…うん」 「約束破って、ごめん」 「…うん」 私の前では、涼太くんは時々泣き虫になる。辛そうな顔も、苦しそうな顔も、悲しそうな顔も、一番見て来たのは私だと思う。その度に私は、根拠もなく「大丈夫だよ」と言って来た。無責任かも知れないけれど、「涼太くんなら大丈夫だよ」という意味を込めて。それに気付いていたのだろうか、私のその言葉を聞くと涼太くんはすぐに笑って見せたのだ。だから、今日だってそう。「だいじょうぶだよ」そう言いながら涼太くんの手から自分の左手をするりと抜いて、代わりにその頭を撫でる。まるで自分の腕じゃないような感覚。まだまともに力も入れられないけれど、何度も何度も、涼太くんの頭を撫でた。大丈夫だよ、がんばったね、お疲れ様―――色んな意味を込めて。そしてそのまま、指でそっと涼太くんの涙を拭う。だいじょうぶ、ともう一回言えば、また涼太くんはいつものように笑った。 「」 「ん」 「は、飛べない魚なんかじゃないよ」 「え……?」 それはいつか、香澄が私の状況を見て揶揄した言葉だった。お姉ちゃんと涼太くんの間でに板挟みになり、あっぷあっぷしている私はまるで窒息しそうな魚だと言ったのだ。私と香澄しか知り得ないその言葉。まさか、香澄から何か聞いたのだろうか。私がずっと、溺れかけの魚だと自分を思っていたということも。涼太くんはそれを知っているような顔をしていたのだ。 優しく微笑んで、べたついた私の頬にそっと触れる。黙ってしまうと、部屋には医療機器が私の心臓の音を伝える無機質な機械音と、酸素マスクの先に繋がれた流量計が立てるぼこぼことした水の音しか聞こえない。ドアという壁一つ隔てた向こうの慌ただしい足音や話し声は、どこかずっと遠くの世界での出来事のように思えた。 「何があっても俺が手を伸ばすし、が水の中にいたいなら俺も飛び込んでと一緒に泳ぐ」 飛べない魚じゃない―――どういう思いで涼太くんがその言葉を口にしたのかは知らない。香澄からどんな話を聞いたのかは知らない。けれどその一言には思いの外、自分で雁字搦めになっていたらしい。涼太くんの言葉を聞いた途端、何かから解放されたような気がした。 ずっと私だけは置いてきぼりで、違う世界にいるのだと言い聞かせていた。そうでなければどうにかなりそうで苦しかったのだ。これでいいのだと、私は後ろをついて行くだけで良いのだと、そう思いながらも半分は納得できていなかったのに。一緒に走りたかった、同じ景色を同じ速度で眺めていたかった。こんな私でも、それを許して欲しかった。傍にいることを疎く思わないで欲しかった。他の誰よりも、涼太くんの隣にいたかったのだ。 「私、いいの…?」 「がいい」 優しく微笑む涼太くんの姿が段々とぼやけて行く。涼太くんの言葉に返す言葉も見つからず、喉の奥がつっかえて声が出ない。そして、涼太くんが私を選んでくれたと言う現実をやっと受け止め、私の胸はいっぱいになった。 欲しかった言葉、何よりも望んだ言葉。こんな私でも、私が良いのだというその言葉が、私は欲しかった。他の誰でもなく、私を一番に見てくれる人、それが涼太くんであればと何度願ったことだろう。 涼太くんが握ってくれているおかげで段々と熱を持ち始めた左手で、私も涼太くんの手を握り返す。思ったよりも力が入らなくて、二人で顔を見合わせて少し笑った。 (きっと……) きっともう、私は溺れることはないのだろう。相変わらず水中を泳ぎ続ける魚だとしても、涼太くんがいつだって私を掬い上げてくれる。手を伸ばしても、もう手の届かない人ではないのだ。追い掛けるだけじゃない、手を繋いで行けるのだ。背伸びをしなくても隣を歩ける日が来ると、夢見た現実はもうすぐそこにある。 たった一人、私は涼太くんと大空を飛びたいと思った。 ←  → →(2013/05/04) |