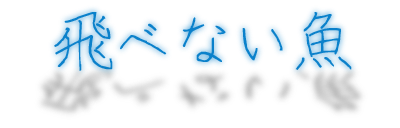
|
大好きな人の腕の中で、溺れかけの魚は一生懸命息をした。泣いて泣いて、困らせて、そうしてようやく呼吸を覚えたのかも知れない。溢れ出す負の感情と、止まらないマイナス言葉。飽きるほど吐いたそれらを、涼太くんはただ頷いて聞いてくれた。私の横に座り、ぎゅっと抱き締めてくれる涼太くん。私がしゃくり上げる度に、ベッドが小さく揺れた。 「手術、いやだよ…」 「うん」 「痛いし、怖いし、」 「うん」 「もし…もし死んじゃったら、もう、会えない…っ」 「…うん」 手術に絶対はない。ほんの僅かな可能性でも、もしものことが起こり得る場合がある。もしそれが自分だったらと、考えるだけで恐怖でおかしくなりそうだ。二度と目を開けることができなかったとしたら―――そんな思いばかりが頭の中を占める。そうするとまた苦しくなって、涼太くんが困った顔をする。大丈夫、と言いながら背中を擦ってくれても、なかなか落ち着くことはできなくて、涼太くんを帰すことができない。明日も学校なのに、部活もあるのに、「もう大丈夫」って笑って見送る、ただそれだけのことができないのだ。不安や恐怖がとめどなく私の口から流れ出る。止めなきゃ、もうやめなきゃ、と思えば思うほど、これまで溜め込んでいたせいか次々と言葉が出て来るのだ。 「それに、手術終わっても、おっきな傷が残っちゃう…っ、そんな身体、だれも…っ」 「、大丈夫だよ」 大きく温かい手が、私の頭をゆっくり撫でる。いい子いい子、とでも言うように、ゆっくりと優しく。そしてもう一度「大丈夫」と言うと、涼太くんは私の身体をそっと離した。やっとまっすぐに見つめることができた涼太くんの目は心配そうで、けれど見たことがないほど穏やかで、私の涙も徐々に止まって行く。不安が消えたわけではないけれど、少しだけ落ち着くことができた。 一体何度、私は好きな人にみっともない姿を見せているのだろう。倒れたり、駄々をこねたり、泣いたり、困らせたり。支えたい、受け止めたいと思う気持ちとはまるで結びつかないようなことを沢山しているのではないだろうか。困らせることで繋ぎとめておきたい、なんて馬鹿なことは考えてない。本当は、できることなら同じスピードで歩きたいのだ。置いて行かれないように、同じ景色を同じ速さで見られるように。それをするためにこの手術は乗り越えるべき山なのだとしたら、それを拒む訳にはいかない。けれど、手術という未知の領域への恐怖を、一体どうして消すことができるだろう。 、と何度目か、涼太くんが私の名を呼ぶと、すっと人差し指で私の胸の真ん中に触れた。 「のここに傷が残ったとしても、俺はから目を逸らしたりしない」 「りょ、た…くん…」 「が好きなんだ」 「え……?」 「好きだから、生きて欲しい」 私と同じくらい、いや、それ以上に苦しそうな顔をして、涼太くんは言う。突然の告白に、私は頭が真っ白になった。さっきまで手術への不安や恐怖でいっぱいだったのに、それが全て吹き飛ぶほどの衝撃だった。そのせいで、まるで通り雨のように私の涙はぴたりと止んでしまった。「本当に…?」震える手を伸ばして涼太くんの頬に触れると、ゆっくりと頷く。お姉ちゃんを追っていた目が、今は私に向けられている。お姉ちゃんに向けられていたそれよりもずっと、穏やかな、けれどまっすぐで射るような目で。いつから、とか、なぜ、とか、そんなことは今は考えられなかった。好きという言葉の大きさを今、身を以って思い知る。負の感情を洗い流してしまうほどの力を持った言葉を受け、ほんの少しだけれど希望が見えた気がした。 「の手術の日、桐皇との試合がある」 「うん…」 「きっと、勝って来るから、だからも病気に負けんな…!」 「うん、うん…!」 再び、その腕に捕えられる。そして思った。もう私は、溺れることはないのではないかと。何度泳ぎ損ねて溺れかけたとしても、きっとこの腕が引き上げてくれるのではないかと。そう思うと、どれだけ深い海の底でも、どんな浅瀬でも、泳ぐのは怖くないのだと思えた。水中で上手く生きていけるような気がした。 それから手術当日まで、涼太くんは時間があれば来てくれた。試合前で大変だろうに、どれだけ遅くなっても絶対に来てくれた。手術当日は来ることができないからと、その分、時間を作ってくれたのだ。手術が近付くほどに私の不安はやはり大きくなったけど、家族と涼太くんがいてくれたお陰で、入院当日のように泣くことはなかった。 *** 「、ちゃんと外で待ってるからね」 「うん」 「がんばって来るんだぞ」 「がんばるのは先生たちでしょ?私はもうまな板の上の鯉だよ」 「気の持ちようって話だ」 当日の朝は、早くからお父さんとお母さんが来てくれた。お姉ちゃんは学校の用事を済ませてからすぐに来てくれるそうだ。出棟までには間に合わせると言っていたけれど、本当に間に合うのやら。時計の針が動く度に、落ち着いてはいれど私の緊張が高まって行くことは否めなかった。それに昨日はさすがになかなか眠れず、少し寝不足気味でもある。体調は万全とは言い難い。そもそも手術を受ける時点で万全なんて有り得ないのだけれど。 もうそろそろ看護師さんが呼びに来る頃だろうか。その時、ばたばたと慌ただしい足音が部屋に近付いて来た。そしてノックもせず部屋に入って来たのは、息を切らしたお姉ちゃんだった。 「よかった…っ、間に合った…!」 「遅いよ、お姉ちゃん」 「ごめんね、これでも急いだんだけど」 来てくれるのは終わってからでも良いと言ったのだけれど、絶対に朝から来るとお姉ちゃんは言い張ったのだ。そしてお姉ちゃんは鞄を置くと、私を頭からぎゅっと抱き締めた。「がんばるのよ」お父さんと同じことを言う。 「あとね、涼太が試合終わったらすぐに来るって」 「別に、落ち着いてからでいいのに…」 「またそんなこと言う」 麻酔が切れて、痛い痛いと泣き喚いていたらどうしよう。今度こそ幻滅されるだろうか。十数年来の幼馴染に今更という気がしないでもないが。それに、もうこの間じゅうぶんみっともない姿は晒した。あれ以上なんて、そうそうないことだろう。 涼太くんに、また会わなければならない。まだ私から「好き」と言っていないのだ。その言葉を言うために、涼太くんからもその言葉を聞くために、ちゃんと帰って来なければならないのだ。負けんな、という涼太くんの言葉を思い出す。何よりも、その言葉は無敵に思えた。前を向けるような気がした。本当は怖いけれど、それに立ち向かえるような、打ち勝てるような、そんな気がする。 「…負けないよ」 呼びに来た看護師さんに連れられて、手術室へ向かう。今頃涼太くんは試合会場に向かっているのだろうか。今日の夕方には、試合の報告が聞けるだろうか。それを聞くために、がんばろうと思った。もう、私は溺れない。 ←  → →(2013/04/11) |