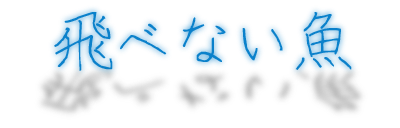
|
いつだって私は、人より何歩も遅れて歩く。実際の歩行でも、気持ちの面でもそうだ。同じ速さで歩けないことを今更どうこう言っても仕方ないと思っていた。諦めるしかない現実を受け入れなければと思っていた。それなら誰にも迷惑をかけないように、誰にも心配させないように、自分でできることは全て自分でしなければと、そう思っていた。けれど結局それができなくて、いつだって誰かに気を遣わせて来た。「あいつは病弱だ」「それを理由に気を引こうとしている」「大袈裟だ」と―――何度も何度も、色んなことを言われて来た。だからひた隠しにして来たのに、それも泡にかえる。 自分の歩幅に誰かを合わさせることは酷く気が引けて、いっそ置いて行って欲しいと思うことさえあった。けれど実際置いてきぼりにされると寂しくて泣きそうになって、そんな時、煩わしさなんて微塵にも感じさせずに待っていてくれたのは涼太くんだった。私が転んでも、遅れても、追いつくまで待っていてくれた涼太くん。けれど涼太くんは私なんかを待っていていい人じゃない。もっと先を行く人たちと競り合って走って行かなければならない人だ。だから、もう涼太くんが私を待たなくて良いように、私は一人で歩く必要がある。大丈夫だよって、自分にも涼太くんにも言い聞かせながら。 (それが、“無理する”ってことだったんだなあ…) 今回もそうだ。大丈夫、まだ耐えられる、そんな私の気持ちとは逆に、身体が悲鳴を上げていた。学校で倒れるなんて、もう二度としたくなかったのに。走り続ける涼太くんを支えられるくらい、強くなりたいと思っていたのに。 「!」 次にちゃんと目を開けられるのだろうか。その時、私の口は自由が利くのだろうか。手も自由に動くのだろうか、ちゃんと一人で立つことができるのだろうか。…息苦しさで意識が朦朧とする中、最後に涼太くんの声が聞こえた気がした。 *** 『こんどの遠足、楽しみだな!』 『…うん』 『、どうした?』 『わたし、遠足いけないの…』 小学校に入りたての頃はまだ様々な制限があった。多少、両親が過保護なところもあったけれど、注意することに越したことはないと自覚していた。体育も、遠足も、社会見学も、周りは普通にできることが私にはできない。何度も何度も泣いて、その度に両親を困らせて、それでも私の身体が劇的に良くなるなんてことはない。それに気付くのは案外早く、それと共に諦めを覚えた。 涼太くんに「わたしはいけない」「わたしはできない」と自己申告したことも一度や二度ではない。そして何回目かの「行けない」という言葉を聞いた涼太くんは、とうとうとんでもないことを言い出した。 『が行けないなら、おれも行かない!』 『だ…だめだよ…!』 『ががまんしてるんだ!おれもがまんする!』 『涼太くんが行かないとみんな楽しくないよ!』 『おれだってが行かなかったらたのしくない!』 結局私は、その遠足に行けることにはならなかったけど、遠足の日の朝でさえ、涼太くんはぶすっとした顔のままでいた。 ずっと、涼太くんは優しかった。私を置いて行こうだなんてしたことがなかった。壁を作っていたのは私の方で、手を離そうとしたのは私の方だった。けれど幼馴染という特別な枠を捨てきることができなくて、あまつさえ涼太くんが心配してくれることを嬉しいだなんて思ったりした。 罰が当たったのだろうか。いつまでもこの心地の良い関係にしがみついていたから、神様が怒ったのかも知れない。飛べない魚は飛べないまま、水底で暮していればよかったのだ。太陽をも掴もうとする彼を、水中から腕を出して掴んでいようなど、誰が許してくれると言うのだろう。 『がいないせいで、楽しくなかったぞ』 遠足から帰ってもまだ不機嫌そうな涼太くんを見て、嬉しいやら悲しいやら、幼い私は泣きじゃくった。 *** それは、懐かしく、温かい夢だった。夢の余韻に浸ったまま、目覚めた私に告げられたのはシビアな現実。途端に冷めて行く頭でなんとかこの状況を飲み込もうとしたけれど、今回ばかりはそうも行かなかった。 「治ってない?」 「手術適応になります。それ以外、治療法はありません」 学校で倒れ、運ばれたのはかかりつけの病院ではなく、高校から一番近い病院だった。そこであらゆる検査をしてもらった所、私の心臓は治りきっていないことが判明したのだ。そしてそのまま入院、手術することとなった。私はただ、先生の話に頷くだけで、手術の説明も何もかも、頭に入ってなど来ない。ただの作業のように、手術の同意書にサインをした。 身体が限界を訴えていることに気付きながら、我慢をしていた。食欲が出なかったことも、浮腫んでいたことも、すぐ息切れすることも、隠そうとしていた。次の受診日までまだ耐えられると、そう信じたかった。あと少しだけ、あともう少しだけと、そう願ったことを叶えることはこんなにも難しいことなのだろうか。ただ、普通に学校に行きたい。普通の生活をしたい。涼太くんの隣にいたい。涼太くんに特別な誰かができるまでは、私が一番近くにいたい。決して贅沢を言っている訳ではないのに、どうして。 頭は真っ白、心は空っぽになる。決して難しい手術ではないと先生は言ってくれた。不幸中の幸いか、ここはその手の手術に長けた医師がいるらしいのだ。けれど、先生や看護師さんが、両親とお姉ちゃんがどんな言葉をかけてくれても、もう私は聞こえなかった。怖い、嫌だ、逃げたい、なんで私が―――私の中の負の感情が一斉に溢れ出して来るようだ。怖くて怖くて、泣きたくなる。夜になり、一人になると余計不安は増幅した。 「う、ぅ……っ」 怖いって誰に言えばいいの、誰に言えば分かってくれるの。…そんなことばかり思いながらベッドの上で蹲っていると、コンコン、と控えめにドアがノックされた。両親かお姉ちゃんか、何か忘れ物でもしたのだろうか。泣いていただなんて知られたくなくて、ドアに背を向けたままきつく両目を擦って涙を拭く。そっとドアが開かれたのを感じて「忘れもの?」と聞いたが、この鼻声では泣いていたことはバレバレだろう。また心配をかけてしまう、と嫌になる。 しかし、なかなか返事が来ない。不思議に思って後ろを見ると、そこには涼太くんがいた。私からは直接、入院したことを涼太くんには言っていない。だとすると、お姉ちゃんが言ったのだろうか。それとも、お母さんが涼太くんのお母さんに言って、そこから涼太くんに伝わったのか。いや、経緯なんてはどうでも良い。もうすぐ消灯時間だと言うのに、部活帰りにわざわざ寄ってくれたことに動揺を隠せなかった。けれど私以上に涼太くんは驚愕しているようだ。ドアを開けて突っ立ったまま、入ってこようとしない。その表情は固まっていた。 「…入って、いいよ」 「うん…」 消していた部屋の電気をつけ、涼太くんはゆっくりと私の傍までやって来る。そしてベッドサイドにあった椅子に座った。 「姉と山下から、連絡があって、全部聞いた」 「うん」 「そんなに、悪かったんスか…?」 「……うん」 手術をしなければならないほど、という意味なのだろう。険しい顔で涼太くんは私をじっと見た。気まずくて、その視線から逃れようと私は俯く。布団をぎゅっと握って、再びこぼれそうになった涙を必死で堪えた。 もし、ここで私が怖いと言ったなら、手術を受けたくないと言ったなら、涼太くんはどんな顔をするのだろう。怒るだろうか、悲しむだろうか。それとも何も言わないのだろうか。本当は誰かに言ってしまいたい。隠して来た本音を全て吐き出してしまいたい。今にも心が破裂してしまいそうなのだ。本当はとっくに、心の許容量を超えていた。もっと早くに誰かに甘えれば良かったのかも知れない。そうすれば、今になってこんなに苦しまなくて済んだかも知れないし、迷わなかったかも知れない。けれど、本音のマイナス部分を涼太くんに告げるのは、涼太くんを前にしてもなお悩む。本当はこんなにも駄目な私を涼太くんには見られたくなかった。 「あ、だ、大丈夫だよ!そんなに難しい手術じゃないらしいし、先生の腕も良いらしいし」 「、違うだろ」 「それに私、まだやりたいこといっぱいあるし、高校にだって入ったばっかなんだから、そんな滅多なこと…」 「縁起でもないこと言うな!」 「っ分からないじゃない!死ぬかも知れないじゃん!」 「バカか!」 ぱんっと、小気味良い音と共に、私の左頬に衝撃が走る。それに加えて、勢いよく倒れた丸椅子が大きな音を立てた。しかしすぐに、私は手加減なしに涼太くんに抱き締められた。呼吸も苦しいほどに、その腕の中に閉じ込められる。 「言いたいのは、そんなことじゃないだろ…!」 「りょうたく……」 「怖いとか、嫌だとか、ちゃんと言えよ…っ」 涼太くんの方が泣きそうではないか。私よりよほど辛そうにそんなことを言うものだから、つられて私も再び泣きたくなる。「」と優しく名前を呼ばれると、それが引き金となった。今度こそじわじわと目に涙が溜まり、やがて大雨のように両目から流れ出す。 もう消灯時間も過ぎているのに、私の雨はなかなか止めることができなかった。 ←  → →(2013/04/08) |