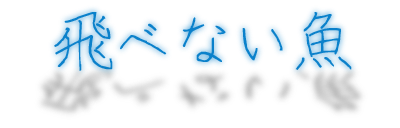
|
昨日の今日で、涼太くんとは非常に気まずかった。生憎、喧嘩なんて一瞬だったものの、あんなことがあった以上、一層涼太くんを意識してしまう。これまでは何とか持ち堪えていたし、幼馴染というラインを守っていたから、緊張するような場面に出くわさなかったのだ。一番近い幼馴染と、彼女と言うポジションとでは何もかもが違う。だから守って来た境界線だったのに、あっけなく踏み込まれてしまってはもう私だけで解決できる問題ではなくなってしまうのだ。 それでも、気まずいからと言って接触を避けていては、この先ずっと避け続けることになる。それだけは回避したいことだった。だから、平静を装って涼太くんと会話するしかない。 「おはよう、」 「お…おはよう。今日、遅いんだね」 「試合の後だから朝練はないんスよ」 遭遇した、というよりも、待ち伏せされていたと言った方が正しいだろう。家の門を出ると、隣の黄瀬家の前に涼太くんが立っていたのだ。いつもと変わらない様子で話す涼太くんにほっとする反面、私のぎこちなさを反省する。 いつもは、朝練のあるお姉ちゃんや涼太くんは私よりもずっと早くに登校する。本当はそれくらいの時間の方が電車も空いているし私の体にも負担はかからないのだけれど、お姉ちゃんと涼太くんは二人で登校することもしばしばあったため、その時間帯は避けて来たのだ。二人が話している所を見たくないという、たったそれだけの理由で。部活も引退になるお姉ちゃんは、それでも今日は早くに出て行った。残された私はいつも通りに出て来たという訳だ。入学して以来、涼太くんと登校なんてしたことがない私は、周りの景色すら違って見える。駅までの道のりもあっという間、満員電車もあっという間だった。 しかし、私には慣れた登校ルートでも涼太くんには違ったらしい。学校から最寄りの駅に着く頃には、涼太くんはすっかりぐったりしていた。 「いつもこんな満員電車で通ってるっスか…」 「慣れだよ」 「ダメっスよ!あんな満員電車、体に悪いっス!も俺と同じ時間にすればいいのに…」 「うーん…」 曖昧に笑って返すと、涼太くんは足を止めた。私も合わせて止まり、涼太くんを振り返る。「もう、姉も朝練ないし」―――そう言いながら、私を窺って見せた。それは、お姉ちゃんがいなくて一緒に登校する人がいなくなる寂しさからなのか、私が気まずい思いをすることはないという意味なのか、そこまでは図りかねる。もしかするとどちらもなのかも知れないが、そこまで言及する気にはなれなかった。しかし、「考えておくね」と答えれば、ぱっと嬉しそうに笑った涼太くんを見ると、さほど深い意味はないのだろうか。 そうして再び歩き出したものの、まだ隣から視線を感じる。私も隣を歩く涼太くんを見上げると、彼は何か難しい顔をしていた。そして言いにくそうにぽつりと零す。 「……、夜更かしでもしたっスか?」 「なんで?」 「なんか、浮腫んでる気がする」 「え…」 「まあ、は元々細いから気にならないっスよ」 そう言って涼太くんはくしゃりと私の頭を撫でた。何でもないことのように言う涼太くん。けれど、それは私にとって大きな意味を持っていた。 何となく、気付いてはいたのだ。気のせいだと思っていた、思っていたかったのだ。涼太くんは多分、顔のことを言ったのだろうけどそれだけじゃない。顔よりも、下肢の方がそれは顕著だった。最初は歩き過ぎただけだと思った。だから足を挙上して寝てみたり、マッサージをしてみたりした。けれど元に戻らないのだ。これは、太ったとか、そういう話じゃない。あと少し、あと少しと見過ごして来たせいなのか。まさか、顔を見て指摘されるなんて。 「…?」 「あ、ううん、なんでもない。もうすぐ受診日だな、て」 「まだ、いっぱい薬飲んでるんスか?」 「仕方ないよ」 昔のように頻繁には行かなくて良くなった病院。今では一、二カ月に一回程度だ。でも、調子が良いと思っているとすぐに体調を崩す。だから気をつけて来たつもりだった。ストレスを溜めないように、負担をかけないように、様々なことに注意して来たつもりだった。できるだけ周りの子と同じような生活を送れるように、取り除けるマイナス要素は取り除いたつもりだったのに。 「、何かあったらすぐ言うっスよ」 「心配性だなあ、涼太くんも」 「当たり前っスよ、なんだから」 なにそれ、と笑いながらも泣きたくなる。実際、涼太くんが何をどこまで理解しているかは知らない。単に、幼い頃に弱かった体をまだ引きずっているだけと思っているかも知れないし、それよりは重症だと思っているのかも知れない。本当のことは何も知らない。それはそうだ、私だって何も言わなかったのだから。 けれど、こういう時にどうすれば良いのか分からない。自分の身体に少しでも異変が起こった時、どのレベルで相談をすれば良いのか分からないのだ。まだ耐えられると思えば限界で、もう限界だと思えば何ともないと言われ、自分でも自分の身体が分からない。その不安は、誰に向ければ良いのかさえ未だに分からないのだ。両親にも、お姉ちゃんにも、香澄にも言えずにいる。もちろん、涼太くんにも。 「は抱え込み過ぎなんスよ。まあ、そうさせた一人は俺かも知れないっスけど…」 「大丈夫だよ。今度ちゃんと検査してもらって来るし」 「絶対、無理しちゃダメっスよ」 「うん」 いつもは嬉しいと思う涼太くんの言葉も、笑顔も、今は苦しい。言ってしまいたい、私の身体は今でも爆弾を抱えているということを。本当はこのままずっと普通の生活ができるだなんて思っていないことを。このまま大人になって、働いて、結婚して、子どもを産んで―――そんな人生を歩めるとは思っていないことを。 けれど、そんなことを涼太くんに言ってどうするのだ。ただの幼馴染に言うようなことなのだろうか。こんな重い話を背負わせて良いとは、とてもじゃないけれど思えないのだ。たとえ、涼太くんがどれだけ心配してくれていて、どれだけ優しくても。私は心配されるよりも、涼太くんが疲れた時に受け止められる存在でありたい。そのためには、まだこの身体が音を上げる訳にはいかないのだ。 「涼太くんも、無理しないでね」 本当に、もっと家に近い学校に通わなければならなくなるかも知れない。学校にすら行けなくなるかも知れない。…そうやって私は、いつだっていろんな可能性を考える。それも、プラスではなくマイナスの方向にだ。でも、そうでもしないと本当にそうなった時に辛いのだ。期待すればするほど、その望みが切られた時の辛さも倍になる。 だから、私が望むことなんていつだってほんの少しだけ、叶えられる程度。涼太くんを支える誰かが現れるまでは、私だけが涼太くんの全てを受け入れていたい。弱い所も、狡い所も、矛盾した所も、私だけが知っていたいと願うのだ。 ←  → →(2013/03/13) |