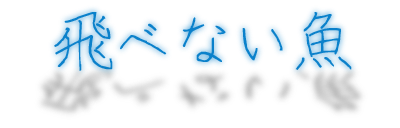
|
私と涼太くんは、それこそ保育園児の頃からの仲だ。当時は一緒にお昼寝をしたり、手を繋いで歩いたこともあった。けれど、男女でいつまでもそんな仲ではいられない。だから、こんなにも涼太くんにしっかり触れたことなんてなかった。年齢が一つ上がる度に私たちの関係の形も、ほんの少しずつ変わって、距離感も在り方も変わって来た。そんな風に離れて行くばかりの中で、こうやって涼太くんに頼られるなんて夢にも見なかった。気の利く言葉をかけられる私じゃない。失恋の痛みを知っているからこそ、簡単に励ましたり慰めたりなんてできない。 ずっと、お姉ちゃんに彼氏がいることを隠してきた私も同罪だろうに、なんで私まで胸が痛いのだろう。 『…段々ややこしくなってるんじゃないの、の周り』 「うん…」 香澄と別れた後のことを話すため、私は涼太くんの家から帰ってすぐに彼女に電話した。一通り聞き終えた電話の向こうの香澄が溜め息をつく。 胸が痛い。どこで何をどうすれば良かったのだろうと、考えても考えても答えなんて出て来てくれやしない。遅かれ早かれ涼太くんは事実を知ることになっていたのだし、それが今日だっただけ。けれど、なぜ今日だったのか。笑って「おめでとう」と言うはずだったのに、私はその一言を一度も口にすることのないまま帰って来てしまった。 けれどその実、私は少しほっとしていた。これでもう涼太くんがお姉ちゃんを追い掛けることはないんじゃないかと、涼太くんはお姉ちゃんを諦めるんじゃないかと。自分の性格の悪さに嫌気がさす。 『でも私、黄瀬はが好きなんだと思ってた』 「まさか。ここ数年ずっとお姉ちゃんだよ」 『それって本当に恋だった?』 「え…?」 『きっと黄瀬は、さんよりもを失うショックの方が大きいはずだよ』 だって、いつも傍にいたのはでしょ―――そう続けられた香澄の言葉に、私は声もあげずに泣いた。嬉しかったのだ、そんな風に言ってくれる人がいて。涼太くんにとってはお姉ちゃんは遠い存在で、いつも背中を追い続けている人で、決してすぐ傍にいる人ではなかった。毎日がつまらないと言っていた時も、バスケを始めて笑顔が増えた時も、また段々変わって行った時も、どんな時だって私の方がお姉ちゃんよりも近くにいた。けれど、距離ではないのだ。どれだけ私がいろんな涼太くんを知っていても、涼太くんの一番にはなれない。お姉ちゃんを追い掛けなくなった所で、他に魅力的な女の子が現れたら、今度はその子を追うのだろう。涼太くんの目は、いつまでも私は向かない。いつだって、涼太くんにとって私は“そこにいるのが当たり前な幼馴染”でしかない。だから、気休めだとしても第三者である香澄からそんな言葉をもらえたことで、少しの救いになった。 「明日…」 『うん』 「明日、言うの。インターハイ出場おめでとうって」 『うん』 「試合、また一緒に観に行ってくれる?」 『いいよ、行こう』 応援することをやめられるはずがない。涼太くんが活躍すればするほど遠くなって行っても、やがて手が届かなくなってしまったとしても、ここまで好きになった人から目を背けられるはずがない。 私だけが応援に行っても嬉しいと、そう言ってくれた涼太くんの言葉を信じて、私は次の試合も観に行くことを決めた。 *** 「涼太、何してんの?」 「姉…」 すぐ隣だが、を送り届けた後、彼女の部屋の電気が点くまで家の家の前で見ていた。すると、不審に思ったのか姉がと入れ替わりで出て来たのだ。正直、まだ顔を見るのはキツイものがある。さっきまでと話してた、と返したが、上手く笑えていたかどうかは分からない。けれど、さっきまでがいてくれたからか、話すことくらいは大丈夫そうだ。姉とのこともしか知らないから、ずっと話を聞いて来てくれていたんだよなあ、と、の部屋にようやく電気がついたのを確認しながら思い返す。 「が涼太の試合観に行きたいって言い出した時はびっくりしちゃった」 「そうなんスか?」 「あの子、絶対行きたがらなかったもの」 「そ、それはそれでショックっス…」 「心臓に響くんだって。大声、歓声、ドリブルの音、走る音…私たちは何気なく思ってるものでも、にはストレスになっちゃう。分かってるからずっと避けてたの」 「心臓…」 が病弱なのは、うちの家族でも知っていることだ。病名までは難しくて覚えてないけれど、そう、心臓の病気だったと思う。けれど、年々は活動範囲も広がったし、体育のような激しい運動はできないけれど、それ以外ならおよそ自分たちと変わらない生活を送るようになっていた。いや、そう思っていた。「違うんだよ」「違う?」「普通に過ごしているように見えるように、が選んで行ったの」悲しそうに笑いながら、姉もの部屋を見上げる。カーテンはもちろん閉ざされているが、時々揺れていることから彼女は窓に凭れているのだろうか。…俺は、姉の言葉の意味を分かりかねて首を傾げた。 「何て言うのかな…私たちが多少、“大丈夫でしょう”と思うことも、あの子は慎重に考えて切り捨てて来たの。夏冬はほとんど外に出なかったりね。血圧上がりそうな映画を観なかったり…むしろ、映画館に行かなかったり」 「そう…だったんスか…」 「神経質だと思うでしょ?でもちょっとしたことがあの子の恐怖なの」 体の中に爆弾を抱えている、と姉は表現した。そして、それを決して誰にも打ち明けたことがないとも。は、姉にも抱える恐怖を話したことはないのだと言う。ただ、姉は可愛い妹のことはお見通しらしく、全て見聞きしたかのように話した。年も近く、いっそ過保護なほどに見守って来た妹のことを、姉は誰よりも理解しているのだろう。だから、に無理に話すようにも言わなかった。 いつも朗らかに笑う、困った時には手を差し伸べてくれた、何があっても目を逸らさずにいてくれた。…そうか、自分の傍にはいつだって誰よりも一番、がいてくれたのだ。けれど俺はそうじゃなかった。いつもを見ていた訳ではない。いつでも自分のことばかりで、が体が弱いことを知っていつつも、本当には理解できていなかったのだ。それなのにが俺の傍にいてくれた理由は、荒んだ時にも見離さずに微笑みかけてくれた理由は、それは果たして幼馴染だからというだけなのだろうか。 「そんなあの子が、やっと一歩外に踏み出した。それは他でもない、涼太のお陰だよ」 「俺は何も…」 「だから、私が言うのも変な話だけど、を見ていてやってよ」 姉でさえ背伸びをしなければ届かない頭に、めいいっぱい手を伸ばしてくしゃくしゃと乱暴に撫でる。は姉よりもずっと小さい。この間、体育館でシュートを教えた時にも、その小ささに改めて驚いたくらいだ。あの細い腕には大き過ぎるボールを構え、しかし彼女の小さな体からは想像できない豪快さで振りかぶり、一生懸命リングにボールを当てて見せたのだった。その後見せた嬉しそうな笑顔を、俺の八つ当たりにさえも、「いつだって応援していた」と泣きながら言ってくれたを思い出すと、さっきの自分を殴ってやりたい気持ちに駆られる。 俺が隣にいるべきなのは、俺が守ってやるべきなのは、俺が追い掛けるべきなのは、目の前にいる姉じゃない。ずっと、誰よりも自分のことを考えてくれただったのだ。 ←  → →(2013/03/04) |