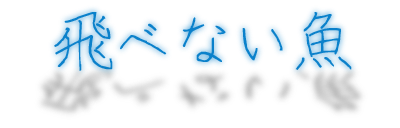
|
インターハイ予選後半で、お姉ちゃんの所属する女子バレー部は敗れた。三年間全力で取り組んだお姉ちゃんの部活生活は終わってしまった。エースとしてメンバーの前では決して涙を見せなかったお姉ちゃんも、帰宅すると一人、部屋で泣いていたらしい。翌朝、目が赤く腫れていた。けれど、「これで受験に打ち込める」とどこか清々しい笑顔でお姉ちゃんは言った。 一方、涼太くんたち男子バスケ部は順調にインターハイへの駒を進めていた。あれよあれよと言う間に勝ち続け、あっという間にインターハイ出場を決めた。運動部に所属したことのない私は、正直に言うとインターハイと言われてもピンと来ない。応援はしていたが、実際はどこか遠い世界のことのように感じていた。香澄と一緒に試合を観に行ったが、その感覚は寧ろ増した。いつもは近い涼太くんがまるで別人のようで、遠い世界の人のように感じたのだ。皆の言う“黄瀬くん”がそこにいた。あれが、“みんなの黄瀬くん”なんだと思った。 「黄瀬って、意外と普通だけど実はすごいヤツだったんだ」 「…私も、初めて見たの」 「試合?」 「うん」 試合が終わり、帰りを急ぐ人たちによる混雑のピークが過ぎてから、私と香澄は体育館を出た。お姉ちゃんは彼氏と観に来る約束をしていたらしく、私は結局、香澄と観に来ていたのだ。決勝ともなると観客の数は溢れかえっており、立ち見の観客もいたくらいだ。そんな中、舞い上がっていた私はかなり早くに会場に着いたため、香澄と共に比較的前の座席で観戦することができた。あの人ごみや歓声の中にいることは少し疲れたが、それ以上に頭の中は真っ白に近かった。涼太くんとの壁を、まざまざと見せつけられたような気がして。 「なーに落ち込んでんの。笑っておめでとうって言ってあげなきゃ。次は全国大会だよ?」 とん、と香澄は私の背中を押す。いきなりのことに前へよろけると、「!」という叫び声と共に誰かに受け止められた。 「涼太くん…?」 「気分悪そうだって山下が…」 「え?」 振り返ると、楽しそうに笑いながら携帯をひらひらと振る香澄。…いつの間にか二人は繋がっていたらしい。 ちょっと疲れただけ、と笑って見せても涼太くんは信じてくれず、部員のみんながいるだろうに、私と帰るなどと言い出す。何度も何度も拒否したけれど、こういう時の涼太くんは非常に頑固なのだ。全く私の話など聞き入れず、さっさと部長さんに「先に帰っていて下さい」という旨のメールを送ってしまった。香澄も香澄で“私の手柄”とでも言いたそうににやりと笑う。仕方なく、私は香澄と涼太くんに挟まれて帰ることになった。 香澄が「あんた、見直したわ」だの、涼太くんが「俺をなんだと思っていたんスか」だの、私を挟んで会話をする。それに時々相槌を打ち、時々笑いながらついて行く。香澄とは方向が逆のため駅で別れたが、その後は涼太くんと二人きりだ。疲れた私の歩く速さに合わせてくれたせいで、家に着くのが少し遅れてしまったけれど、嫌な顔一つしない涼太くん。妙な緊張のせいで私が無口になってしまったが、疲労のせいだと思い込んでくれるだろう。 ようやく門の前まで来た所で、言い忘れていた大切な言葉を言おうと顔を上げた。その時、涼太くんの視線が私にないことに気付く。嫌な予感がしながらも、その視線の先をゆっくりと辿った。 「あれ?、涼太と一緒だったの?」 「おっ、あの黄瀬涼太くん?」 「そうそう。近所の幼馴染」 お姉ちゃんだけなら良かった。そこには、お姉ちゃんだけでなく彼氏の宮間さんが一緒にいたのだ。何度か家に来たことがあるから顔も知っているし話したこともある。けれど、なぜかこれまではタイミング良く涼太くんと鉢合わせすることがなかった。それなのに、よりによって今日、こんな日になぜ。 どくんどくんと、心臓が嫌な音を鳴らす。楽しくおしゃべりを続ける二人を前に、私は顔が強張るのを感じた。景色が白黒に変わって行く。涼太くんの方を見ることができない。涼太くんもまた、一言も言葉を発さずにいた。 「あ、俺はもう帰るよ。お邪魔しました、ちゃん」 「いえ…お気を付けて」 「また来てねー」 「おう」 私のこんな気まずさなんて知らず、二人は爽やかに挨拶をして別れた。「さて、と…」宮間さんを見送ると、お姉ちゃんは涼太くんに向き直った。そして、「インターハイ出場おめでとう!」と場違いで空気の読めない祝福をする。私はまだ、涼太くんの顔を見ることができない。寧ろ、私の目線は下へ下へと落ちて行くばかり。やがて、私と、涼太くんと、お姉ちゃんの足だけを目に映していた。涼太くんはいつも通りに振る舞おうとしているのか、けれどいつも以上のハイテンションとなり、それは違和感を孕んだ。 空回りする。歯車が噛み合わずどんどんずれて行く。何かが外れた、そう思った。もう私の耳には二人の会話など入って来ない。今、涼太くんはどんな気持ちでお姉ちゃんと話をしているのだろうか―――それを考えると動悸と冷や汗が止まらない。早く、早く終われと強く願っていると、突然涼太くんは私の肩にぽん、と手を置く。 「あ、ちょっとと二人で話したいんスけど」 「そっかそっか。じゃあ家に入ってるね」 「お姉……!」 「たまにはゆっくり喋っておいで」 伸ばした右手が虚しく宙を掻く。体が動かなかったのは、涼太くんが痛いほどの力で私の肩を押さえていたからだった。 涼太くんから何を言われるのか容易に想像がついて、私はまたも涼太くんを振り返ることができない。痛い、と声を上げることもできず、涼太くんはありったけの力で私の肩を掴む。とうとう顔を歪める私の耳に、絞り出すような涼太くんの声が届いた。 「なんで…っ」 「りょ…た、く…」 「なんで言ってくれなかったんだよ!!」 ぐいっと引っ張られて無理矢理涼太くんの方を向かされる。両肩を掴まれて詰め寄られても、私は何も言うことができなかった。 だって、あれだけお姉ちゃんを好きな涼太くんに、どうやってこの現実を伝えればよかったのだろう。私が涼太くんを思って来たのと同じように、涼太くんがお姉ちゃんをずっと見ていたことを知っている。それなのに、第三者である私がどうやって口を挟むことができただろう。好きな人が自分を見ていないことの辛さを、私はよく知っている。まさに、目の前の人物がそうだったのだから。涼太くんは私をよく心配してくれる、けれど私を“そういう”対象として見てくれたことは一度だってなかった。お姉ちゃんもそうだ、涼太くんをそんな風に見たことは一度だってなかった。いつだって家で涼太くんのことを話す時は、まるで弟を自慢する姉のような口ぶりだったのだ。 そんなことを、私がどうやって涼太くんに言えたと言うのだろう。 「応援してるなんて嘘だったのかよ」 「ちが…っ!」 「ずっと、馬鹿な奴だって思ってたのかよ!」 「違う!!」 泣き叫び、私はめいいっぱいの力で涼太くんの腕を振り切る。 「わ、私だって、好きな人がいるの!その人は私を見てないって、分かってる、だから、涼太くんの気持ちが、分からないわけ、ないじゃない…!」 「……」 途切れ途切れになりながら、それでも必死に伝えた。馬鹿にしてたことなんて一度もない。応援する気持ちにも嘘はなかった。どれだけ辛くても、苦しくても、涼太くんがふられれば良いなんて考えたことは一度もなかった。自然と私にその目を向けて欲しいと願ったことはあれど、涼太くんの不幸を願うはずがないではないか。 涼太くんに怒ったことのない私が声を荒げたことに余程驚いたのか、ついさっきまで怖い顔をしていた涼太くんは、一瞬で間抜けな顔になった。 「私はいつだって応援してた、してたよぉ…っ」 「…………」 「お姉ちゃんのことだけじゃない、バスケのことも、試合のことも、なんだって、いつだって私は…!」 「……そう、だったスね」 くしゃりと頭を撫でられる。けれどそれは、いつもと比べ物にならないほど弱弱しくて、つい熱くなってしまった私も一気に冷めて行く。 そんな顔は卑怯だと思った。そんな悲しそうな顔で、悲しそうに笑われたら、喉まで出かかった乱暴な言葉なんて全て引っ込んでしまう。代わりに、悲しまないでという言葉が出そうになる。私よりずっと大きな涼太くんが、とても小さく見えた。小さく肩を震わせ、必死に何かを耐えている。 涼太くんは私の手を掴み、黙り込んだまますぐ隣の自宅へと速足で向かう。足がもつれそうになる私など気にせず玄関の内側まで通すと、私をドアに追いやった。まだ何か言われるのだろうか―――少し怯えながら涼太くんを見上げると、今にも泣きそうな顔をしている。私の肩に頭を乗せると、その重みでずるずると玄関に座り込む体勢になってしまった。 「涼太くん?」 「、ちょっとだけ」 「…うん」 縋るように私を抱き締める涼太くんの背中に、私もそっと腕を回す。さっきまでコートの中であんなにも強かった涼太くんが、小さく肩を震わせている。私より体も気持ちもずっとずっと強いと思っていた彼を、初めて守ってあげたいと思った。 ←  → →(2013/02/12) |