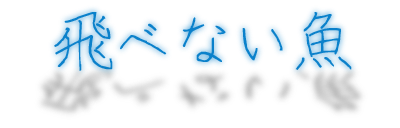
|
その日の掃除は体育館だった。あの広い体育館をひたすらモップ掛けする、想像しただけで気の遠くなる作業だ。誰も進んでやりたがらないだろう。けれど私は少し楽しみでもあった。なぜなら、体育館は体育館でも、いつも涼太くんたちバスケ部が使っている体育館だからだ。人混みが苦手な私は、バスケ部を見に行ったことがない。何せ涼太くんが在籍しているのだ、いつも海常生の女の子たちは熱心に見学に行っている。あまりその女の子たちに愛想よく涼太くんを見るのが好きではないことも、見学に行かない理由の一つだった。部活中の涼太くんに興味がない訳ではないのだ。だから、涼太くんが使っていると言う体育館に一歩足を踏み入れられると言うだけで私はどきどきしていた。 しかし、そんな浮かれた気持ちで体育館に行ったものの、誰も来ない。教室のある棟からは遠い上に、先生の監督のない掃除に、真面目に来る生徒はあまりいないのだ。私も不純な動機―――本音を従えて入るものの、一応掃除と言う建前はある。寧ろ、それがなければバスケ部の使う体育館に入る勇気などない。 (仕方ないか…) 体育館倉庫を開けると鍵をブレザーのポケットにしまい、体育館用の幅の広いモップを取り出す。倉庫は埃っぽく、私は極力呼吸を抑えてすぐに出て来た。そして体育館の奥の方からモップ掛けをしようと意気込んだ時だった。キィ、と控えめに体育館の扉が開く。なんと、部活ジャージに着替えた涼太くんが入って来たのだ。遠くてもあの明るい髪色と背の高さで分かる。何より、涼太くんを私が見間違うはずがないのだ。 「掃除当番ってっスか!?てか、なんで一人!?」 入口から私に向かって叫ぶ。反響してやや聞き取りにくいが、しっかりと聞こえた。私も両手でメガホンを作り、涼太くんに返事を返す。 「誰も来ないの!」 「サボリじゃないスか!」 慌てて涼太くんは走って私に駆け寄る。そしてモップを奪い取り、「掃除なんて俺らが部活終わりにするからいっスよ!」と言う。そんな訳にはいかない、と言いたかったが、一人では終わりそうにないだだっ広い体育館を今一度見渡すと、絶望感すら押し寄せて来る。私は大人しく倉庫にモップを返却し、代わりに二人で体育館の小窓や扉を全て開けて回った。 まるで夢みたいだ、涼太くんと二人で体育館にいるなんて。きっとその内他の部員たちも来るからそう長くはいられないだろうけど、ちゃんと体育館にやってきて良かったと心底思った。なんだかんだ、私はやはり涼太くんが好きなのだ。 「スポーツ、楽しいだろうね」 「そうっスか?」 「だって最近、涼太くん特に楽しそう」 「ってほんと、よく見てるっスねー」 それは涼太くんだからだ。中学の時、バスケを始めてすぐは楽しそうだった涼太くん。それから暫くするとまたつまらなさそうになり、やがてバスケの話をすることを嫌がるようになった。けれど、また最近自ら部活の話をしてくれる。先日、試合を見に来て欲しいと言われたことだってそうだ。結局あれはお姉ちゃんを誘って欲しいということだったけれど、これまで一度だってそんなことを頼まれたことはなかった。尤も、私はスポーツの大会のような人が多くて大声の挙がる場所は好まないため、誘われなかっただけかも知れないが。それにしたって涼太くんは変わった。私は別に、バスケをする涼太くんに惹かれた訳じゃない。それでもやっぱりバスケをしている涼太くんはかっこいいのだと思う。しっかり見たことはない、少し通りがかりに見掛けるだとか、帰りにその辺のコートででシュート練習をしているのを見掛けた程度だけれど。 私にとっては遥か高くにあるように見えるバスケットゴールを見上げる。涼太くんでは簡単に手が届いてしまうらしい。ジャンプ力のあるお姉ちゃんも、もしかしたら跳べば届くのだろうか。私では到底無理だ。じっとゴールを見つめていると、涼太くんは「ちょっと待ってるっス」と言って倉庫へ走り出す。そして出て来た涼太くんの手には、バスケットボールが一つあった。 「もやってみるっスか?」 「む、無理だよ!バレーのパス練習でも息切れしちゃうんだよ!?」 「大丈夫っスよ。走らせたりしないし」 「私、ノーコンだし…」 「フォローするっスから」 ちょっとシュートするだけっスよ。笑って私の手を引くと、名前も知らない線の上に立たされ、ボールを持たされる。涼太くんがいつも軽々と操って見せるボールは、私が持つと重い。両手で持ったまま、私は頭の上から思いっきりゴールに向かって投げて見せた。しかし当然、リングに掠ることすらせず、壁にぶつかって跳ね返った。それを見た涼太くんが肩を震わせて笑いを堪えている。 「だ、だから言ったのに!笑わないでよ!」 「い、いや…っ、、意外と、豪快だなって…っ、はは…!」 「涼太くんってば!」 返って来たボールを拾い、私に軽くパスをする。よろけると、また涼太くんは笑った。大袈裟なリアクションではないのだ、本当に、それほどに私は運動らしい運動をせずにここまで来たのだから。 私が機嫌を損ねると、涼太くんは笑いを堪えて涙目になりながらも、私の手を取る。 「右手はここで、左手はこう。ほら、もう一回」 「う、うん…」 「力ずくで投げなくて良いっスよ」 言われた通り、今度は前へではなく放物線を描くように上へと投げる。すると今度はちゃんとボールがリングに当たった。「涼太くん見た!?」はしゃぎながら彼を振り返ると、また笑っていた。いつも軽々とシュートを決めて見せる涼太くんからすれば、入らない事の方が余程不思議なのだろう。しかし腕力も握力も平均点以下の私にとっては、リングに当たったそれすらおおごとなのである。また口を尖らせると、「良かったスね」と言いながら私の頭を撫でる。面白がっているのか、馬鹿にしているのか。悪気はないのだろうけど、良い気分ではない。 涼太くんを無視して、転がって行ったボールを拾いに行く。そしてその場所から適当に涼太くんに向けてボールを放った。するとそれを見事にキャッチし、数回ドリブルしてゴールに近付くと、綺麗に片手でリングにボールをくぐらせて見せる。その流れるような動作に見惚れる。きれいだ、と思った。上手い人がゴールを決めるとこんなにもきれいなものなのかと、初めて知った。 「試合、見に来たくなったっスか?」 「…ちょっとだけ」 「予選の最初の方ならそんなにうるさくないっスよ」 言いながら、またその場で数回ボールをついて、シュートする。どこからでも入るんだ、と涼太くんにとっては当り前であろうことに感心する。私なんて、さっき涼太くんからボールをかなり手加減をしたパスされただけで、手がこんなにもびりびりしている。まだ痺れているみたいに感じる。 もし涼太くんが本当にその言葉を私にだけ言ってくれたなら、どれほど嬉しかっただろう。私が試合を観に行くということは、その場にはお姉ちゃんも含まれるということだ。涼太くんがそれを期待していることくらい、私には分かっている。いつだって意識してしまうのはお姉ちゃんと言う存在。私も含め、誰も決して越えることのできない壁。中学の頃から部内屈指のジャンプ力を誇っていたお姉ちゃん。そんなお姉ちゃんに、私がいくら跳ねた所で敵うはずがない。気持ちだけは、こんなにも涼太くんを全速力で追い掛けているのに。 「私だけが観に行っても、嬉しい?」 「え?」 「な…なんでもない!」 「嬉しいっスよ」 「へ…」 嬉しいっス、と、もう一度繰り返す。笑いながら、私にそう言う。そのたった一言で私は堪らない気持ちになる。ぎゅうっと胸が締め付けられて、苦しくて、もっともっと涼太くんを好きになってしまう。私をこんなにも一喜一憂させるのは涼太くんしかいない。涼太くんはそれを分かって言っているのだろうか。たったそれだけで、私がどんなことさえ許せてしまうことも、受け入れてしまうことも。 やがて、体育館にぞろぞろとバスケ部員たちがやって来る。私は涼太くんになんの返事もできないまま、「じゃあ、帰るね!」とだけ言い残し、その場を去った。 もう、この胸が苦しいから痛いのか、嬉しいから痛いのかすら分からない。恋をすればするほど麻痺して行く心なんて、これまで少しも知らなかった。 ←  → →(2013/02/05) |