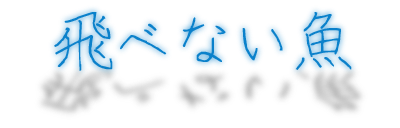
|
倒れた原因はただの疲れだった。これまですぐ近くの学校に通っていたのに、急に電車通学となり、それが思いの外負担となっていたらしい。かかりつけの病院で色々な検査を受けたが特にこれまでと変わりはなく、すぐに帰宅できることとなった。しかし今回の件で通学に対し私以上に不安を抱いてしまった母が、毎日車で送迎すると言い出したのだ。これ以上家族に迷惑をかけたくない、心配をかけたくないと思うのに、そう思えば思うほど上手くいかない。 私は大きく溜め息をつき、部屋のベッドにダイブした。その時、静かな部屋に携帯のバイブが鳴り響く。そういえば全く携帯を見ていなかったと思い、私は鞄から携帯を取り出す。すると、涼太くんから十件近くのメールと着信があった。内容はどれも「ごめん」という謝罪か「大丈夫か」という心配ばかり。けれど私が欲しいのはそんな言葉じゃない。私が涼太くんに望んでいるのはそんな言葉じゃないのに。 (大丈夫だよって、一言……) その一言だけで良いのに。そんな気持ちすら抑えて、「もう大丈夫だから」とだけ打ったメールを涼太くんに返す。もうそろそろ部活の時間だから、きっと返事は来ないだろう。そう思いまた携帯を鞄へ投げた。 随分疲れてしまった。耐えて来た疲れや見えないふりをしていたストレスが一気に圧し掛かって来たようだ。どんどん重みを増す瞼が完全に閉ざされようとしたその時、部屋の扉が叩かれる。お母さんがそっと部屋を覗いて私を窺うように声をかけて来た。 「、山下香澄ちゃんと言う子が来ているのだけど…」 「香澄が?」 友達だよ、と言うとすぐに香澄を通してくれた。どうやら担任からプリントを数枚託されたらしい。私の家は涼太くんから聞いたのだと彼女は言った。 「明日でも良いのに」 「これは口実。に会いたかったんだってば。で、大丈夫なの?」 「うん、また明日から学校に行くよ」 「体弱いんだって、黄瀬が言ってたけど」 「昔ね。もう治ってるよ」 「…なら良いけど」 長居しちゃ悪いから、と言って香澄はすぐに帰ってしまった。どこか腑に落ちないような顔をしていたが、私が疲れていることを察してくれたのだろう。私も本当は色々話も聞いてもらいたかったけれど、明日また学校で聞いてもらおう。涼太くんにもお姉ちゃんにも言えない話、相談したことのないこと。もうずっとこの体がコンプレックスだったことや、だから余計涼太くんやお姉ちゃんとの距離を感じることを。 そして、もしものことを考える。もし、私の体が健康で、他の子たちと何も変わりなく生活ができていたら。お姉ちゃんと同じように外を走り回れて、スポーツもできる体だったら。そうすれば、こんなにも自分に自信をなくすことはないのだろうか。内気で籠ってしまうような性格じゃなかったのだろうか。涼太くんも私を見てくれたのだろうか。同じように全国大会を目指すと言う志を持ち、互いに憧れ、思い合う関係になれたのだろうか。 (それは違うか) 私はであってではない、たったその一つの現実だけが、この恋を実らなくさせているのだから。 そしてとうとう、私は眠りの淵に落ちて行った。 *** 翌朝、学校に着くといつだったかのように昇降口で涼太くんと鉢合わせした。涼太くんは朝練終わりだろうか、タオルを握り、足元には鞄が無造作に置かれていた。昨日あんな別れ方をしてしまったため、少々気まずい。しかし素通りする訳にも行かず、私は極力いつもどおりに笑いながら「おはよう、涼太くん」と声をかける。すると涼太くんははっとして私を振り返る。随分思いつめているようで、私が着いたことに気付かなかったらしい。 「昨日は…」 「昨日はごめんね、調子悪くて心にもないこと言っちゃったの」 「そう…なんスか…?」 涼太くんが何かを言い出す前に、私から言葉を被せる。もう心配をかけるのは嫌だ。迷惑だと思われたくない。私が弱い所を見せたせいで、涼太くんが私に弱い所を見せてくれなくなるのは嫌だ。…そんな気持ちから、口からはすらすらと出まかせが飛び出す。いつからこんなにも嘘をつくのが上手くなったのだろう。いくら人をよく見ている涼太くんでも、私の作り笑いは見抜くことができないようだ。私はひたすら仮面を被り続けた。 「もう何ともないよ。ごめんね」 「が謝ることないっス!俺こそ、がしんどかったの気付かなくて申し訳なかったっス…」 項垂れる涼太くんに手を伸ばし、いつも私にしてくれるみたいに頭を撫でてやる。すると、驚いたのか目を見開いて私を見た。 「しばらくお母さんが送り迎えすることになったけど、学校、変わらなくて良いって」 「よ…良かったっス!これからもと同じ学校っスね!」 「もちろんだよ」 私以上に喜びながら、私の両手をぎゅっと握ってぶんぶんと振った。通り過ぎて行く他の生徒たちは不思議そうに私たちを見ているが、涼太くんは止めようとしない。私は苦笑いしながら「痛いよ」と言うとようやく離してくれた。すると、部活の友人だろうか先輩だろうか、バスケ部のジャージを肩に引っ掛けた男子生徒が通りがかりに「おい黄瀬、朝からナンパかよ」とからかって行く。それを全力で否定する涼太くん。そんな、ただの男子高校生な涼太くんのやり取りを見て微笑ましく思う。幼馴染とはいえ、私は涼太くんの友人関係などあまり知らないため、そういった現場を見るのは新鮮でもあった。 「なに笑ってんスか、…」 「仲良いなあと思って」 「別に、フツーっスよ」 「そっか」 「あ、教室まで送る」 「…うん」 いいよ、と断りそうになったけれど、それを飲み込んで首を縦に振る。なんとなく今日は甘えておこうと思ったのだ。涼太くんにとっては、私の教室を経由することは遠回りになってしまうけれど。 他愛ない話をしていると、あっという間に教室に着く。今日はお姉ちゃんの話は出なかったな、とほっとしていると、別れ際に涼太くんは私を引き止めた。 「、倒れた次の日にこんなこと言うのもアレなんスけど…」 「な、なに?」 急に改まった態度をとる涼太くんに、私は何か嫌な予感がした。 「今度、試合見に来てくれないっスか?」 「それは…」 「山下とか誘っても良いし…いや、の体調が良かったらの話っスけど」 「お姉ちゃん」 「う」 「でしょ?」 「…はなんでもお見通しっスか」 自分で誘えば良いのに、と、私だけではだめなのか、という気持ちがぎゅうっと心を締め付ける。いや、私の知らない所で事が進んでしまうと、それはそれで辛いけれど。涼太くんは、こんなことを私にしか頼めないってことを知っていて私に頼んで来る。悪気はないのだ、私が涼太くんを好きなように、涼太くんもお姉ちゃんを好きなだけ。だから必死で見てもらいたくて、がんばっているだけ。分かっていて、どうやって涼太くんのお願いを無碍にすることができるだろうか。 「試合の日、決まったら教えて。お姉ちゃんの予定聞いておくから」 「、ありがとっス!」 こうして私は、どんどん自分の首を自分で絞めて行く。涼太くんの頼みを振り切って、自分の我儘を通す理由がない。あるとすれば、私が涼太くんを好きだと言うことくらい。香澄だったら「自分で直接聞け」と言いそうだけど、もうずっと体に染みついた涼太くんを甘やかす癖も直すことができず、ますます悪循環にはまって行く。 一部始終を見ていたらしい香澄は、涼太くんが去って行くと「あんたらしいわ」と言って見せた。苦笑で返すことしかできない私。きっと、香澄にももどかしい思いをさせているのだろうと思う。行動に踏み切ることができない私にも、私の気持ちに気付かない涼太くんにも。 「…コンプレックスなの、今でもちょっとしたことで息があがっちゃうような体が」 「バレー部レギュラーの姉に、バスケ部エースの幼馴染ねぇ…。私がだったら、劣等感抱きまくって二人を避けてると思う」 「そうできたら良かったのにね。高校まで追い掛けちゃった」 「あんた強いよ」 また、ぽんぽんと私の背中を叩いて、教室の中へと足を促す。悲しいやら、嬉しいやら、泣きたい気持ちになる。 嫌だって、言ってしまいたい。お姉ちゃんなんて誘いたくないって、言ってしまいたい。言えたらどんなに楽だろう。自分がこんなに苦しくなるのに、それでも、あんな風に笑う涼太くんを見てしまうと、困らせることは何かとてつもなく大きな罪のように思えて、私は我儘一つ言えなくなる。だから、「一回くらい困らせてみれば」という香澄の助言にも、素直に頷くことはできなかった。 「できないよ、好きだから」 「…そっか」 私が我慢すれば丸く収まるのだと、その時、私は愚かなほどに信じていた。 ←  → →(2013/02/05) |