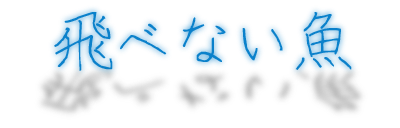
|
涼太くんの両親が揃って不在の日、涼太くんはいつもうちに夕飯を食べに来る。今日が偶然その日だったのだが、幸か不幸か、今日はお姉ちゃんが部活で遅くなる日だった。残念そうにする涼太くん、けれど内心ほっとしてしまう自分に気付いて私は唇を噛んだ。嫌な子でいたくない、けれど現実を目の当たりにする度に私はどんどん理想とかけ離れて行く。 「またいつでも来れば良いよ。お姉ちゃん、最後の大会前で気合い入ってるんだ」 「そっスね。がんばれって伝えといてくれる?」 「もちろん。もしオフだったら試合観に行ってあげてね」 良い子でいなきゃ、良い子でいなきゃ―――そう思えば思うほど、自分の本心とは真逆の言葉ばかりが口をついて出る。お姉ちゃんの話題以外ではこんなにも辛いことはないのに、最近は会うとお姉ちゃんの話題しか出なくて、私の苦しさは限界をとうに越えていた。 違うのに、本当はもっと他のことを話したいのに。そうすれば無理して笑わなくて済むのに。…けれど、私と話していて涼太くんが一番楽しそうなのは、お姉ちゃんの話をしている時なのだ。それ以外の話を聞いてくれない訳じゃない、けれど反応も食いつきも違う、それを見てしまうと、少しでも涼太くんに笑っていて欲しいと思う私は、お姉ちゃんの話を出さない訳にはいかない。自己犠牲なんて好きでやっている訳ではないのに。 「その時はも一緒に行くっス」 「…うん」 悪気のない涼太くんの笑顔に、私はいつも息苦しくなるのだ。 *** 「損な性格してるって言われない?」 すっかり仲良くなった私と香澄は、並んで体育を見学していた。今日はバレーだったのだが、パス練習を暫くしていると息切れを起こし、すぐに見学になってしまったのだ。合わせるかのように香澄も「お腹痛いです」などと嘘か本当か理由を述べて、先に座り込んでいた私の隣に腰を下ろした。そして昨日の夕飯のことを話したのだが、ばっさりと斬られてしまった。 「私だったら“お姉ちゃんの話はしないで!”て啖呵切ってそのまま告白する」 「男前だね…」 「当たって砕けろがポリシーだからね」 彼女の勇気が半分でも私にあれば、同じことができたのかも知れない。けれど実際は彼女の五分の一の勇気も覚悟も持っていない私は、もう何年も前から変化はない。告白すれば代わりに失うものが必ずある。それが、良好な関係を築いて来た良い幼馴染というポジションだ。対価はあまりに大きく、それを失う怖さから逃げられない私は、上手な作り笑いを覚えてしまった。 私にだけ弱音を吐く涼太くん。私にだけ涙を見せる涼太くん。私にだけ“毎日がつまらない”と言った涼太くん。他の女の子にも、お姉ちゃんにも、友達にさえ見せない所を私だけが知っている。それなのになぜ、涼太くんの特別な一人にはなれないのだろうと、歯痒い思いをしたのは一度や二度ではない。神様は残酷だと、私は溜め息をついた。 「って魚みたいだね」 「魚?」 「あっぷあっぷしてる。今の状況って言う池の中から飛び出せなくて、窒息しそうな魚」 「…………」 彼女の的確な言葉に、私は言葉を失った。 やがて授業が終わり、更衣室から教室へ向かう途中で涼太くんを見付ける。どうやら涼太くんは移動教室らしく、手には化学の教科書を持っているのが見えた。すると涼太くんも私に気付き、ぱっと笑って手を振って来る。私も控えめに手を振ると、口パクで「おつかれ」と言われた。どうやら友人に誤解されたようで、涼太くんは何やらからかわれながら化学室の方へ行ってしまった。 そんな些細なことで堪らなくなる。きゅんと切なく疼く胸、緩む口元を必死で隠した。「付き合ってないのが不思議でしょ」と呟く香澄。その一言は嬉しくもあり、また胸に深く突き刺さった。今もまた、窒息しそうになっている。向けられた笑顔も、かけられた言葉も、全てがこの胸を占めて止まない。嬉しくもあり、幸せでもあり、けれど苦しくもある複雑な気持ちを、まだこの先コントロールして行かなければならないのかと思うと気が遠くなる。香澄の言うとおり、告白してしまえば楽なのだろうか。もし振られてしまえば、涼太くんと言う太陽に水中から手を伸ばそうとすることを諦められるのだろうか。 「…水底に潜っちゃうくらいなら、窒息しかけてる方が良いのかも知れない」 「そっか」 その方がらしいわ。苦笑いしながら香澄は私の背中を二、三度叩く。諦めてしまって楽になれることより、涼太くんを思ったまま苦しむ方を選ぶ、その愚かさは分かっている。自ら茨の道に突入しなくても、と香澄も本当は思っているのだろう。けれど、一年や二年どころではない、もっと長い年数を掛けて育って来た片思いは、たとえ息のしやすくなる生活をちらつかされた所で手放せるものではなくなっている。そう、最早この息苦しさすら生活の一部、彼を好きでいることも生活の一部なのだ。たとえば、この体と長年付き合って来たのと同じように、涼太くんへの気持ちとも上手く付き合わなければならない。そう、私は選んだのだ。 「、大丈夫?」 「え?」 「顔色悪いけど」 「ちょっと、」 「気分が悪い」と言いかけた瞬間、くらりと眩暈がする。隣に立っていた香澄の腕を掴もうとして、掴めなくて、片手が虚しく宙を掻く。そして目の前が真っ暗になり、私の意識はそこで途切れた。 *** 右手に人の温かさを感じて、私は目を覚ました。首を巡らせると、私の手を握りながら壁に凭れている涼太くんがいた。どうやら座りながら居眠りしているようだ。りょうたくん、とからからに渇いた口で名前を呼べば、女の子が羨ましがるような長い睫毛に縁取られた瞼が僅かに震える。少し右手に力を入れてみると、今度こそ涼太くんは目を覚まし、椅子から立ち上がって私の手を両手で握った。 「心配したんスよ!」 「…ごめんね」 「さっき山下が俺に言いに来てくれたっス」 「そっか」 「のお母さんにも連絡したから、もう迎えに来てくれるっスよ」 私はあの後すぐに保健室へ運ばれ、まるまる一時間眠っていたらしい。その間、ずっと涼太くんは付き添っていてくれたのだと言う。情けなくて、泣きたくなって、私は涼太くんから顔を逸らした。 こんな風に倒れるなんて、ここ二、三年は全くなかった。順調に行っていると思ったのに、そうは行かない自分の体に歯痒くなる。お姉ちゃんのようにスポーツをしたいだなんて欲張りは言わない、ただ普通に学校に通いたいだけなのに、どうしてそれすら自分の体に阻まれなくてはいけないのだろうか。体育が制限されてしまっても良い、電車で通って、授業を受けて、友達とおしゃべりをして、たまに帰りに寄り道をして―――そんな生活すら私には負担となってしまうのだろうか。 「…転校しなさいって言われたら」 「何言ってんスか」 「もっと近い学校があるでしょって言われたら、やっぱり電車通学なんて無理だって言われたら、」 「どうしたんスか、らしくないっスよ」 私らしいって何。そんな言葉を飲み込んで、滲みそうになった涙をごしごしと袖口で擦る。私の後ろ向きな言葉で気まずい空気が流れた時、タイミング良くお母さんが迎えに来てくれた。鞄を持って来てくれた香澄も同行しているようだ。ゆっくりと起きて眩暈がないことを確認すると、ベッドサイドに設置されている籠からジャケットを取り、着用する。「涼太くんありがとうね」というお母さんの声をどこか遠くに聞きながら、私はちらりと涼太くんの方を見る。至極心配そうな表情の彼を振り切って、私は保健室を後にした。 ←  → →(2013/02/03) |