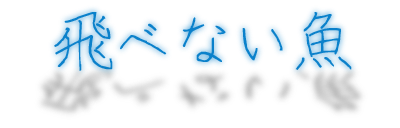
|
世間が騒ぐモデル・黄瀬涼太に、私はあまり興味がなかった。だから涼太くんの載っている雑誌はほとんど見たことがないし、小さい頃から一緒に育った私にとっては、本当に涼太くんがモデルなんてしているのかと未だに不思議に思うくらいだ。バスケに関しても同じで、確かに昔から器用にあれこれと卒なくこなしていたが、まさか全国レベルの選手になっているだなんて想像もしなかった。…そんな私の話を聞いて、中学の友人は「じゃあ黄瀬くんのどこがいいの?」と聞いて来たことがあった。多分、涼太くんのファンを名乗る女の子たちは、涼太くんの本当の姿を知らない。目立つ容姿やバスケをしている姿ではない、悲しいかな私はお姉ちゃんを好きな涼太くんを好きになったのだ。 「最近、とはいつも“久し振り”から始まるっスね」 「クラスも違うもんね。それに涼太くんは部活も忙しいみたいだし」 「そうなんスよ、毎日へとへとっス…。姉ともなかなか会わないんスよねえ」 お姉ちゃんの名前を出して涼太くんは項垂れた。涼太くんもお姉ちゃんも遅くまで部活をしており、終わる時間もまちまちのためなかなか出会わないらしい。練習に使用している体育館も違い、入学式以来校内では全く見掛けていないのだという。そういう私も、涼太くんと帰りを共にするのはかなり久しぶりだった。私は任命された委員会の会議で遅くなり、涼太くんは部活がいつもより早く終わったため、校門で遭遇したのだ。 嬉しい鉢合わせに高鳴る胸。部活はどうか、どんな先輩がいるのか、クラスはどんな雰囲気なのか、色々と聞きたいことがあるのに、きっと思いのままに聞いたら尋問のようになってしまう。私は自然と、口数が減ってしまった。けれど話題の豊富な涼太くんは私の聞きたいことを言わずとも話してくれる。帝光も練習はかなりハードだったが、高校もかなりハードであること。声が大きい先輩がいたり、女の子好きな先輩がいたり、キャプテンにはいつも蹴られていること。クラスはまあまあ馴染んだ気がするということ。 「でも結構大変っスよ…」 「そりゃあ、あの黄瀬涼太くんが同じ学校にいると思えばみんな騒ぎたくもなるよ」 「そのお陰で素でいられないのがしんどい」 「じゃあ気を遣わなくていいうちに遊びにおいでよ。そうしたら、うん、…お姉ちゃんもいるし」 「…ありがとっス、」 またくしゃりと私の頭を撫でた。 世間が作り上げた“黄瀬涼太”でいなければならない時間は、生活の大半を占める。そうやって演じられている“黄瀬涼太”にうっかり惚れてしまう女の子は少なくない。涼太くんは実は人をよく見ているから、相手が本当の自分を見ているのかどうかなんてすぐ見抜ける。最初は軽い気持ちで始めたと言っていたモデル業も、有名になればなるほど悩みは増え、窮屈らしい。それでも、楽しんでいる所は楽しんでいるようではあるが。 時々こうして涼太くんの不満や弱音を聞くのは私の役目だった。なら何でも話せる、と言ってくれたことは嬉しくもあり、その内容に心を痛めることもある。例えばお姉ちゃんのことを相談される時だ。それでも、自分の首を締めながらも、涼太くんがこんな話をできるのは私だけなのだと言う優越に浸っている私は、本当に性格が悪いと思う。涼太くんの弱い所を私だけが知っている、だなんて。 そんな私の気持ちなど知らない涼太くんは、心配そうな表情で私の顔を覗き込む。 「こそ、体は大丈夫っスか?」 「今のところはね。でもちょっと無理しちゃうとすぐ電車酔いしちゃうみたい」 「気をつけなきゃだめっスよ。昔みたいに倒れたらと思うと心配で仕方ないっスから」 「うん、ありがとう」 「それじゃ、また学校で」 家の前で別れる時、何度も何度も涼太くんの手を掴もうとした。涼太くんの手を掴んで、引き止めて、好きだと伝えたかった。けれど私では駄目なのだ。どれだけお姉ちゃんと顔がそっくりでも、姉妹であっても、私はお姉ちゃんではないのだから。涼太くんが私の好意を受け取ってくれる可能性は万に一つもない。それを知りながらなお、涼太くんに好きだと言うだけの勇気は私は持っていなかった。私だけに弱音を吐く涼太くん、私だけを心配してくれる涼太くん―――そんな当たり前の日常を失うことが、私はとても怖かった。この関係が壊れてしまうくらいなら、好きだなんて言わなければいい。 「またね、涼太くん」 だから笑って手を振るだけ。また明日、と。 *** 「ねえねえ、さんってさ、黄瀬と付き合ってんの?」 話したこともない前の席のクラスメートに、突然聞かれた。聞かれることは珍しくはなかったが、休み時間、突如私を振り向いて前置きも何もなくその質問をぶつけられたことに驚いたのだ。 「ち、違う、けど…」 「そうなの?仲良いから付き合ってんのかと思った。あ、私、山下香澄ね。よろしく」 「よろしく、山下さん…」 「香澄でいいよ。私もって呼ぶし」 別段、敵意を向けられている訳ではないらしい。彼女は純粋に疑問に思っただけのようで、それ以上は何も涼太くんについて言及はして来なかった。しかし始まったのは尋問のような私への質問攻めであった。「どこの中学出身?」に始まり、趣味だとか、好きな食べ物だとか、休日は何をしているかだとか、雑誌の質問コーナーのように次々と彼女の口から質問が飛び出して来る。あまりの食いつきようにやや引き気味になっていると、「ごめんごめん」と軽く謝られた。 「この際だから色々聞こうと思って」 「はあ…」 「黄瀬の彼女でそれを鼻にかけてすごい澄ましてんのかと勘違いしてたんだ。なんだ、ってただの人見知り?」 「う、うん」 そんな勘違いをされたのは初めてだ。香澄の想像力に感心しながら、私は苦笑いをした。 私も大概教室では影が薄く浮いている方だが、香澄も休み時間に席からあまり離れない人間だ。人見知りと言うわけではなさそうだが、あの女子の輪の中に入って行くのが面倒なタイプの人間なのだろうか。ともあれ、入学してからまともにクラスメートと話すのは初めてで、私はかなりどきどきしていた。…長いまつげに、気にならない程度に施された薄いメイク、可愛いシュシュでまとめられた髪―――正直にいえば、香澄は私なんて気にとめないような子なのではないかと思っていた。全く違うタイプの人間だから、一人でいることに気付いていても私から話しかけることはせずにいた。 その時、右側にある廊下側の窓が何の前触れもなくいきなり開けられた。これにはさすがに香澄も驚いたようで、私たちは椅子から落ちそうになってしまった。その犯人は、最初に香澄との話題に上がった涼太くんだった。 「!……と、お友達?どうも、黄瀬涼太っス」 「ども、山下です」 「どうしたの、涼太くん」 「……現代文の教科書を…」 「借りに来たの?」 「そっス」 机の引き出しから一際分厚い現代文の教科書を取り出す。それを手渡すと、まるでご褒美をもらった犬のように喜んで見せた。中学の時にもよく予習を見せてくれと頼まれたことを思い出す。部活で大変なことを知っている私は、いけないことと分かりつつも涼太くんの頼みを断れないでいたのだ。 そんな私と涼太くんのやり取りを黙って見ていた香澄が、そこで初めて口を挟んだ。 「ねえ、なんでなの?」 「へ?」 「黄瀬クンならわざわざ進学コースの棟まで来なくても借りれる人いるんじゃない?」 「なんか嫌味に聞こえるんスけど…なに、この子と友達なんスか…?」 今にも見えない火花が飛びそうな雰囲気を緩和しようとするも、なぜか涼太くんと香澄はお互い睨み合っている。最初に「黄瀬」と言っていたことにしろ、涼太くんへの聞き方にしろ、確かに涼太くんに良い印象を持っているようには見えない。幼馴染だという私の説明にも「幼馴染、ふうん…」と答えたのみ。そしてまるで品定めするかのように涼太くんをじとりと見た。 この凍りそうな空気を和ませる術など持たない私は、ひたすら香澄と涼太くんを交互に見遣るのみ。いつまで続くのだろうかと冷や汗をかいていたが、やがて予鈴が鳴りそうになると、涼太くんは慌てて「また返しに来るっス!」と言って去って行く。廊下に顔を出してその背中を見送り、私は元通り窓を閉めた。ほんの数分のはずなのに、やけに二人が睨み合ってる時間は長く感じた。ふう、と小さく溜め息をつくと香澄はぽつりと零す。 「黄瀬て案外普通だね」 「う、うん」 「今の黄瀬の方が良いよ。私、雑誌とか出てる黄瀬のアイドルスマイル好きじゃない」 「随分はっきり言うね…」 「で、は今の黄瀬が好きなんでしょ?」 ぴし、と私は固まった。ぎこちない笑顔のまま返事をできずにいると、彼女はにやりと笑う。「私の勘は鋭いの」と言うと、丁度次の授業の先生が入って来たため、香澄は不敵な笑みを残して前を向いてしまう。初めて見抜かれた恋心に動揺した私は、それ以降授業に身が入らなかった。 ←  → →(2013/01/30) |