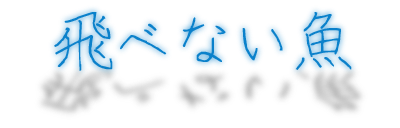
|
ずっと小さい頃から、お姉ちゃんは私の憧れだった。私にないものばかりを持っていて、いつだって輝いていた。そんな姉が自慢であり、誇りであり、コンプレックスでもあった。それともう一人、幼馴染の涼太くん。お姉ちゃんと涼太くんは私にはできない色々なことができた。例えばスポーツだ。なぜだか、大きな病気一つしたことない両親や姉とは違い、私は幼い頃から病気がちだった。すぐに熱を出して保育園や小学校を休んでおり、遠足もあまり行った記憶がない。それが修学旅行ともなると大変で、家族みんなが気が気でなかったという。どうして私だけが、という思いは最初こそあったものの、そういうものなのだと受け入れるしかないことを悟った私は、早々に様々なことを諦めざるを得なかった。この体とは一生付き合って行かなければならないのだから嘆いても仕方ないのだと、ポジティブなのかネガティブなのか分からない考えを持つようになったのだ。 病院を定期的に受診はしているものの、命に関わるほど私の病弱具合は酷くなかったため、無事に私も高校進学を果たした。それがここ、海常高校だ。 「なら絶対、似合うと思ってたの!」 「制服なんて誰が着ても同じだよ、お姉ちゃん」 入学式を終え、初めてのホームルームが終わると、今日は部活が休みらしいお姉ちゃんは教室まで私の様子を見に来てくれた。私以上にはしゃぐお姉ちゃんに苦笑いしながら、私はもらったばかりの新しい教科書を鞄に詰め込む。 私は、中学も高校もお姉ちゃんの後を追っていた。楽しい学校生活の数々の話を聞き、憧れを抱かないはずがない。ただ一つ違うのは、お姉ちゃんは運動部が目的で入学したけれど、私はそうではないという所だ。お姉ちゃんは小学生の時から地元の小学生バレー部に入っていて、中学も当然バレーの強い学校へ進学したかったのだ。中学バレー部でエースだったため、高校はスポーツ推薦で海常高校に決まった。スポーツができないとなれば勉強しかすることがなかった私は、お姉ちゃんとは真逆で推薦で進学クラスへの入学となった。 そして今このクラスにいるのだが、緊張のためまだ誰とも話すことができずにいた。中学の友人は皆、地元東京の高校へ進学したため、このクラスには中学の同級生は一人もおらず、心細さも感じている。けれどお姉ちゃんの他にあと一人だけ、私のよく知る人物がいた。 「さーん!ー!」 「叫ばなくても聞こえてるよ、涼太」 「そんな大きな声出してないですって!」 「涼太は普通に喋っててもウルサイの。の体に響くからよしてよね」 「さんいい加減過保護っスよー」 涼太くんもバスケ部が強いという海常に進学したのだ。お姉ちゃんと、涼太くんと、私。私たち三人は保育園の頃からずっと一緒なのだ。二人姉妹と隣の家の男の子という関係はもう十年以上変わらない。中学ならまだしも、高校まで同じになれたことは奇跡のようでありとても嬉しいが、私と涼太くんはクラスが全く違うため、心強いかと言われればそうでもない。それに、三人一緒になれて嬉しいと思う反面、複雑でもあった。間近でお姉ちゃんと涼太くんのやり取りを眺めている私は、実は心穏やかではない。 涼太くんはずっとお姉ちゃんのことが好きだ。それに初めて気づいたのは中学一年の時だっただろうか。憧れ以上の感情を持っていることに、私はいちはやく気付いた。恐らく、本人が自覚するよりもずっと早く。なぜかって、私も同じようにずっと涼太くんを見ていたからだ。涼太くんはお姉ちゃんが好きで、そんな涼太くんを私が好き。けれどお姉ちゃんには彼氏がいることを、涼太くんはきっと知らない。不毛な恋のサイクルが回り続けていることを、私だけが知っているのだ。 「もそう思うっスよね?」 笑顔のまま私に同意を求める。けれど、私に向ける笑顔と、お姉ちゃんに向けられる笑顔にはほんの僅かだが違いがあることを、私だけは気付いている。…涼太くんが好き。それは昨日今日のことじゃない。もう何年も何年も思い続けて来たのだ。涼太くんがバスケを始める前から、モデルをやり始める前から、もっとずっと前からだ。涼太くんは、私の初恋の人なのである。 *** 病気がちであることを言い訳にするつもりはないが、私はかなりの引っ込み思案で人見知り、内気な人間だ。お姉ちゃんや涼太くんのように明るく活発になれないし、友人もそう多くない。いつも二人を追いかけては転び、追いかけては転びを繰り返して来た。眩しいく輝く人間が二人もすぐ傍にいて、妬みこそしないがコンプレックスはある。二人が大好きだからこそ、自分に引け目を感じることが多々あるのだ。せっかく高校生になったのだから、そんな自分とは脱却しなければと思うものの、現実はそう上手くいかない。 入学して一週間、昇降口で久し振りに会った涼太くんの言葉に、私は固まった。 「、友達できたっスか?」 「うーん…どうだろう…」 涼太くんの問いに笑って誤魔化そうとしたが、それも上手くはいかない。私が涼太くんのことをよく知っているように、涼太くんもまた私のことをよく知っているのだ。 実はと言うと、自分の周りの席のクラスメートとも、碌に話をしていないのだ。席も後方の端っことあって、教室の真ん中で何かをしていてもそこに入って行く勇気が出ない。十五年付き合って来た性格とはなかなかお別れはできないようだ。 「中学が恋しくなっちゃった」 「中学に上がった時もそれ言ってたから大丈夫っスよ」 「うん…」 「部活とか入ってみたらどうっスか?文化系の部活ならでもできそうだし」 「そうだね。いろいろ調べてみる」 「応援してるっスよ。あと、何かあったらすぐ言うこと」 まるで妹にそうするように、私の頭をくしゃくしゃっと撫でた。背の高い涼太くんからすると私の頭は丁度良い位置にあるらしく、特に身長差が開いてからはよく私の頭を撫でたがる。涼太くんが好きな私にとって、それはかなり気恥しくもあり、嬉しくもあった。これだけは私の特権だ。年上であり、背の高いお姉ちゃんにはまさかこんなことはできない。だから、頭を撫でられている瞬間だけは、特別なものをいつも感じていた。それはもちろん、一方的にだけれど。 涼太くんの手が私の頭から離れると共に、様子を窺っていたらしい女子生徒数人が「黄瀬くんおはよう!」と声をかけて来た。そしてその場でおしゃべりを始めるので、私は涼太くんの目が離れた隙にそっとその場を去った。 涼太くんは元々かっこよかったけれど、モデルをするようになってから更に有名になり、中学の時もよく女の子に告白されていた。けれどそれに対しては私は何の危機感も持っていなかった。だって、涼太くんはお姉ちゃんしか見えていなかったのだから。一見遊んでいそうな感じはするけれど、実は一途であることを知っている私は、その他大勢の女子は脅威になり得なかったのだ。それよりも、私の一番近くにいるお姉ちゃんの方が、ずっと脅威ではあった。 (お姉ちゃんには勝てないや…) 私も、あの女の子たちも。そんなことを考える自分の性格の悪さにも一層嫌気が差し、私は涼太くんを振り返らずに教室へ向かった。 ←  → →(2013/01/30) |