
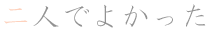
|
ふっと、水面に浮かび上がるかのように目が覚めた。そこで初めて呼吸を覚えたかのように、一つ大きな息をした。まだ頭はぼんやりするし、体も重い。ゆっくりと寝返りを打つと、大輝くんは私のベッドに凭れて雑誌を読んでいた。壁に掛かっている時計を見れば、もうお昼の十二時を過ぎている。三時間弱、私はぐっと眠っていたらしい。 「だいきくん…」 「おう、起きたか」 声色にも表情にも、数時間前までの険しさはない。起き上ろうとした私を手で制すと、「無理すんな」と言って大輝くんが立ち上がる。キッチンの方へ歩いて行ったかと思うと、何やらレンジで温めている。戻って来た大輝くんの手には、お粥の入ったお茶碗があった。一瞬作ってくれたのかと思ったが、なんてことはない、スーパーで売っているレトルトのお粥だ。湯気の立つそれをローテーブルに置くと、私が起き上るのを支えるように背中に手を添えてくれる。先程と打って変わって優しい大輝くんに、私は戸惑った。 ローテーブルの前に座ると、大輝くんがじっとこちらを見ている。そんな風にまじまじと見られることもないので恥ずかしく思っていると、そっと抱き寄せられた。熱のせいで汗もいっぱいかいたのにまずい、と思っても大輝くんは離してくれるはずがなく、また私も抵抗するだけの力も回復してはいない。 「お前が寝てから、落ち着いて考えた」 「え?」 「の方がキツイはずだろって。お前が人に甘えられねぇ性格なのはよく知ってるはずだったのによ」 「なに、いきなり」 「謝ってんだよ、さっきのこと。察しろ」 「そんな横暴な…」 大輝くんの肩越しに部屋の端を見ると、放り出されていたのは下世話な記事の書いてある週刊誌。どうやら大輝くんが見付けてしまったらしい。お節介な友人が「これあんたのことじゃない?」と言って見せて来たものだ。そこには大輝くんについても結婚についても散々に書かれていて、読んだことを泣くほど後悔した。だからと言って大輝くんとの結婚を取り止める気などさらさらないが、その記事が重くのしかかったのは事実。結婚と言うおめでたいはずの、祝福されるはずのものを非難される悲しさに泣いたことは一度ではない。なぜか、嫌でもそういった負の情報ばかりが私の目に留まるようになったのだ。 それでも、大輝くんに会う度に元気になれたし、気にしないでいられた。けれどここ数日、忙しくてメールや短い電話しかできなかったことが祟ったのかも知れない。体調まで崩すなんて。 大輝くんがいきなり謝るなんて、やっぱりあの記事を読んだのだろう。あんなもの、置いておかずにさっさと捨てるべきだった。 「これからもこんな思いをさせないとは約束できねぇ」 「うん」 「けど、俺がを手離せねぇんだよ」 「そんなの、私もだよ…」 支えたいと思いながら、いつも支えられていた。大輝くんだって大変なはずなのに、疲れているはずなのに、私が少しでも仕事で失敗すると話を聞いてくれたり、励ましてくれたりした。仕事が上手く行かなくて、注意されることが多くて、それで落ち込んだ時には一晩中傍にいてくれた。今日だって、きっとテツヤくんから話を聞いたのだろう、私の部屋まで飛んで来てくれた。 本当に私でいいのかな、不釣り合いじゃないかな、こんなにも不出来な女でいいのかな―――心配すること、不安なことは山ほどある。けれどそんな私をも受け止めて、結婚しようと言ってくれた大輝くんから、どうやって離れられよう。プロポーズされた時にどれだけ嬉しかったか、どれだけ幸せを感じたか、大輝くんには想像できるだろうか。 「私、大輝くんが好き」 「…おう」 「ほんとにほんとに、好き」 「わーったよ」 「ね、私、大輝くんでよかった」 「俺もで……って言わせんな馬鹿」 「えぇー…」 嬉しくて、ぐずぐずとした鼻声の私を抱き締めたまま、大輝くんは悪態をつく。 こんな私たちが良い。時々言い合いをして、すれ違ったりしてもちゃんと戻って来て互いを確かめ合える、そんな私たちが良い。せっかく温めてくれたお粥が冷めちゃうな、なんてことを頭の端っこで考えながら、私はまだ涙目で大輝くんにしがみついていた。 |
←
 →
→(2013/08/29)