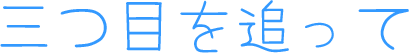|
「結城ー!差し入れー!」 部活開始直前、そんな叫び声が聞こえたかと思うと、は野球部のグラウンドの外から大きなスーパーの袋を投げて寄越した。入口の低いフェンスとはいえ、投げる奴がいるか、と呆れながらもキャッチする。すると、は「ナイスキャッチ主将!」と笑って見せた。 結構な重みのあるそれを開けてみると、“熱中症対策飴”が軽く十袋は入っていた。…はなかなか肩がいいな。 「部員数詳しく知らないから適当に買った!」 「結構かかったんじゃないのか?」 「人の好意に値段はつけられないんだよー」 あ、それと―――そう言ってごそごそと今度は鞄の中を探り出す。またフェンス越しに投げられても困るため、一旦フェンスの外に出る。 とは一年の頃から偶然にもずっと同じクラスだった。中学はほんの少しの差で学区は違ったらしいが、意外と家が近いことも知っている。そんなは度々こうして何かしら野球部に差し入れを持って来てくれるのだ。無理しなくていい、と言っても「私がやりたくてやってんだから!」と押し切られ、結局そのまま三年生になってしまった。 「はい、運動部と言えばやっぱりこれだと思って久し振りに!結城には特別ね、皆には内緒」 「内緒…」 「だって、今日は何の日か知ってる?」 「…いや、知らないが」 「ぷくく…今日は結城が一軍に入って初めて三振した日だよ」 おかしそうに笑いながら渡されたのはスポーツ飲料だ。初めて渡された時、「濃くて飲めないな」と言って以来ずっと水だったのだが、今日は本当に久し振りに出て来た。薄めて飲めばいいじゃない、とでも言いたげに口を押さえては笑う。 はまだ話を続けた。他にも覚えてるよ、と。俺が初めて打席に立った日、一軍に入って初めて試合に勝った日、試合で初めて一本もヒットを打てなかった日、主将に任命された日、準決勝で負けた日。頭のいいやつだとは思っていたが、並みの記憶力ではない。それを勉強に使ったらどうだ、と言えば「勉強に関しては足りてるからねこの頭」と自信たっぷりに言う。 「無駄な経験はないって言葉、私大好きだから」 「ああ」 「三振ばっかでも、練習試合ボロ負けでも、それどころか公式だったらコールドでも、盗塁失敗しても送球失敗してもね!!」 「今日は傷を抉って来るな…」 「むしろそう言う悪いことの方が覚えてるからね、私」 威張る所ではないだろう。やや呆れながらを見下ろすと、視線が合い、けれどすぐにすい、と逸らされてしまった。 他の部員たちは続々とグラウンドに集合している。俺との横を挨拶しながら通って行くのも二、三年は慣れたもので、も「こんにちはー」なんて笑顔で手を振りながら挨拶を返していた。それを見慣れていない一年生だろうか、遠くで何やらこそこそと話をしているのは。 そろそろ部活に、と言い出そうとした所で、は最後に言う。 「うん、だからなんていうのかな…常にかっこいい主将でいる必要はないよーって。かっこよかろうとよくなかろうと、結城は結城だし、私は応援してるからね!…って、いやまあ、野球部部外者の私が言うのも変な話だけど」 やや頬を染めて捲し立てるように言う。そんながおかしくて、まだ練習を始めていないきれいな手でくしゃりと髪を撫でてやった。こうすると、いつもははにかんで見せる。その顔がどうしようもなく好きで、一瞬心拍数が上がる。へへ、と笑うと「じゃあ今日も怪我しないようにね!」と言っては自分の部活に向かった。 本当はその後ろ姿が見えなくなるまでを眺めていたいが、そういう訳にも行かない。からの差し入れの熱中症対策飴は後で部員全員に配ろう。スポーツ飲料はどうすべきか悩んだが、どうせ練習中に飲むことはない。飴と同じ袋に入れてベンチの隅に置いておく。マネージャーに頼めばそのままそこに置いておいてくれるだろう。すると、目敏い亮介が声をかけて来る。 「さん、今度は何持って来たの?」 「熱中症対策飴だそうだ」 「まだそんな時期じゃないと思うんだけど。よくやるよね、さんも」 「もう三年だ」 ふうん、と興味あるのかないのか、適当な返事が返って来る。もう一度ベンチを振り返って、グラウンドに走った。「あーっ!」と一段と大きな叫び声が聞こえたかと思うと、今度は沢村が詰め寄って来る。 「さっきの先輩誰っすか!リーダーの彼女ですか!」 「沢村うるさいよ」 「いや、彼女ではない」 「哲も真面目に答えなくていいじゃん」 「でも予約はしてある」 「よ、よや…っ、よやく…!リーダーそれは一体どういう…!」 「へえ、それは俺も初めて聞いたな。ちょっと今度詳しく聞かせてよ」 「…練習始まるぞ」 話を切り上げて帽子をいつもより目深に被る。 予約なら、三年前からしている。一年の六月、俺はに告白された。俺もが気になっていた。けれど高校の間は野球に専念したいと、そうはっきりに言った。だから他のやつを見付けた方がいいと。だがは言う通りにはしなかった。「私がもうやだって思うまで応援する、好きでする、付き合ってなんて言わない」そう毅然と言い、今に至るのだ。だから、ああやってが野球部に差し入れを持って来ることも三年目に入り、俺は言った。引退したら付き合って欲しいと。 随分自分勝手なことを言ったと思う。それでもは泣いて喜んだのだ。普通だったら俺みたいなやつはすぐに諦められて当然だろうに、は今もまだ俺を追ってくれている。 (俺も、二つだけ覚えている日がある) が好きだと初めて言ってくれた日、俺がに待っていて欲しいと言った日。きっとのことだからそれも覚えているのだろうな、と思った。他とは違う、特別な日を同じように覚えているのは、案外嬉しいものだ。 引退したら、ということは今はまだ何も考えられない。目の前の野球のことしか考えられない。けれど、いつかにもう一度言える日は必ず来る。好きだ、と。それが三つ目の共有する特別な日になればいい。 |
(2014/07/27 パラダイム/アンダーグラフ)