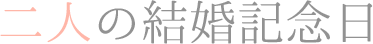
|
大輝くんは、誕生日とかナントカ記念日とかっていうのを覚えているタイプではなくて。盛大に私の誕生日を祝ってもらった覚えもない。女はみんなサプライズが好きだって言うけれど、私だって別に何か特別なことをして欲しい人間ではない。そりゃあ、してもらったら嬉しいのだろうけど、私が大輝くんに求めているのはそういった類のものじゃないから。 だから、残業が終わって二十時も回る頃、家に帰ってびっくりした。 「どうしたの…」 「どうしたもこうしたもねぇだろ」 いつも、私の方が仕事が遅く終わった日は、大輝くんは大体夕ご飯を食べ終えるか待っているかで、リビングのソファでテレビでも見ている。もしくは雑誌を読んでいるかのどちらかだ。それが、ダイニングのテーブルの前に一人、座っていた。そのテーブルの真ん中には私の好きなガーベラの小さなブーケ。大輝くんの席と、私の席の前には苺の乗った小さなショートケーキがちょこんと二つ、用意されている。 鞄を持ったままダイニングの入口で立ち尽くしていると、不機嫌そうに190数センチの大の男が口を尖らせる。 「てめ…覚えてねえのかよ」 「は、いや、何が…」 「結婚記念日」 けっこんきねんび、けっこんきねんび。口の中で告げられた単語をもごもごと繰り返す。数回噛み砕いた後、ようやく理解する。そうか今日結婚記念日か!と。 「なに、大輝くん、これ用意してくれたの」 「ああそうだよ」 「ケーキも?花も?」 「何回も言わせんじゃねぇ!」 「えっ大輝くんが?うそ?」 私のあまりの驚きっぷりに大輝くんはとうとう顔を引き攣らせた。 私たちはお互い忙しくて、すれ違う生活の方が一年の内に多くて、大輝くんがシーズンオフでも保育士の私にそんなものない。現実的な話をすれば、本当はものすごいバスケプレーヤーの大輝くんの収入があれば、私は働かなくてもいい程度の生活は余裕でできる。それでも保育士を続けたいという私の気持ちを大輝くんは尊重してくれた。本来なら私は家を守って、プロのプレーヤーである大輝くんを支えなければいけないのに、私の我儘に大輝くんは目を瞑ってくれている。例え食事の内容が雑になっても文句の一つも言わず食べてくれる。他のスポーツ選手の奥さんたちは栄養バランスを考えて勉強したりしているのに、私はそんなこと一つもしていなくて、本当は大輝くんの奥さんには相応しくないんじゃないかと何度も思った。 (そういう記事が、出回ったことも何回もあったし…) けれど、あの大輝くんがこうして結婚記念日を祝ってくれるということは、こんな準備をしてくれていたということは、めいいっぱい愛されていると自惚れて良いのだろうか。これからも、このままの生活でいいのだろうか。退職して家のことや大輝くんを支えることだけに専念しなくても、いいのだろうか。 「おい、何泣きそうになってんだよ」 「だって、私、何にも用意とかしてなくて…」 「別に、こういうのはしなきゃならねーもんじゃねぇだろ」 「でも大輝くんはしてくれた」 「それは、あー…俺がしたかっただけなんだよ。ったく、婚姻届出しに行った日も泣いてたよな、」 「なんでそういうどうでもいいこと覚えてんのよ」 大輝くんの癖に、バーカ。そう言うと、大輝くんは立ち上がって私の方へ近付いて来る。そしていつもはボールを自由自在に操っている大きな手のひらが、私の頬を包んだ。私のとは違う骨ばった手、マメだらけの手のひら、温かい温度。私の大好きな大輝くんの優しい一面だ。こうしてくれる時、大輝くんがくれるのは私のためだけの言葉。 「とのことでどうでもいいことなんか一つでもあるかよ」 喧嘩もする、小さな言い争いはもっとする。けれどそれ以上に何度でも好きになる。何度でも愛しくなる。こうして、時々見せてくれる大輝くんの優しさが、全ての不安や心配を真っ白にしてくれる。ああ、私は大輝くんを信じてさえいればいいんだって、そう思わせてくれる。 「大輝くん」 「ん」 「これからもよろしくね」 私も手を伸ばして大輝くんの頬に触れる。すると、大輝くんは屈んでこつんと額を合わせた。当たり前だろ―――そんなぶっきらぼうな言葉さえ愛しい。自信たっぷりに言う大輝くんに笑うと、同じように大輝くんも笑った。 私の選んだ相手は、私を選んでくれた相手は、こんなにも私を幸せにしてくれる。これからもたくさん、色んなことがあるだろうし、ぶつかることもあると思う。けれど大輝くんとならそれ以上に大きな大きな幸せを見付けられると、“大輝くんだから”という理由だけで確信が持てた。 今、私はこの世界中で一番幸せなのだ。 |
(2014/07/23 恋奏歌/アンダーグラフ)
