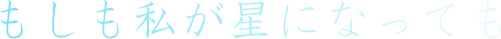
|
学校に到着する頃には、もうお昼休みに入っていた。教頭やエレンの担任の元へ謝罪に行き、理由を話すと怪訝そうな顔をされてしまった。こういう目は慣れている。頭痛薬を何度もを飲んでいる所をジロジロと見られもしている。個人の事情を理解してくれる人間ばかりではないのだ。社会に出てしまえば、なお。けれど当然、分かってくれる人もいるし、心配してくれる人もいる。向かいのデスクの先生は、朝からメールをくれていた。彼女にも理由を話し、もう大丈夫だと伝えるが、顔色の悪さをやはり指摘されてしまった。 そして今、携帯と睨めっこしている私は、さっきからリヴァイさんへのメールを打っては消し、打っては消しを繰り返している所だ。言い訳がましくないだろうか、今更ではないだろうかと不安ばかりがぐるぐると頭の中で渦を巻く。けれど、もう何を打っても仕方がない。とにかく「いつでも良いので会って話がしたいです」とだけ打ち込んだ至って簡素なメールを、最終的に送信した。それから一分と経たない内に彼からのコールバックがあった。 「ちょ…っ、ちょっと待って下さい、移動します…!」 『時間がねえ、そこで聞け』 「え、ええ、えっ」 『俺は今日会議で帰りが遅い、二十時は回る。迎えに行くから家で待っとけ』 「へっ」 『じゃあな』 待って、と言おうと思ったのに、言葉を挟む隙もなく電話は切られてしまった。随分と早口で言われた約束を頭の中で繰り返す。会議で二十時は回るから家に迎えに行く―――思えば、これが初めての約束だ。いつもは突然休日に「暇だろ、付き合え」と押しかけて来てばかりだった。これが最初で最後にならなければいいと思いながら、携帯をぎゅっと握り締める。 なんだか、力が抜けてしまった。確かに忙しかったかも知れないが、開口一番もっと何か言われるかと思ったのだ。メールも無視し、電話にも出なかった私に、文句の一つや二つ、いや三つや四つはあるかと思った。けれどそう言ったものは一切なく、ただ一つ、押し切るように約束を取り付けた。 先生は今日、ぶつかって行くことはそんなに難しくないと言った。それは、案外本当なのかも知れない。 *** 仕事を終えて帰宅すると、エレンが夕飯を待っていた。エレンはいつも宿題より夕飯が先だ。 今からなら、エレンの分の夕飯を作っても約束の時間に間に合うだろう。私が食べられるかどうかは怪しいが。冷蔵庫から玉ねぎを取り出しながら、私はエレンを振り返った。 「二十時過ぎにちょっと出掛けて来るね」 「今日倒れたばっかだってのに元気だな、姉ちゃん」 「そんなに遅くならないから」 「おー」 エレンの良い所は食べ物の好き嫌いがない所だ。だからいつも夕飯のメニューに悩まずに済む。手抜きにはなってしまうが、ちょうど冷蔵庫の中を見てみるとカレーを作れそうだったため、必要な野菜を追加で取り出した。 滅多に家で携帯を触らない私だけれど、今日ばかりはいつリヴァイさんから連絡が来るか分からないため、冷蔵庫の上に置いてちらちらと見ていた。カレーのルーを入れて煮込みながらも、目は携帯へ。そろそろ良いか、と火を止めた所でまるでタイミングを見計らったかのように携帯が震える。メールを見ると、「五分で下へ降りて来い」と相変わらず横暴ながらも彼らしい一文。 「じゃあちょっと行って来るから、ごめん、自分でよそってくれる?」 「えっマジで」 「それくらいできるでしょ」 「お、おう」 なんで自信なさげなの、と思わず苦笑いしながらエプロンを外す。五分、五分、と時計を見ながら用意しておいた鞄を引っ掛けた。多分、エレベーターを待つより走った方が早い。そう言えばこういうの、久し振りだ。以前はよく突然土日に呼び出されていたが、最近は私がずっとリヴァイさんからの連絡を無視していたから。 今度こそ何か言われるだろうな―――そう思いながらエントランスを出ると、車に凭れながら彼は立っていた。別段、不機嫌な様子はない。怒っている風でもない。肩で息をする私を見て一言、「久し振りだな」と言った。はい、と返事をするのが精一杯で、階段を一気に駆け下りた足はガクガクと震えている。リヴァイさんは一歩二歩と私に近付き、何も言わずに私を抱き締めた。 「そんなに悩ませてるとは思わなかった」 「え…?」 「俺はまたお前に会えた、それだけで良かったんだ」 絞り出すような声が、耳のすぐ傍で聞こえる。強い後悔を孕んだ声だった。その背中に恐る恐る手を回すと、彼の腕の力は更に強くなった。アパートのエントランス、そんなことも忘れて、空白になってしまった時間を取り戻すように私たちは抱き合った。 私だって、もう一度出会えただけで良かった。一目見た瞬間にこの人だと分かった、直感だった。それなのに、どんどんと距離は近付き、引き返せない感情を知り、けれどこれは独り善がりなのではと悩み、結局この人から逃れられない事を知る。抱き締めれば抱き締める程、けれどそれは私だけじゃなかったのだと伝わって来た。 「リヴァイさん」 「なんだ」 「好きでした、ずっと」 「ああ」 「ずっとです、ずっと」 「…ああ」 やっと言えた言葉。私の頬を涙が伝う。この一言を言うために、私はもう一度この世界でこの人に出会わせてくれたのだろうと、普段は信じてもいない神様に感謝をした。 ずっと、ずっと―――それは過去も、今も、そしてこれからも。私が私としてこの魂が廻る度に思い出すのだろう。今自らの腕で感じているこの人こそ、私が誰よりも探し求めている人なのだと。 |
←
 →
→(2014/06/12)